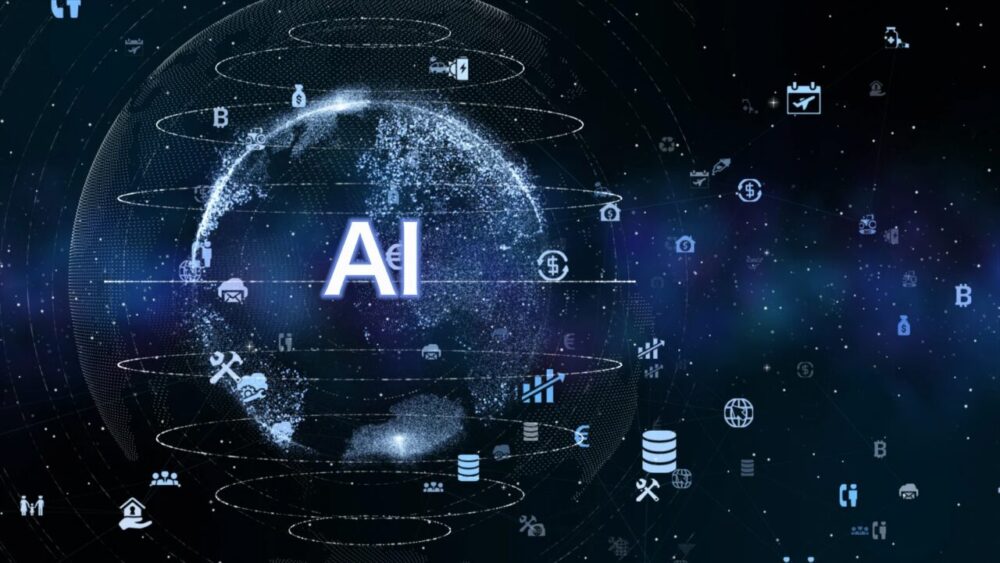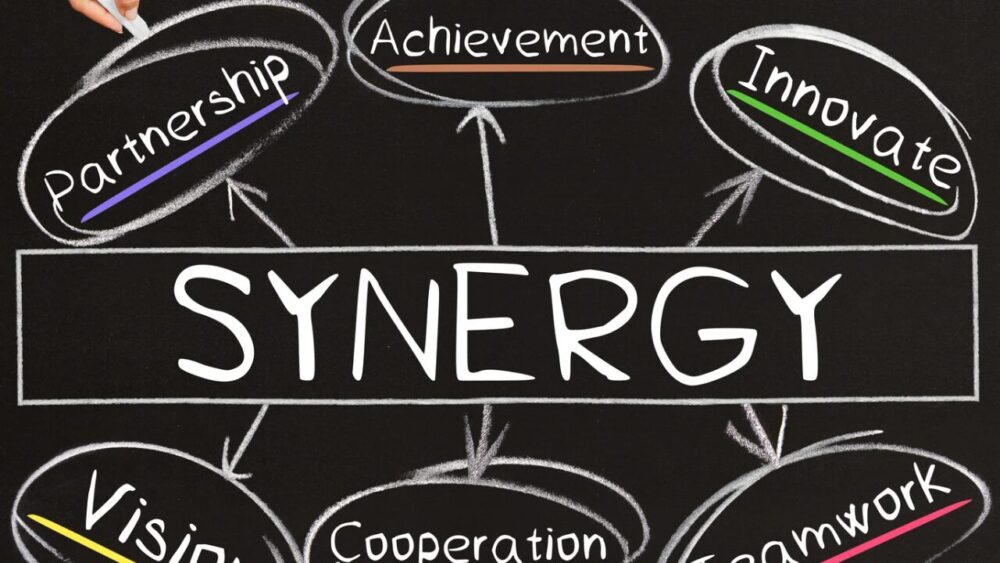エヌビディアが切り開くAIロボットの夜明け、僕らは何を思う?
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
時価総額で世界1位にもなった半導体メーカー、エヌビディア(NVIDIA)がロボット開発向けのAI技術を無償で提供するよ、というニュースが出ました。ロボットが人間みたいに動いたり、コミュニケーションしたりする未来が近づいているのかもしれない。こんな話を聞くと、たとえば「荷物を運んでくれるAIロボット」がパッと思いつきますが、じつはそこにとどまらない大きなうねりがあるような気がします。
AIといっしょに悩みを分かち合える?
いまはChatGPTなどの生成AIが身近になりはじめました。たとえば、会議資料をまとめたり、企業の戦略アイデアを聞いたりしても、わりとちゃんと答えてくれる。人がやりとりしているのか、AIとやりとりしているのか、ふとわからなくなる瞬間だってある。「意外と、こっちの意図を汲んでくれているかも?」と思うこともある。そんな風に感じられるのは、AIがただ事務的に作業するんじゃなく、僕らの“コミュニケーション相手”になりはじめているからではないだろうか。
これがさらに進んだ先には、もしかすると「AIロボット秘書」が登場し、「AIコンサルロボット」として助言やアドバイスをしてくれる未来も待っているかもしれない。それが現実になるなら、就活中に「わたしの自己PRはどうかな?」と相談する相手が、いつかはAIロボットになっているかもしれないです。

それでも、人にしかできないこと
ただ、すべてがAIで解決できるわけではない。人って、悩みのなかでも言語化できない部分にこそ、本質があったりする。ちょっとした雑談や、なんでもないようなおしゃべりが、じつは大きな気づきにつながっていたり。たとえば面接のあと友人に「どうだった?」と話すとき、言葉に詰まりながらでも自分の考えを整理していることがある。そういう“揺れ動き”は、まさに人間の経験。
でも、もしAIロボットが、そのたわいもない会話のやりとりにもうまく付き合えるようになったら? たとえAIとわかっていても、“人として”安心して対話できるデザインがなされていたら? 意外と人同士のコミュニケーションに近い感じで、自分の頭のなかを整理してくれるかもしれない。
AI差別? そんな場合じゃない
いまクリエイターの世界でも「AI差別」があるように感じる。「AIが作ったものは所詮AIだから」と、あまり評価しない人もいる。でも、効率という観点からみると「どうしても勝てない部分がある」と気づくべき。これは単に「AIに勝てないから諦めよう」という話ではなく、「人にしかできない価値は何なのか」を問い直すいい機会かもしれん。
この問い直しは就活においても大事だ。世の中が大きく変わるときこそ、自分が何を大切にしているかがハッキリ見えてくる。募集要項や待遇ばかり気にするのではなく、AIに負けない自分の人間らしい部分を見つめ直す。AIができることが増えれば増えるほど、人がやる意味のある仕事やコミュニケーションの本質が、もっと明確になっていくはずなんだから。
僕らにしかできないこと
ロボットやAIが、まるで人間みたいに動きはじめる。このニュースは、驚き以上に「僕らは何を人間の強みだと思っているのか?」という問いを突きつけてくれます。就活生のみなさんにとっては、ここがチャンス。自分の言葉で話し、自分にしかない思考をまぜこんで語る。それはAIになかなか代替できない“人間ならでは”の力のはず。
今後、AIはさらに高度になり、みなさんの就職活動や仕事をサポートしてくれる存在になるかもしれない。でも、そのとき「僕らでなければできないこと」がきっとある。逆に、AIに任せられることは任せて、僕らが“本当にやりたいこと”に集中できる時代も来るかもしれません。
ちょっと未来を想像してワクワクする。それがどんな世界かはわからないけれど、少なくとも「僕らにしかつくれない何か」があるはずです。ロボットが動き出す時代だからこそ、人がやるべきこともまた、はっきり見えてくるんじゃないか。
Vamos学生メンバーとして一緒にWebマガジンの運営にチャレンジしてみませんか?
Vamosの一員として企業取材を進めていくと、自然と業界研究やマーケティングスキルが身につきます。すでに多くの学生が参加しており、インタビュー経験を就活に活かしている人も多数! 詳しくは参加者の体験談をリンクからご覧くださいね。参加希望は、Vamos公式LINEに「説明会参加希望」と送信するだけです。