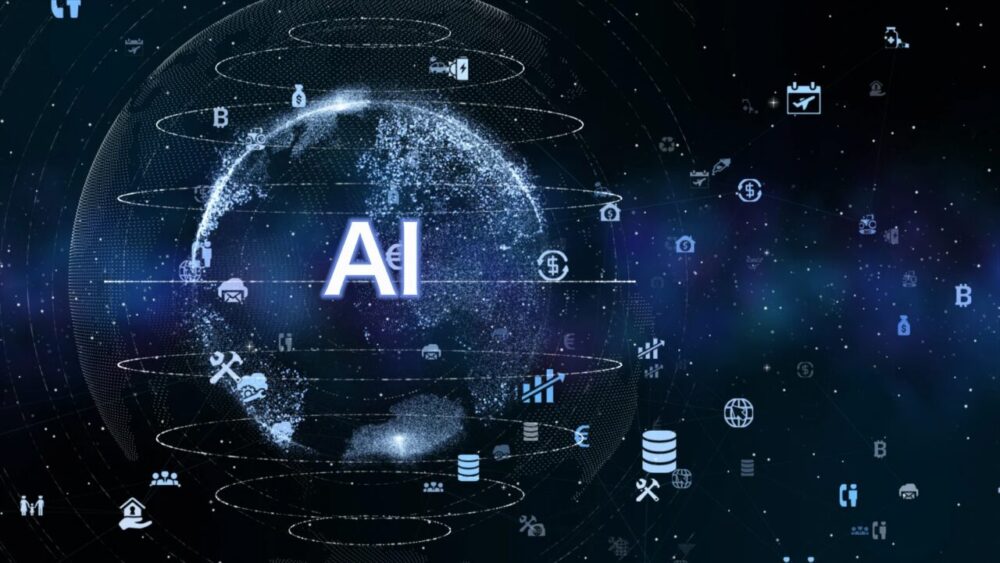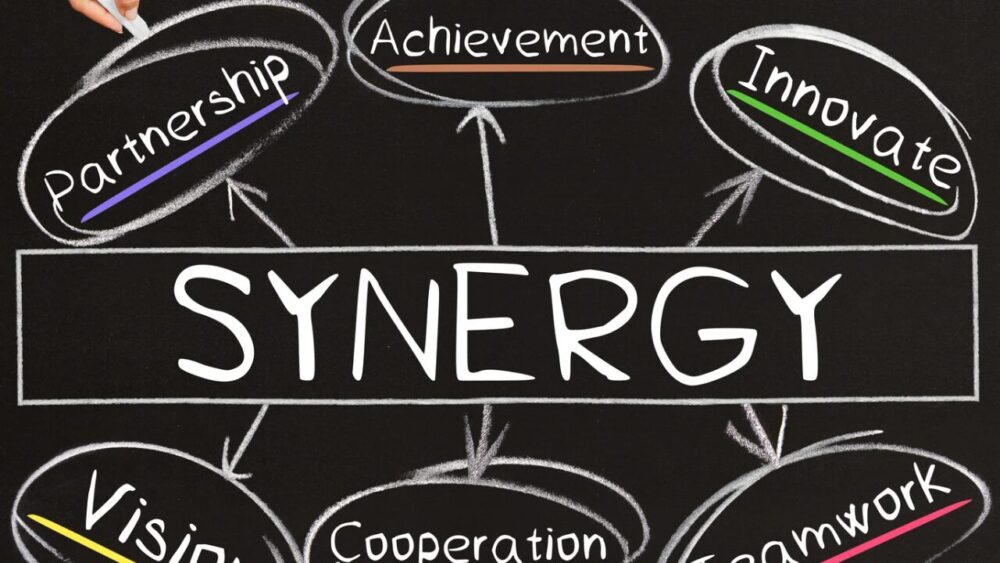「荷物が動く」の奥にあるもの
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
物流コスト10%増なら… 物価0.2%押し上げ:日本経済新聞
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
「物流」って聞くとどうしても、“運ぶ”とか“倉庫の中を行ったり来たり”みたいなイメージで終わっちゃいがちです。でもじつは、それだけじゃない。むしろ、わたしたちの日常を支えている存在なんです。
今日紹介する日経新聞の記事でも「2024年問題」って呼ばれているトラック運転手さんの残業規制のことや、物流費が10%上がると物価が0.2%上昇するという話が出てきています。特に飲食料品の値段がグッと上がりそうだとか。これ、地味に大きな話なんです。
いま、もしもあなたがコンビニで手に取ったおにぎりやパンが、以前に比べてちょっと高くなっていたら。もしかすると、それは「運賃が上がったから」かもしれない。そんなふうに考えるだけで、あの「運んでくれるトラック」や「小さな荷物を集める仕組み」が気になってきませんか。
モノは、誰がどうやって運んでいる?
サプライチェーンって言葉知っていますか?たとえば「工場から原材料を運ぶところ」「それを商品に加工するところ」「商品を在庫として管理するところ」「お店まで流すところ」──そんな一連の流れが、一つの“鎖”としてつながっているイメージ。ざっくり言えば、これがサプライチェーン。
なにか一箇所だけで大問題が起きても、それが商品価格に影響したり、お店からモノが消えてしまったり。まるで鎖のどこかが切れると、一気にみんなが転んでしまうドミノ倒しです。だからこそ、みんなで協力して強い鎖を作り直そうという声が聞こえてくるのも自然なこと。今そんな声がものすごく叫ばれているってことを知っておくといいです。
10%の物流コストが、0.2%の物価上昇につながる
内閣府によると、もし物流費が10%も上がってしまうと、世の中の物価が0.2%ほど押し上げられるんだそうです。ピンとこないかもしれないけど、0.2%という数字も、積み重なるとけっこう無視できない。その物価上昇の多くを占めるのが飲食料品で、つまりは毎日のごはんや飲み物が少し高くなる。
なぜ飲食料品がいちばん影響を受けるかって? そりゃあ、大量に運ぶ上に鮮度も重視しなきゃいけないから、物流に依存する部分がめちゃくちゃ大きいのです。たとえば、朝に搾られた牛乳が夜には店頭に並んでいるのって、物流の方々が休まず動いてくれているおかげ。
「2024年問題」トラック運転手の勤務時間が変わる
2024年から、トラック運転手の残業は「年960時間まで」と定められることになりました。それでも残業が多いと感じると思います。本当に運転手の皆様には感謝です。これまで正直なところ“長時間労働”でがんばっていた部分を、見直さなきゃいけないわけです。健康を守るためには大事なルール。でも、そのぶん人手が足りなくなったり、輸送効率をあげなきゃいけなかったり。
あっちを立てればこっちが立たない──そういう綱渡りの時期だからこそ「共同輸送」や「効率化」を進めようって動きが加速しています。たとえば、飲料メーカーとお菓子メーカーが一緒にトラックを使って、荷物の空間をうまく埋めあう工夫をしたりしているのです。
デジタル化&見える化で生まれる未来
さらに大事なのが、サプライチェーンの“見える化”です。ITを活用して「どこに在庫があって、いつ頃どれだけ運べばいいか」をリアルタイムで把握する。それができると、無駄な走行が減ってCO₂削減にもつながるし、人手不足も多少はカバーできる。
「物流=トラックだけ」じゃないんだとわかる瞬間です。データサイエンスやAIが絡むし、調整に必要なコミュニケーションスキルも重要だし、国際物流まで視野に入れれば、語学力も求められるかもしれない。こうした幅広い可能性を秘めているのが、現代の“物流”なんですね。

「物流目線」で考える就活
就活というのは、どうしても「自分がどこで働くか」を考えがちです。
物流って、表舞台の華やかさはないかもしれない。だけど、現実には生活必需品を運び、スーパーの棚を満たし、商品が切れないように支えている。気づかないところで、社会がうまく動くようお膳立てをしているんです。
就活で「社会貢献をしたい」と言う人はたくさんいますよね。でも、そのカタチは実は色々あって、物流のように“縁の下の力持ち”で貢献する道もある。そこにやりがいを感じられる人は、必ず活躍の場が見つかるはず業界でもあるわけです。
国境と時間を超える発想
サプライチェーンはグローバルにつながっています。輸入品が遅れれば日本の物価や小売りに影響が及ぶし、逆に日本から海外へ輸出する仕組みを整えるのも重要な仕事。世界がつながっていると実感するには、物流のことを考えるのがいちばんわかりやすい。
これからの時代、企業研究をする際には「この会社は、原材料をどこで調達して、どんなふうに輸送しているの?」といった部分にも目を向けてみると、思わぬ面白さや強みが見えてくるかもしれません。
トラックを眺めながら、思うこと
道ばたでトラックを見かけるたび、学生の頃の上杉は「ああ、なんかたくさん荷物が載ってるんだろうなあ」とか、「運ちゃん大変だなあ」くらいに思うだけでした。でも今は違います。「このトラックの中には、いろんな人の暮らしが積まれているんだ」と考えるようになりました。きっとこのVamosのお仕事の中でいろんな企業さんたちと関わりを持たせてもらったからかなと。
就活をするうえで、「物流という社会の血液を回す仕事」は、決して運転だけではありません。調達、生産、在庫管理、IT活用、マーケティング、国際感覚……あらゆる要素が絡み合って、はじめてわたしたちの生活がスムーズにまわっていく。それをトータルに考えるのがサプライチェーンであり、そこには多種多様な関わり方があります。
「自分の仕事って、何の役に立つんだろう?」と考え込むことがあるかもしれません。でも、物流を学んでみると、その答えが意外と身近に隠れているかもしれない。「自分の得意を、誰かの助けに変えられる場所がある」──それが“物流とサプライチェーン”という大きな世界なんだと思います。
「就活で見る世界は広いほうがいい」ってよく言われます。もし、ちょっと視野を広げたいなと思ったときは、道ばたを走るトラックに意識を向けてみてください。そこに積まれているのは、あなたが今日食べるかもしれないパンや、あなたの家族に届くプレゼントかもしれませんから。
そんな考え方をしてみるとすべての仕事が素敵に見えてきませんか?
Vamos学生メンバー募集
Vamos学生メンバーとして一緒にWebマガジンの運営にチャレンジしてみませんか? Vamosの一員として企業取材を進めていくと、自然と業界研究やマーケティングスキルが身につきます。すでに多くの学生が参加しており、インタビュー経験を就活に活かしている人も多数! 詳しくは参加者の体験談をリンクからご覧くださいね。参加希望は、Vamos公式LINEに「説明会参加希望」と送信するだけです。