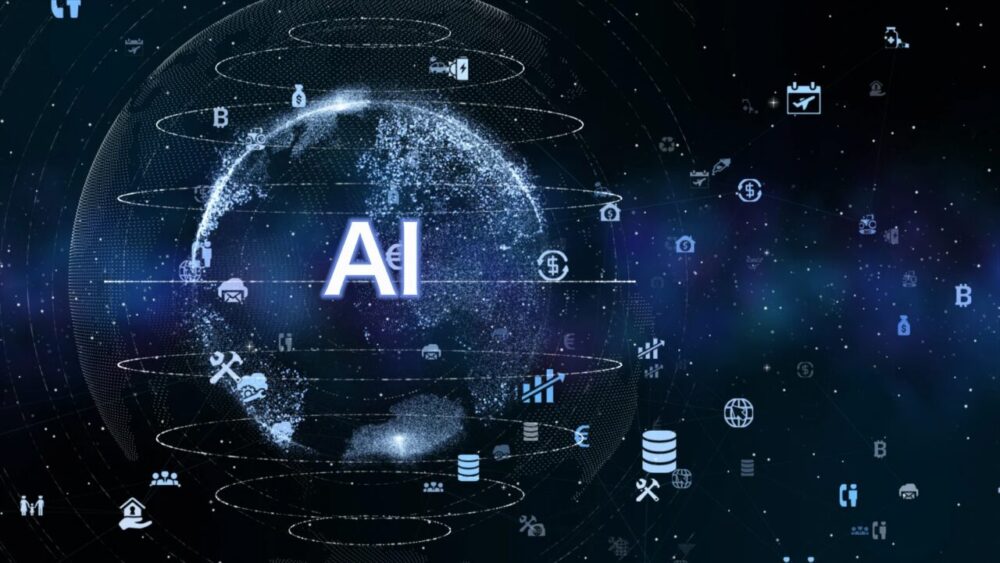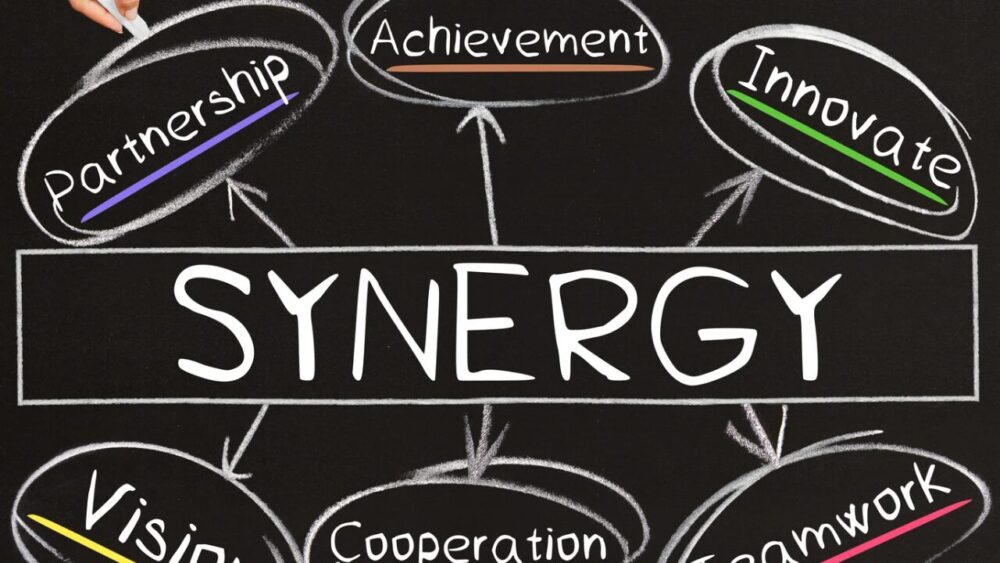デフレ脱却への挑戦と、コンビニのいま
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
日本経済が長く悩まされてきたデフレ。その脱却を目指す流れのなかで、「ちょっと高くても便利さで勝負する」という姿勢を定着させたのがコンビニだと、ぼくは思っています。モノの値段を“安いか高いか”だけで判断する時代から、「便利なものはある程度の対価を払ってもいい」と意識を切り替えるきっかけをつくってくれたのが、深夜でもお弁当が買えたり、公共料金の支払いができたりする“コンビニ”の存在だったわけです。
ところが、今回の日経新聞の記事を見てもわかるように、セブン&アイ・ホールディングス(以下、セブン)がコンビニ事業の不振で苦しんでいる。これは、「デフレ脱却ってそう簡単じゃない」という現実を突きつける事態でもあるように感じます。安売りを得意とするドラッグストアやスーパーマーケットが勢いを増し、消費者の懐事情も厳しくなるなか、コンビニまでもが値段重視の流れに巻き込まれようとしている。でも、そうなると本来の“コンビニらしさ”がどんどん薄まってしまう──そんなジレンマが見えてきます。
コンビニ業界が直面している、「安さか、利便性か」という課題を掘り下げていきながら「安いほうが喜ばれるのはわかるけど、それだけでいいの?」ってことを話ししていきます。そのまま就活やキャリア選択にも通じる大きなテーマかなと思っています。
コンビニが牽引してきた“ちょっと高くても便利”の世界
長引くデフレの真っ只中、「できるだけ安く」という消費者心理が当たり前になっていた日本。そのなかで、あえて価格を下げすぎず、“便利さ”という付加価値を提供してきたのがコンビニでした。たとえば、深夜にのどが渇いたらサッと買いに行けるし、お弁当やお菓子はいつでも新鮮なものが並んでいる。深夜・早朝でも公共料金を支払えるし、宅配便の受け取りもできる。こうした「少し高いけれど、そのぶん時間と手間が節約できる」という発想を浸透させてくれたのがコンビニであり、その動きは“デフレ脱却”を目指す日本社会において重要な役割を果たしてきました。
デフレ脱却の旗手がデフレの波に呑まれるジレンマ
しかし、ここ数年で状況は一変。ドラッグストアやスーパーマーケットが低価格路線を強化し、さらにネット通販でさえ生鮮食品や日用品を素早く届ける時代になりました。となると、消費者の目線はまた「安さ」へと回帰してしまう。「とにかく安いほうがいい。便利さはそこそこでも大丈夫」という雰囲気が高まってきて、セブンをはじめとするコンビニ業界も「値ごろ感」を打ち出さないと厳しくなってきたわけです。
そもそもコンビニって「利便性を買う場所」です。何度も言いますが、ぼくたちがコンビニで求めるのは、深夜・早朝でもふらりと立ち寄れて、必要なものがすぐ手に入るという気軽さのはず。ドラッグストアやスーパーのように「とにかく安さで勝負」というわけではない。だから、少し値段が高めでも納得できる。要するに「時間や手間をお金で買っている」イメージです。
ところがいま、コンビニも「安さ」に引っ張られつつある。セブンの「うれしい値!」という低価格商品拡充は、その典型例のように感じます。消費者の経済状況が厳しく、みんなが財布の紐を固くしている以上、仕方のない面もある。でも、それでコンビニが安売り競争に加わってしまったら、“コンビニらしさ”を捨てるのに近い状態になってしまうのではないか──そう感じる人も多いはずです。

デフレ脱却の象徴が「デフレの波」に追いかけられる皮肉
「高くても便利で稼ぐ」構造をつくりあげ、デフレ脱却の道しるべのような存在のコンビニ。しかし、ここ数年でドラッグストアやスーパーという強敵が立ちはだかり、消費者の「安くしてほしい」という声に応えようとすればするほど、デフレ志向に巻き込まれていく。まさに「デフレ脱却を牽引してきた存在が、デフレの大きな波に呑まれている」ような図式が見えてくるわけです。
コンビニ業界が抱える課題が、就活生に教えてくれること
「それで、どうしてこれが就活やキャリア選択の話につながるの?」
じつはコンビニが抱えている「安さか、利便性か」というジレンマは、わたしたち個人にも重なる部分があるんです。
安さで勝負できないなら、何を武器にするか
ドラッグストアやスーパーに匹敵する安さをコンビニが求められても、なかなか勝ち目は薄いでしょう。では、どうするか。やっぱり選択肢は「利便性」で勝負するしかない。自分の強みを活かし、スピードや手軽さやサービスの広がりで差別化する。これは、就活生が「自分をどう売り込むか」を考えるときにも通じる話だと思うんです。
たとえば、学歴や資格で勝負するのは、ものすごくハードルが高い。そういう人がゴロゴロいるから。でも、あなたにしかない経験や、「この瞬発力は誰にも負けない」という特技があるなら、そこを前面に押し出すほうがいい。つまり「自分にしかない価値って何だろう?」を突き詰めるのが大事なんじゃないか、ということです。
「自分らしさ」とは、“少し高め”でも選ばれる理由
コンビニは本来、「便利という価値」で“ちょっと高め”でも選ばれてきました。これ、個人で言えば「自分らしさや個性」という価値だと思います。それがあれば、たとえ全体のスペックが同程度でも「あなたがいい」と選んでもらえる。逆に、個性を捨てて“学歴・資格・世間体”を追求する生き方をすると、競合は山ほどいるし、そこから抜け出せなくなる可能性が高い。
こう考えると、セブンの悩みは、そのまま就活や人生の悩みに重なる気がします。みんなが「安い・安い」と言い始めた時に、自分はどう戦うか。それは、「自分の価値をどう伝えるか」という問題に他ならないはずです。
デフレ脱却とは、「サービスの本質を磨くこと」かもしれない
セブン&アイは、米国の不採算店閉鎖やネットスーパーの撤退など、大きなリストラを進めています。苦しい決断ですが、そのなかで「コンビニ専業戦略」を打ち出し、資源を集中投下しようとしている。要は、「本当に稼げる柱を強化するしかない」という覚悟です。これからのコンビニは、ドラッグストアやスーパーと同じ土俵で戦うのではなく、“時間を買う”サービスをもっと進化させる方向へ行くのかもしれません。
ぼくたち個人も同じではないでしょうか。「なんでもかんでも安売り」で生き延びるのか、本当に自分が得意とする分野で勝負するのか。ときには思い切ったリストラ──つまり、不必要になった部分を切り捨てる勇気が必要になるかもしれません。“コンビニらしさ”をアップデートしていくセブンの動きは、「自分の得意分野や好きなことに絞って伸ばす」という道を選ぶことに重なるように見えてきます。
「安さ」ではなく「新しい価値」を
デフレ脱却のカギは「モノやサービスにお金を出す価値がある」と思ってもらうこと。コンビニが“時間や手間を省く”ことの価値をさらに成長できれば、たとえ値段が多少高くても「そのほうが助かるから」と選ばれるかもしれない。逆に、中途半端に安さを追求してしまえば、ドラッグストアやスーパーに埋もれてしまうかもしれない。そこを生き抜くために、セブンは構造改革を急いでいるように見えます。
就活生も同じです。面接で「私はどんな場面で、どんなふうに周りを助けられる人なのか」「どんな強みを買ってもらうのか」を明確に示すことができれば、多少スペックで負けていても“本質的”な魅力で勝てる可能性がある。値段(=スペック)ではなく、「自分にしかないサービス」を提案していくことを忘れないでください。
Vamos学生メンバー募集
Vamos学生メンバーとして一緒にWebマガジンの運営にチャレンジしてみませんか?さまざまな企業へのインタビューを通じて“現場の声”を直接学ぶことが可能です。就活に有利なだけでなく、自分の視野をグッと広げるいい機会にも。参加学生のリアルな声はリンク先にたくさん載っていますので、ぜひご覧ください。気になった方は、Vamos公式LINEに「説明会参加希望」と送るだけで始められます!