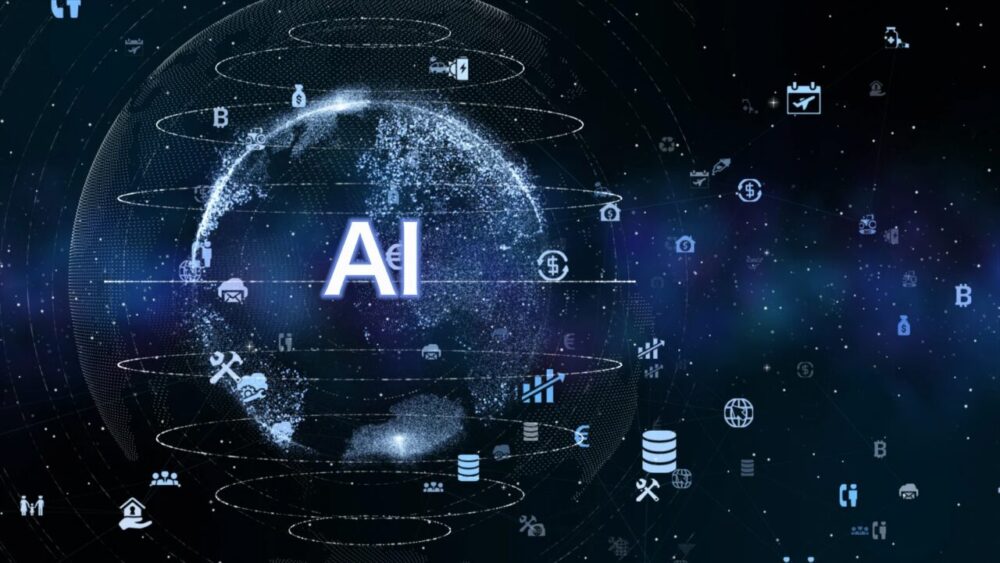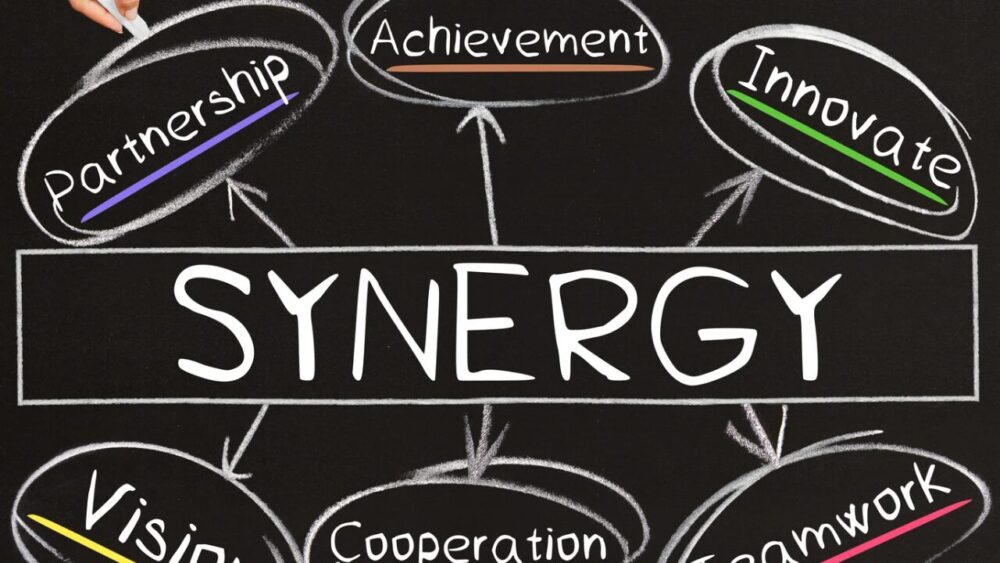「NFT」って、そもそも何?
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
SBIトレーサビリティやプログマという企業が、日本のウイスキーをNFT(非代替性トークン)として流通させる試みを始めるという記事。
でもまず「NFT」がまだピンとこない人もいると思うので、簡単に説明してみますね。
NFT(Non-Fungible Token)というのは、「代替不可能なトークン」のこと。ちょっと難しく聞こえますが、要は「一つひとつ固有のIDを持っていて、デジタルの世界で唯一無二の“所有権”を証明するもの」というイメージです。
これまでは「デジタルの画像や音声ファイルはいくらでもコピーできて、持ち主が誰かなんてわからない」と思われていました。だけどブロックチェーンという仕組みを使って発行・管理することで、「これはあなただけのものですよ」というのを証明できるようになったのです。しかもその記録は改ざんが極めて難しいので、安心感がある。
たとえばデジタルアートの世界では、作品をNFT化して売買することで、所有者をハッキリさせることが可能になりました。これがいま、「リアルなモノ」にも応用されはじめている。ウイスキーみたいな資産性のある商品をデジタル上のNFTとして持っておけば、実物をわざわざ動かさなくても、「自分が持ち主です」と証明できるわけです。
なぜウイスキーがNFTと結びつくのか?
今回の記事では、日本のウイスキーをNFT化して流通させる試みが紹介されていました。そもそもウイスキーは時間をかけて熟成されることで価値が上がっていく、いわゆる「寝かせるほど深まる」お酒ですよね。何年もかけて育まれる分、完成前から投資や資金調達をするのがむずかしい側面もある。
だけど、「NFT化」することで、まだ完成していないウイスキーを買うことが可能になる。さらにそれを売買する人同士は、ウイスキーを移動させることなく、デジタル上で所有権を受け渡しできるんです。これが海外投資家にとっても大きな魅力。遠い国に暮らしていても、ウイスキーを“所有している”事実だけを手軽にやりとりできるようになるわけです。
今回、鹿児島県の小牧醸造が屋久杉のたるでつくるウイスキーを対象にNFTを発行しようとしているとのこと。完成するまで資金を集められるだけでなく、完成後に市場価値が上がったタイミングで、NFTの取引で利益を得ることも可能になる。こうした動きはウイスキーだけにとどまらず、日本酒や絵画、伝統工芸品などに広がっていくかもしれません。
NFTとブロックチェーンで変わる「持ち方」の未来
NFTの背景には「ブロックチェーン」という仕組みがあります。これは、世界中のコンピュータ同士が取引記録を分散して管理する仕組み。特定の管理者がいなくても「これは誰が持っている」といった記録が正しく維持されるので、紙の証明書よりも安全性と信頼性が高いとされています。
しかも、たとえば「ウイスキーを海外の誰かに譲りたい」となっても、現物を送る必要がない。NFTをポチッと送るだけで、相手が正真正銘の所有者になる。この「持ち方」の変化が、これからさまざまな産業の流通や投資スタイルを変えていくかもしれないんですね。

就活生にとっての「NFT的な考え方」
ここからは、ちょっとぼくが感じたことを話してみますね。
NFTなんて聞くと、「最先端テクノロジーで何か難しそう…」と思うかもしれない。でもいちばん大事なのは「何がしたいか」というところだと思います。ウイスキーを好きな人に「完成前から応援してもらいたい」と思う心とか、世界中にその魅力を広めたいという情熱とか。
そうした想いと技術が合わさると、いままでなかった流れが生まれる。それがNFTの面白さなんじゃないかと、ぼくは考えています。
就活生の方々がこれを読むと、「自分の進む分野に関係ないや」と思うかもしれない。でも、何か新しい仕組みや概念を知ったときには、いつでも「自分のフィールドに当てはめるとどうなる?」と想像してみるといい。たとえば料理が好きな人なら、「食材の産地や育て方をNFT化したらどうなる?」とか。アパレル志望なら、「服のサステナビリティ情報をブロックチェーンで共有できたら?」なんてね。
いろんな業界で「持ち方」や「所有のかたち」を再発明するキッカケになるのが、NFTというテクノロジーだと思うのです。
「持つこと」とは「物語を持つ」こと
結局のところ、ぼくたちが何かを「持つ」ときって、必ずしも物質的な“モノ”だけを持っているわけではないように思います。そこには「こうなったらいいなあ」という期待や、「こんなふうに使って楽しみたい」という物語も含まれている。
NFTは、そういう物語や価値をデジタルの形でやりとりできる仕組みなんじゃないか。特に、時間をかけて醸されるウイスキーみたいな存在とは相性が良さそうです。
NFTやブロックチェーンの最新動向が直接あなたの仕事に関わるかどうかはわかりません。でも、「リアル」と「デジタル」が混ざり合って新しい価値を作る流れは、これからどんな仕事の場面でも大きなインパクトをもたらすはず。もしよかったら、自分の興味や専攻とNFTを結びつけて、未来のビジネスやサービスを妄想してみてください。
きっとそれは「ただの投資商品」の話じゃなくて、「ああ、こういう形で人と人とがつながるんだなあ」という楽しみ方につながるんだと思います。
Vamos学生メンバー募集
Vamos学生メンバーとして一緒にWebマガジンの運営にチャレンジしてみませんか? Vamosの一員として企業取材を進めていくと、自然と業界研究やマーケティングスキルが身につきます。すでに多くの学生が参加しており、インタビュー経験を就活に活かしている人も多数! 詳しくは参加者の体験談をリンクからご覧くださいね。参加希望は、Vamos公式LINEに「説明会参加希望」と送信するだけです。

Vamos公式LINEはこちら