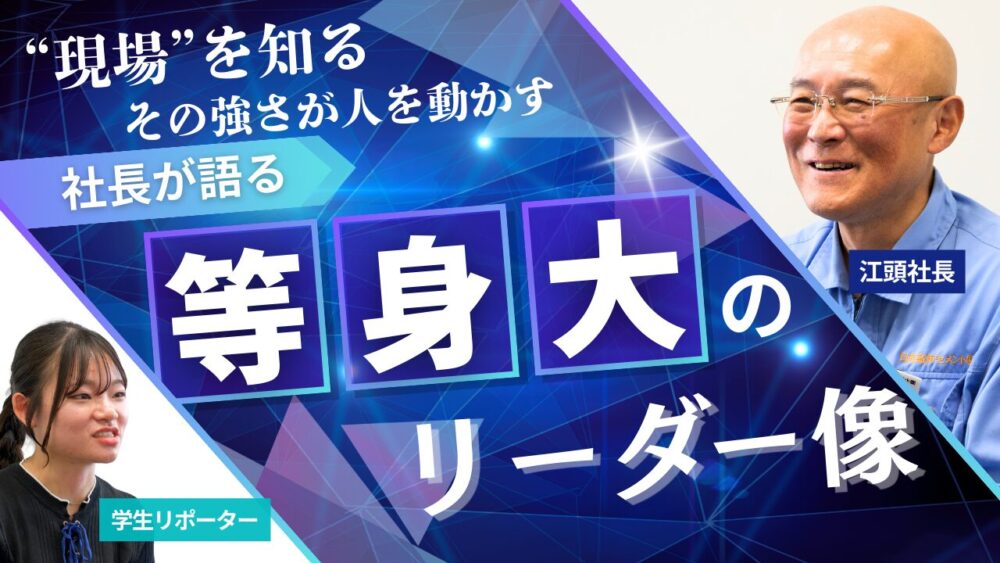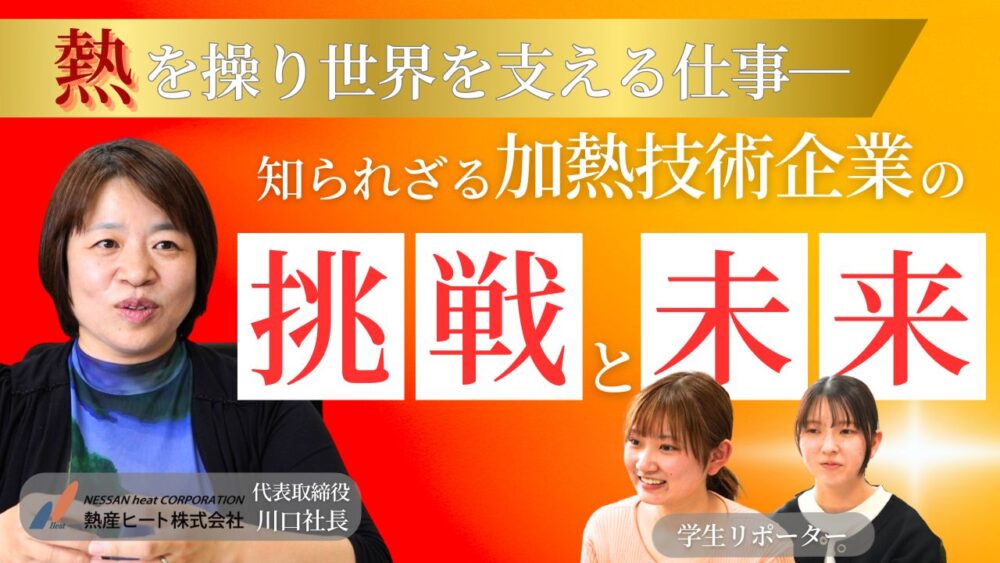SDGsや環境意識の高まりを背景に、「リサイクル」に興味を持つ学生が近年増えつつあります。しかし、実際の工場では どのような工程で、どんな工夫や苦労があるのかは、まだまだ知られていないのが現状です。そこで本記事では、北九州市で第三セクターとしてペットボトル再生事業を展開する西日本ペットボトルリサイクル株式会社と学生が対談。市の出資や製鉄技術の応用など、独自色の強いリサイクル工場の舞台裏を掘り下げます。自分たちの生活に欠かせないペットボトルが“どのように循環しているのか”を知れば、リサイクルの世界がぐっと身近に感じられるでしょう。
1. 第三セクターとペットボトルリサイクル:官民連携が生む“ものづくり”の新たな可能性
「今日はお忙しい中、ありがとうございます。私たちは北九州市の取り組みや、第三セクターとしての特色に興味があって取材をお願いしたのですが、まずは御社がどんな経緯でスタートしたのか教えていただけますか?」
「ようこそお越しくださいました。当社は1997年の操業開始以来、一貫して“ペットボトルリサイクル”を専業として きました。資本金は約1億円で、出資企業にはプラスチック容器の大手や繊維メーカー、輸送会社などが名を連ねています。そして北九州市が5%を出資しているので、いわゆる第三セクターの形態ですね。」
「北九州市が出資しているというのは、やはり地域のエコタウン構想の一環なのでしょうか? 私自身、北九州はかつての公害を克服して環境に力を入れている、という話を聞いたことがありますが……。」
「おっしゃる通りです。北九州市は公害を克服した後、今度は“エコタウン構想”を掲げて、環境関連企業の誘致や育成に力を注いできました。当社もその流れで設立されたわけです。リサイクル拠点を地域に置くことで雇用も生まれますし、ごみ処理だけでなく資源循環の一端を担うわけですから、市としても『先進的な環境都市をアピールしたい』という狙いがあります。」
「なるほど。一般的には“リサイクル”って地味な印象があるかもしれませんが、実際は行政との連携や企業との共同出資など、かなり大きなスケールで動いているんですね。」
「そうですね。第三セクターという形態にはメリットもあります。市が関わることで市民と一体となった回収ルートが得られる場合もあるし、一方で民間の出資企業からノウハウや資金を集めやすい面もあるんです。おかげさまで、創業から20年以上、ペットボトル専業リサイクル工場として実績を積み重ねてこられました。」

2. 製鉄技術とリサイクル:共通する“ものづくり”の発想
「ところで、御社には製鉄会社出身の方々もいらっしゃると聞きました。いわゆる鉄づくりとペットボトルリサイクルって、一見すると全然違うように思えますが、実際にはどんな共通点があるんでしょう?」
「皆さんもご存じのように、製鉄では鉄鉱石や石炭といった原料を炉で溶かし、不純物を除去しながら最終的に均質な鋼材を作りますよね。そこで必要になるのは“ばらつき管理”と“不純物の排除”という考え方です。実はペットボトルも同じで、回収されてくるボトルの状態はバラバラ。中には飲み残しや変形、キャップやラベルがついたままのものもあれば、他のプラスチックが混在していることもある。そうしたものを選別・洗浄して、最終的に高い純度の再生ペレットにする工程は、製鉄の『原料を管理しながら狙い通りの製品を仕上げる』ことと通じる部分が大きいんです。」
「なるほど。そう考えると“リサイクル”というより“ものづくり”の要素が強いんですね。確かに、家庭から出るボトルがそのまますんなり使えるわけじゃないですものね。製鉄技術と聞くと炉の温度管理や不純物除去のノウハウをイメージしますが、それがペットボトルにも応用できるとは驚きです。」
「最初は私たちも試行錯誤でしたけど、製鉄会社の技術者の視点が大いに役立ちましたね。例えば『海外製の設備を導入するにしても、現場の原料性状を詳しく把握しないと想定通りに動かない』といったノウハウとか。鉄を扱うのと同じ発想で、温度や分離手段をコントロールしてバラつきを最小限に抑えていく。それが当社の強みになっています。」
3. ペットボトル再生のプロセス:ベール→選別→破砕→洗浄→ペレット
「なるほど。リサイクルというより、一連の製造プロセスに近い印象ですね。実際はどういう流れになっているのか、もう少し詳しく聞かせていただけますか? 家庭で回収ボックスに入れたボトルは、その後どんな形で工場に届くんでしょうか?」
「回収されたペットボトルはまず、ギュッと圧縮されて固まり(ベール)になった状態で当社に運ばれてきます。大きいものだと百数十キロにもなるんですよ。それをほどいてバラバラにし、ベルトコンベヤーで選別工程に送ります。」
「圧縮されたボトルが塊になって来るんですね。そこから先の選別工程では、どんな方法で仕分けるのですか?」
「赤外線や近赤外線を使ったセンサーで、PETとその他の樹脂を見分けています。ラベルやキャップはポリプロピレン(PP)やポリエチレン(PE)が多いので、検知されるとエアブローで吹き飛ばすんです。ビニール袋などの異物が混ざっているケースもありますから、複数の工程でしっかり排除していきます。」
「近赤外線で判別してエアブローで弾き飛ばすなんて、すごい仕組みですね。想像以上にハイテクだと思います。そうやって不要なものを取り除いたら、次はどうなるんですか?」
「仕分けが終わったペットボトルは、破砕機で10mm程度の大きさに砕いて“フレーク”と呼ばれる形にします。細かくしすぎると洗浄時に粉が舞って扱いにくいし、大きすぎると汚れが落ちきらない。長い経験から、このサイズが一番効率がいいと分かっているんです。」
「確かにそのほうが洗いやすそうですよね。フレークにした後、最終的に再生ペレットになるまで、まだ洗浄が必要なんですか?」
「はい。フレーク状になってはじめて、本格的に汚れや異物を洗い落とせるんです。水や薬剤を使って徹底的に不純物を取り除きます。ここでしっかり汚れを落としておくことが、最終的に高品質な再生ペレットを作るうえでとても重要なんですよ。」
「なるほど。ペットボトルは一度使ったら捨てるものというイメージしかありませんでしたが、こうした工程を経ると新しい素材として生まれ変わるわけですね。単なるゴミじゃなくて、きちんと資源になるんだなと実感しました。」
「そうなんです。“リサイクル”という言葉のイメージだけでは伝わりにくいんですが、実は品質管理や製造工程がしっかりしてこそ成り立つ“ものづくり”なんですよ。」
4. 長年のノウハウ:海外設備の導入と現場改善の積み重ね
「でも、その工程を整えるには相当なご苦労があったのでは? 1997年当時は、今ほどペットボトルリサイクルがメジャーでなかったと思うんですが……。」
「そうですね。まだ国内に大規模なペットボトルリサイクル設備があまりなかった頃です。その後生産規模を拡大する中でフランスやドイツなど海外メーカーの機械を取り寄せては、工場のラインに合わせて改造を繰り返してきました想定している原料の状態が違ったり、モーターのパワーが合わなかったり、実際に動かしてみると問題がいろいろ出てくるんですよ。」
「そのあたり、まさに製鉄で培った『海外技術を進化させる』経験が活きたんでしょうね。」
「はい。製鉄も海外からライセンスを導入して、自前で改良しながら使うのが当たり前でしたから、そうしたノウハウが生かせました。例えば選別機のセンサー感度を日本で求められる高品質要求に対応すべくボトルに合わせて微調整したり、破砕機のブレードを特殊な形状に作り直したり。何度も改善を繰り返して、累計48万トン以上のペットボトルを再生してきたという実績があります。」
「48万トン……相当な量ですね。そうした経験の蓄積が信頼につながって、いまや業界トップランナーの一つというわけですね。」
「ありがたいことに、自治体や企業からの問い合わせも増えていますし、海外から見学に来られることもあります。結局、品質や仕様の異なる原料をいかに均質なペレットにするかが勝負どころですから、その点で“長年の現場データ”は何よりの財産ですね。」

5. 広がる用途と海外需要:ボトルからトレー・繊維まで
「できあがったペレットは、どんな製品に再生されるんでしょうか? たとえば“ボトルからボトル”に戻すのが理想的という話もあるじゃないですか。」
「ボトルへの再利用も可能です。実際、飲料メーカーさんに納品して“食品用飲料ボトル”にリサイクルされるケースがあります。ただ、食品用途は基準が厳しく、FDAに沿ったプロセス管理が必要だったりしますから、工程が多少違うんですよ。
一方で、卵パックや透明トレー、あるいは衣料用ポリエステルの原料になることも多いです。『ボトルからボトル』に注目が集まりがちですが、衣料用だって石油由来のポリエステルを削減する意味がありますからね。どの用途であれ、リサイクルによって資源を節約している点は変わりありません。」
「海外需要というのは、どのような形で起きているのでしょう? 国内のペットボトルが海外に輸出されてしまう、みたいな話も聞きますが……。」
「日本のペットボトルは比較的きれいに回収されるので、海外のリサイクル企業がまとめて買い付けることもあります。ただ、当社の場合は国内で処理する分がメインですね。海外へ出すにしても物流コストがかかりますし、当社の設備で再生したペレットを国内のトレーメーカーや繊維メーカーに納品する形が多いです。
ただ世界的に見ると、海外でも『リサイクル材を使う』という機運が強まり需要が一気に伸びつつあります。もちろん、原油価格が下がってバージンPETが安くなると、再生PETの値段面でのアドバンテージが薄れる局面もあるんですけどね。」
6. リサイクル現場でのキャリア:設備保全・品質管理・研究開発の魅力
「私は就職活動で『環境に関わりたい』と思っているのですが、正直リサイクル企業の中で具体的にどんな仕事があるかが分からなくて。新入社員の場合、まず何を担当するんでしょう?」
「当社の場合は、最初に現場の流れを肌で覚えてもらうため、ラインオペレーションや検品作業などを経験してもらいます。いきなり専門部署に配属するよりも、まず“どこでどんな不純物が混じるのか”“どうやってトラブルに対処するのか”を体験しておかないと、後々困ることが多いんです。」
「それは大事ですよね。ラインが止まったら大変そう……。」
「ええ、24時間稼働しているので、何か詰まったり機械が異常を起こしたりすると、一気に生産計画が狂ってしまいます。そういうトラブルシューティングを学んだ上で、『設備保全』『品質管理』『営業』『研究開発』などの部署に振り分けていきますね。」
「設備保全っていうのは、具体的にどんな仕事なのでしょう? ずっと機械のメンテナンスをするイメージですか?」
「そうですね。破砕機のブレード交換スケジュールを決めたり、センサー類の校正を定期的に行ったり、摩耗したパーツをどのタイミングで取り替えるか判断したり……。ライン停止を最小限に抑え、かつ安全性を保つための裏方作業ですが、とても重要です。」
「品質管理はペレットの検査をするイメージが湧きますが、具体的には何をチェックするのでしょう?」
「目視や重量測定だけでなく、異臭がないか、溶融時の粘度が規格内かどうか、混入率はどうか——など、多角的に調べます。食品用途ならさらに細かい検査が必要になりますし、顧客の要望に応じて試験をすることもあるんです。」
「研究開発もあるとのことでしたが、どんなテーマに取り組むのですか?」
「大きく分けて2つあって、1つは『既存ラインの効率化・高品質化』の研究。例えば、より短時間で洗浄を済ませるにはどうするか、選別精度を向上させる新しいセンサや装置はないか、といったことを調査研究します。もう1つは『新規プロセスやシステムの導入検討』ですね。海外メーカーが新型の光学選別機を開発したら、担当者が現地で視察し、実際に試運転を見てから導入を判断したりします。語学力があると海外とのやりとりを任されることも多いですよ。」
7. 学生へのメッセージ:現場を見てリサイクルの未来を描こう
「ありがとうございます。リサイクルと一口に言っても、こんなに多様な役割やキャリアがあるのは驚きでした。最後に、これから就職活動を進める私たち学生にメッセージをいただけますか?」
「リサイクルって“環境のために仕方なくやる”みたいなイメージを持たれがちですが、実際には『高度な技術やデータ管理を駆使してものづくりをする』仕事でもあるんです。ごみを処理するだけじゃなくて、『どうやって再生樹脂という新しい価値を生み出すか』を追及し続けるのが面白さですね。私たちは日常の中からまだ使える資源を見つけ出し、それを再び経済活動につなげているわけですから、やりがいは大きいと思います。」
「私も工場見学をして、選別機や破砕機が想像以上にハイテクで、しかもトラブル対応やライン管理がすごくシビアだと実感しました。まさに“ものづくり”ですよね。」
「そう言ってもらえると嬉しいですね。もし少しでも興味があるなら、どんどん見学に来てください。ペットボトルの山が分刻みでフレークになり、洗浄され、きれいなペレットとして生まれ変わる様子は、自分の目で見ると感動が大きいですよ。そこから『自分もこの現場で働きたい』と思う人が増えたら、私たちとしても本望です。」
「たしかに、文章だけではピンとこないかもしれないですもんね。今後ますますリサイクルの需要が高まると予想されますし、海外との競争や協力もありそうで、面白い分野だと感じました。」
「ありがとうございます。“国内だけでなく世界的にリサイクル材への注目が集まっている”というのは追い風です。でも同時に、原油価格の変動や世間の意識の高まりなど、先が読めない要素も多い。だからこそ、若い皆さんの柔軟な発想が新しい可能性を生むかもしれません。ぜひ一度、現場に足を運んで自分の目で確かめてみてください。」

ペットボトルリサイクルは一見、“ごみ処理”の延長に思われがちですが、その実態は製鉄のノウハウや海外技術の導入による高度な“ものづくり”といえるものでした。家庭から集まったボトルが選別・破砕・洗浄という厳密なプロセスを経て、再び資源として よみがえる様子は、まさに現代社会を支える要の姿。北九州市との連携や第三セクターならではの強みも活かされ、安定供給と技術革新を同時に実現しています。就職活動中の学生にとって、リサイクル業界は想像以上に幅広いキャリアの可能性を秘めるフィールド。興味を抱いたなら、ぜひ工場を訪れて、その迫力と奥深さを実感してみてはいかがでしょうか。