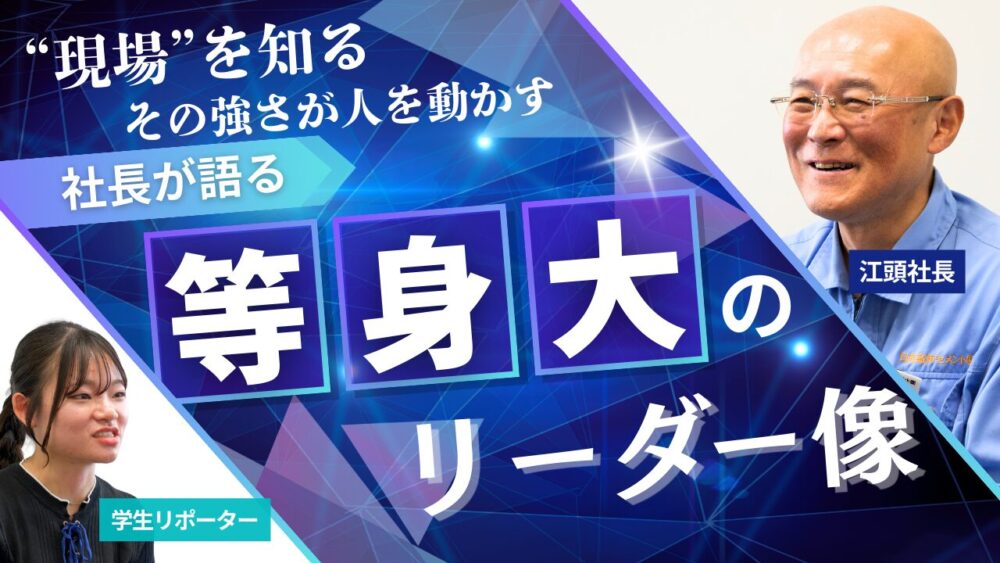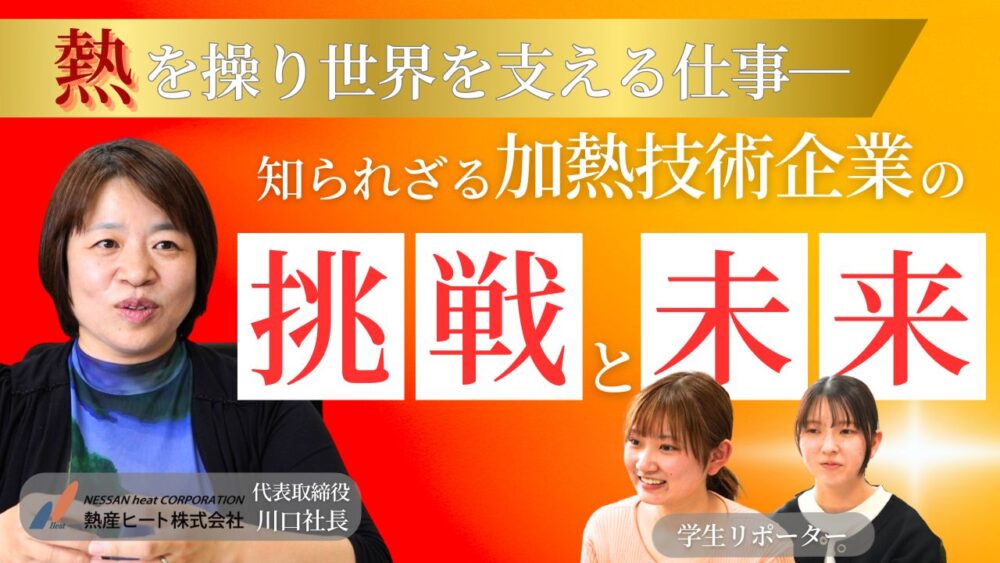北九州農業協同組合(JA北九)は、地域に根付いた活動を通じて農家や住民を支えている協同組合です。「JA」という名前はよく聞くけど、実際にどんな組織なのか詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか? リクルートWebマガジンVamosでは、総務部長の原さんにJAの仕組みや役割、そして地域とともに歩むための取り組みについてお話を伺いました!
JAの職員ってどんな立場?地域密着型の活動ってどんなことをしているの?そんな疑問に答える内容がたっぷり詰まっています!ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「JAって何?」基本からわかる仕組みと働き方
JAという名前はよく耳にしますし、CMなどで見ることも多いですが、実際にどういう組織なのか、あまり詳しくは分かりません。まずはJAについて教えていただけますか?
JAというのは“農業協同組合”の略でして、もともとは農家の方々が助け合うために作られた組織なんです。日本全国に広がる大きなネットワークを持っているんですが、各地域で独立して経営しているのが特徴ですね。例えば、JA北九の場合だと、福岡県北九州市と遠賀郡・中間市を対象に活動しています。
地域ごとに独立しているというのは興味深いですね。それから、JAの職員の方々の立場についても教えていただけますか?
JAの職員は、公務員でも会社員でもなく、いわゆる“団体職員”という立場なんです。これは、協同組合として組合員の方々の利益を最優先に考える仕組みを取っているからなんです。
JA北九では地域密着型の活動をされているとのことですが、具体的にはどのような事業を展開しているのでしょうか?
主に農業支援、そして金融、共済(保険)という3つの柱で事業を展開しています。例えば、農業の技術指導や農業資材を供給したり、地元の農産物の販売をサポートしたりして農家の方々を支えています。それに加えて、地域住民が利用できる直売所や購買店舗を運営して、地産地消を促進する取り組みも行っていますね。
幅広い活動をされているんですね。収益についても少し教えていただけますか?
収益が発生した場合は、基本的に組合員の方々に還元される仕組みです。これによって農業だけでなく、地域全体の発展にも貢献しています。
JAでは“組合員”という言葉をよく耳にしますが、具体的にはどのような方々を指しているのでしょうか?
組合員には2種類あって、農業を営む方を“正組合員”と呼び、それ以外の方を“准組合員”と位置づけています。正組合員の方には議決権があって、経営方針や事業計画の決定に参加していただくんです。一方で、准組合員の方々も、JAが提供するさまざまなサービスを利用することができます。
なるほど、組合員の方々がJAの活動にしっかり関わっていらっしゃるんですね。
JAの組織構造についても詳しく教えていただけますか?
JAのトップに立つのは“組合長”という役職で、これは農家の代表として正組合員の中から選ばれます。一般企業でいうと社長にあたる役職ですが、農業の経験が求められるため、正組合員以外の方がなることはできないんです。
組合長以外の役職についてはどうでしょうか?
組合長の他には常務や専務がいて、彼らが実際の運営を担っています。このポジションには、JAの職員や県レベルのJA団体等での経験が必要です。ちなみに、JAは株式会社ではなく農協法に基づいて運営されていますので、一般企業とは組織のルールや役職の条件がかなり異なります。
多彩な事業と新卒が描くキャリアパス
JA北九では具体的にどのような事業を展開しているのでしょうか?
まず、農業支援の分野では、肥料や農業資材の提供だけでなく、農産物の販売サポートも行っています。それに加えて、地域の農産物を販売する直売所も運営していて、地産地消の発信にも努めています。そして、金融事業としては、JAバンクを通じて地域住民の金融ニーズに応えていますし、共済事業では、JA共済を通じて各種の保障を提供しています。
かなり幅広い事業を展開されているんですね。事業所の規模感も気になります。
事業所数は50を超えています。金融店舗や直売所、購買店舗などが地域全体をカバーしています。
JAの事業には、保険や金融など多岐にわたる分野があると伺っていますが、これらはどのように発展してきたのでしょうか?
JAの始まりは、農業を営む方々が地位を向上させようと協力し合ったことからスタートしています。そして、お金に余裕がある方と困っている方がお互いに融通し合う仕組みが生まれ、これが金融事業の起点となったんです。
なるほど。そこから金融だけではなく、共済や他の事業も発展してきたんですね
そうなんです。共済事業では、農業や生活で予期せぬトラブルが起きた際に、自分たちで助け合う仕組みを作りたいという思いから始まりました。一般の保険よりも手頃で、組合員同士が支え合う形で広がったんです。それから、葬祭事業やその他の事業も加わっていきました。組合員同士が協力し合って負担を軽減する仕組みが生まれたんですよ。
JAを就職先として考える場合、どのような業界として捉えるべきでしょうか?
一般的には、JAバンクやJA共済のイメージが強いため、金融業界として認識されることが多いですね。でも実際には、農業支援や地域密着型の事業展開も大きな柱になっています。そのため、金融だけでなく、幅広い分野で活躍できる場があるんですよ。
新卒で入社された方は、具体的にはどのような仕事からスタートされるのでしょうか?
一番多いのは、金融店舗への配属ですね。JA北九では金融店舗の職員数が多いので、支店のような金融店舗が最初の配属先になることが多いです。ただ、それだけではなくて、総務や広報活動を担当する部署に配属されることもあります。例えば、Instagramを使った情報発信や広報誌の作成などを通じて、地域とのつながりを深める業務もありますよ。
なるほど、幅広い業務があるんですね。他にはどんな配属先がありますか?
営農経済部門に配属される場合もあります。この部門では、農業資材の提供や販売支援を通じて、地域農家をサポートする重要な役割を担っています。新入職員は、それぞれの適性を見ながら満遍なく配属されるよう配慮していますが、最初のステップとしては金融店舗が多いのが実情ですね。

JAが向き合う地域課題と未来への挑戦
地域密着型の活動を進めてこられた中で、現在の課題はどのようなものがあるのでしょうか?
現在のJAは、どうしても金融や共済事業に重心が置かれすぎているという指摘を受けることがあります。農業支援や地域密着型の活動も重要ですが、収益面では金融と共済が大きな役割を果たしているのが現状です。ただ、それらの収益を地域社会や農家の支援に活用して、仕組みを維持していくことが大切なんです。例えば、災害時の人的支援や地域資産の維持・運営など、多岐にわたる活動を行っています。
農業従事者の高齢化や後継者不足が問題になっていると聞きますが、JAとしてどのように対応されていますか?
そうですね、後継者不足は確かに大きな課題の一つです。農業は体力的にも厳しい仕事ですし、若い方には『儲からない』というイメージがあるのも事実です。これを変えるために、JAでは販路拡大やブランド化に力を入れています。例えば、若松地区の “若松潮風Ⓡキャベツ”や大玉スイカの“若松潮風Ⓡプレミアム” など、地域特有の農産物をブランド化して、付加価値を高める取り組みを進めています。

ブランド化というのは、具体的にどのように進められているのでしょうか?
例えば、若松地区では潮風が農作物に甘みを与えるという特性を活かして、“若松潮風Ⓡキャベツ” というブランドが生まれました。このように、地域特有の条件を最大限に活用して、新しい農産物を発掘しているんです。そして、栽培方法の改良やブランド化をサポートしています。さらに、JA北九では“農業振興資金”という独自の助成措置を設けて、ブランド化に向けた資金支援も行っています。これにより、農家の方々が新しい取り組みに挑戦しやすい環境を整えているんですよ。
JAさんでは、子ども向けのコンテンツが充実していると伺いましたが、その背景にはどのような考えがあるのでしょうか?
やっぱり農業を次の世代に引き継いでいくためには、若い世代に興味を持ってもらうことが大切なんです。そこで、例えばアンパンマンをキャラクターに起用した交通安全教室を開催したり、バケツでお米を育てるキットを提供したりと、子どもたちが楽しみながら農業に触れられる活動を行っています。
すごく面白そうですね!他にも取り組まれていることはありますか?
例えば、食品衛生法の影響で直売所での漬物販売が難しくなっているんですが、そういった課題にも取り組んでいます。伝統的な食文化を次の世代に伝えるためにいろんな工夫をしています。こうした活動を通じて、農家の知識や技術をしっかり次世代に継承する努力を続けていますよ。
JAの職員の皆さんは、農家の方々とどのように関わっているのでしょうか?
職員はそれぞれの部門で役割を持って農家を訪問しています。例えば、金融部門の職員は融資や貯金に関するサポートをしますし、農業部門の職員は栽培方法や販路拡大についてのアドバイスを行います。ただ、一人ですべての業務を担うのは難しいので、各部門が連携して農家を支えています。この連携のおかげで、地域に密着したきめ細かいサービスが提供できるんです。

JAの連携と未来へのテクノロジー活用
各部門の連携について詳しく教えていただけますか?
各部門の部長が定期的に会議を開いて、連携を深めるようにしています。それぞれの専門分野に応じて役割を明確に分担することで、効率よく農家の支援を行っていますよ。
海外向けの取り組みもされていると聞きましたが、その点についてはいかがですか?
海外への販路拡大にも取り組んでいますが、日本の農産物はコスト面で厳しい部分があります。なので、富裕層向けに高品質な農産物を輸出するなど、ターゲットを絞ったアプローチを取っています。
農業従事者の減少に対応するために、スマート農業のような技術革新も活用されていますか?
そうですね。全国的にスマート農業の取り組みが進んでいます。例えば、ドローンを使った農作業や、完全機械化されたハウス栽培などがあります。これによって、効率的な生産と人手不足の解消を目指しています。
農学部や理系の学生さんもJAで活躍できる場はありますか?
もちろんです!農学部や理系の学生にもぜひ多く来てほしいと思っています。文系の視点だけでなく、理系ならではの考え方やスキルが加わることで、組織に新しい風が吹き込まれると考えています。

働きやすさが魅力!JA北九の職場環境とサポート制度
職場環境としても魅力的な点はなんですか?
今の組合長が特に重視しているのが、職場内での連携や協力なんです。全員が協力し合って働ける環境づくりを進めていますよ。
離職した職員の方が再び戻られるケースもあるのでしょうか?
はい、JA北九ではカムバック採用制度を取り入れて、一度離職された方でも戻ってきやすい環境を整えています。結婚や出産、介護などで退職された方が、状況が整ったときに再び働ける仕組みです。この制度によって、即戦力となる人材を確保できるだけでなく、外部での経験を持ち帰っていただけることで、組織全体の視野も広がるんです。
育休や産休制度についても充実しているのでしょうか?
もちろんです!以前は結婚を機に退職される方が多かったのですが、今では育休や産休制度が充実していて、ほとんどの方が復帰を前提に利用されています。これによって、職員が安心して働ける環境が整っていますよ。

一般企業との違いとJAならではのやりがい
JAに入組して感じた一般企業とのギャップは、どのようなところにありましたか?
私は一度民間企業で働いた後にJAに入りましたが、一番感じたのは、上下関係が非常にフラットなところですね。これには安心感がありますし、職場の雰囲気も非常に良いと思いました。一方で、新卒で入社された方々は、目標管理や人間関係の難しさに戸惑うこともあるようです。例えば、共済や金融部門では1年間の目標が設定されていて、それを達成するために努力が求められます。
その中で特に重要な部分はどんな点でしょうか?
営業では、最終的に“人を売る”という部分が大切になります。お客様との信頼関係を築くことで、商品やサービスを提供できるんです。この点は、JAが一般企業と共通する部分でもありますね。
JAは一般企業と比べて、経営方針にどのような違いがありますか?
一般企業は収益性の低い事業を切り捨てて、収益性の高い事業に集中する“選択と集中”が可能です。でも、JAでは利用者、組合員の方々の利便性を考えなければいけません。そのため、単純に収益が低いからといって事業をやめるわけにはいかないんです。
それは大きな違いですね。どうやってそのバランスを取っているんですか?
JAは株主ではなく、組合員の利益を守ることを目的としている組織です。ですから、最低限赤字を回避しつつ、地域の利便性を維持するために事業を続ける努力をしています。この点が一般企業との大きな違いですね。
准組合員の方々との関わりの中で、やりがいを感じる瞬間はどのような場面ですか?
金融店舗や事業所で直接お客様と接するときが、一番やりがいを感じます。私たちの提案が役立って、『ありがとう』と言っていただけると、本当に嬉しいですね。もちろん、時にはクレームをいただくこともありますが、信頼関係を築ける喜びは大きいです。
農家の方々とは、どのような関係性で接していらっしゃるのでしょうか?
特に農家の方々とは、家族のような距離感で接することが多いです。じいちゃん、ばあちゃんのような親しみを持って接することもあります。この温かい関係性は、他の仕事では味わえない魅力だと思いますね。

学生と未来をつなぐJAのPR戦略と就活サポート
PR活動についての課題はどのようなものがありますか?
農協は『農家だけが利用するもの』というイメージが強く、それが一般の方々に誤解されています。このため准組合員の方々を対象にしたイベントを開催して、事業内容を紹介する取り組みを行っています。イベントでは、『こんなに良い取り組みをもっとPRすべきだ』というご意見をいただくことが多いですね。
SNSの活用についてはいかがですか?
今はInstagramを活用して、内定者の懇親会や1年目から3年目の職員の活動を紹介しています。ただフォロワー数がまだ少なくて、十分に情報が届いていないのが現状です。人事部門にもSNSを活用したPR活動の重要性を伝えており、学生や若い世代にJAの魅力を知ってもらうためにリアルな声を発信し続ける予定です。
今日は直接お話を聞けて、JAについて詳しく知ることができました!とても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました!
こちらこそ、熱心に質問していただいて嬉しかったです。ぜひまた何か機会があればお話しましょう。これからの活動も応援していますよ!
ありがとうございます!これからの就活活動に活かしていきたいと思います!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
今回のインタビューを通して、JA北九が農業支援を超えて、地域の生活や人々に深く寄り添っていることを実感しました。組合員の方々との信頼関係を築きながら、地域全体の発展に力を注ぐその姿勢に、多くの刺激を受けたのではないでしょうか。
「JA」という名前は聞いたことがあっても、実際にどんな活動をしているのか知らない人も多かったはず。でも、今回の話を聞いて、JA北九がどれだけ地域と密接に関わり、たくさんの役割を果たしているかがよくわかったと思います。
これからの自分たちが、地域や人とのつながりをどう作っていくのか、どんな信頼関係を築いていけるのかを考えるきっかけになったはずです。今日得た学びを自分の未来にどう活かしていくか、ぜひ考えてみてくださいね!