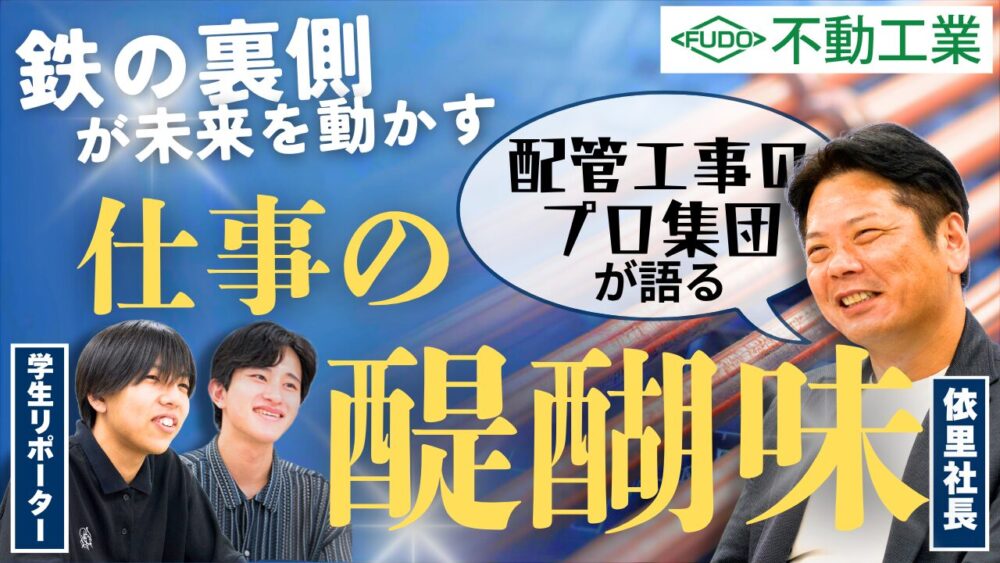任天堂から学ぶ「遊びと人生」
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
任天堂と“日常”の交わり
さて、今回の記事には、任天堂が「ニンテンドースイッチ」の後継機を2025年に発売するという話が書かれています。もっと正確にいうと、公式発表そのものはまだざっくりしたものみたいで、詳しいところはまだベールのなか。僕らはその“わずかな情報”を頼りに、ああでもない、こうでもないと想像をふくらませて楽しむ――それもまた、ゲームの一部みたいなものかもしれません。
ゲーム機のスペックや価格の話は、聞きかじり程度でもすぐに盛り上がりますよね。任天堂はいつだって、“身近にある日常”を変えてきてくれた存在。
任天堂という会社は、昔からどことなく“家族”のようなにおいがすると思うんです。最先端の技術を搭載していながら、親しみやすい、おばあちゃんやおじいちゃんでも触って楽しめそうな雰囲気。こういう“親しみやすさ”が、他のゲーム機とはちがう魅力のひとつになっているんじゃないでしょうか。
実際、今回の日経の記事にも書いてあるように、「身の回りのことから面白さを考える」「ユニークさにこだわる」というのが任天堂の首脳陣の発言にありました。ハードの性能がどうだとか、グラフィックがどうだとか、そういう“技術の見せどころ”ももちろん大切なんでしょうけど、任天堂はいつだって「それがお茶の間のど真ん中に転がっている姿」を想像するように思うんです。
つまり、ゲーム機がリビングにあって、家族や友だちがそれを囲みながらワイワイしている。そのときに、いかに“みんなの会話”が盛り上がるか――そっちを優先して考えているからこそ、不思議と「なんだこれ?」っていうアイデアが出てくる。そんなふうに思えます。
マウス機能が与えてくれるヒント
記事によると、後継機ではジョイコン(コントローラー)に“光学式センサー”が入るかもしれない、という見方があるそうです。これがもし搭載されるとしたら、ジョイコンを机の上でマウスみたいに動かして操作できるんだとか。
最初に聞いたときは、「へえ、そんなことしたらどんなゲームができるんだろう?」と単純にワクワクしました。パソコンで一般的なマウス操作を、そのまま任天堂のハードに落とし込むわけですよね。日常生活で当たり前に使っているマウスを、あえてゲーム機側に持ってくる――これって、今までよりも幅広いゲーム体験をできるようにする意図があるのかもしれない。
そこに任天堂のアイデアに期待しちゃいます。たとえば、これまでコントローラーとマウスは別モノでした。でも、任天堂ならじゃあ「マウス機能を持ったコントローラー」でどんな遊びを考えるのか? ただFPSゲームを快適にするだけじゃなく、まったく新しい操作感のゲームが出てきたらおもしろいですよね。

大きな画面と人生の広がり
スイッチ2の画面が大きくなるという点も記事には触れられています。スマートフォンにしても、テレビにしても、画面が大きくなるとそれだけ視野も広がるし、迫力も増す。
でも、これはただ映像が美しくなるという話にとどまりません。画面が大きい=そのぶん、遊び方も拡張する可能性が高まります。大勢で集まったときに、みんなが覗き込みやすくなったり、細かいニュアンスを共有しやすくなったり。「いや、そこはもっと右だろ」とか「ここに宝物があるよ!」なんていう、リアルタイムでのみんなの反応が増幅されるわけです。
今回の画面を大きくするという点もゲームの迫力だけでなく、みんなで盛り上がるためといった別視点での意図もありそうなのが任天堂だと勝手に思っています。
でも、この発想はぼくらも大事にしたいですね。自分が見ている景色をちょっと大きくするだけで、周囲から見える反応も変わる。たとえば、大学生がアルバイト先で店長の仕事を手伝ってみたら、「あれ、意外と接客だけじゃなくて経営に興味あるかも」と気づいたりする。自分が目の前だけを見ていたところから一歩踏み出すと、こんなにも世界は広かったんだ、って。
任天堂が画面を大きくするのも、そういった“ちょっとの拡張”がもたらす大きな変化を期待しているんじゃないかと思います。
どう生かすかは、いつも自分次第
ハードや道具が進化することは、あくまで“入り口”なんですよね。たとえば新しい調理道具が出たとしても、それをどうやって料理に使うかは、人間のアイデアと腕にかかっている。業務でハイスペックなパソコンを導入しても、それを使いこなして成果を上げる人もいれば、宝の持ち腐れになる人もいる。
任天堂のゲーム機も同じです。技術的に優れているからといって、必ずしも面白いゲームが生まれるわけじゃない。それを「どんな遊びに転換するか」という“はたらき”が、クリエイターだったりユーザーだったりの意志で決まっていく。
つまり、技術や道具はひとつの“きっかけ”なんです。大切なのは、「それを自分がどう使いこなすか」。就活や仕事でもまったく同じで、いい会社やいい学歴を手に入れたとしても、結局はそれを活かすも殺すも自分次第なんですよね。むしろ、「自分がいま持っているものをどうやって輝かせるか」が問われると思います。
“小さな日常”を笑顔にする
任天堂のコンセプトには、「すごい技術で人を圧倒する」というより、「なんだか不思議だけど、みんなが笑顔になる」という不思議な味わいがあります。新型ゲーム機がどう進化しようと、その根っこには「日常のなかの、ちょっとした楽しさ」を大事にする気持ちが息づいているように思うんです。
これって、僕らの暮らしでも応用できるんじゃないでしょうか。たとえば、どんなに忙しくても朝のコーヒーをいれる時間を楽しんでみるとか、誰かとちょっとした笑い話を共有するとか――そういう“些細な遊び心”を持ち込むだけで、なんとなくその日の色合いが変わってくる。大スクリーンで超絶美麗な映像を楽しむのもいいけれど、小さなスクリーンで“心がほっこりする瞬間”を作り出すのも、また大きな喜びです。

Vamos公式LINEはこちら