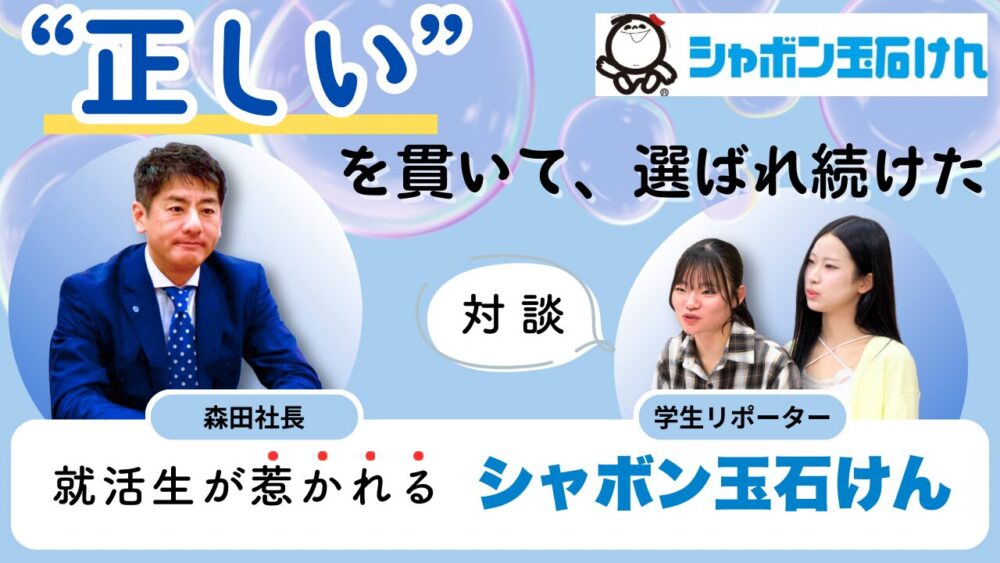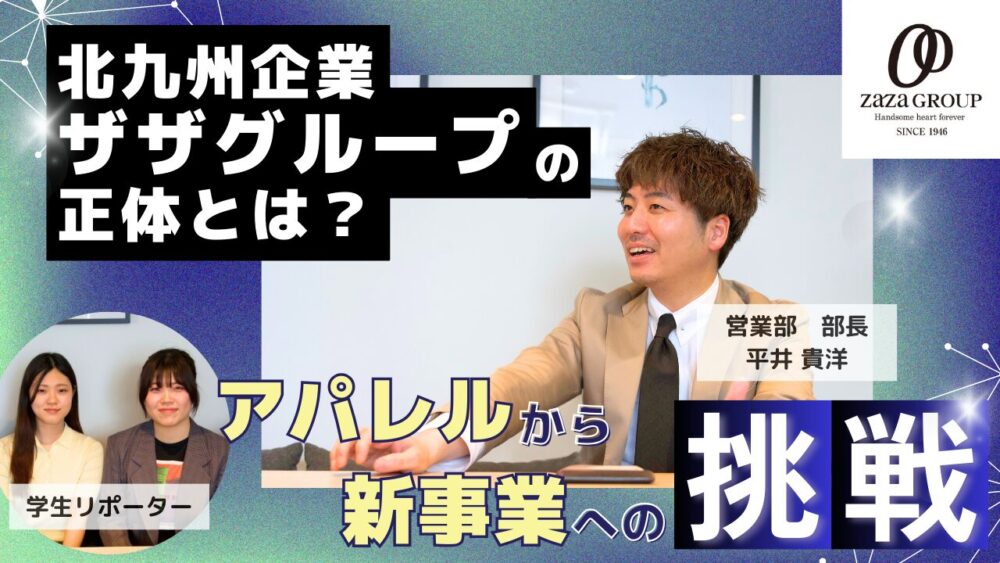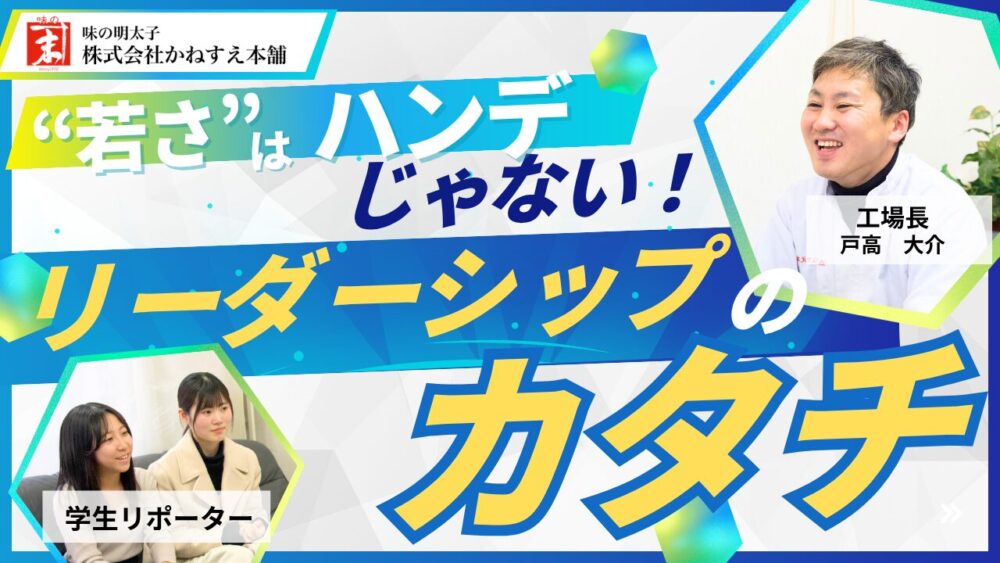「生成AI」が創る新しい起業のかたち
AIスタートアップ「オリオラボ」の挑戦
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
カリフォルニア州サウスサンフランシスコ。ここにある小さなAIスタートアップ企業「オリオラボ」は、不思議な光景が広がる場所です。ラボには“本物のネズミ”がいて、従来のパソコン周辺機器のマウスとはまるで正反対。なぜネズミ? それは肥満治療薬の開発実験に使うため。彼らはAIを活用し、膨大な化合物をシミュレーションで組み合わせ、より効果の高い薬をつくろうとしています。しかも正社員はわずか7人。AIと知恵をフル活用することで、大資本が支配してきた製薬ビジネスに挑んでいるのです。
「生成AI」って、いったい何?
最近よく耳にする「生成AI」という言葉。これは人間が書くコードや文章をAIが学習し、新たな文章やプログラムを“自動生成”する技術の総称です。言語モデルなどのテクノロジーを駆使して、かゆいところに手が届くような新しい情報やアイデアを提案してくれるのが特徴。オリオラボはこの生成AIを使ってプログラムを半分以上“AI任せ”にし、加えて特許管理や規制対応といった業務にも活用しています。まさに、少数精鋭の新時代を体現するやり方だといえるでしょう。
クラウド活用が変えた「数は力」の常識
かつてITスタートアップにとって「サーバーの処理能力をいかに確保するか」は死活問題でした。限られた資金で大量の機材をそろえなくてはならず、場所も人手もかかる。それがクラウドコンピューティングの登場で一変。必要なサーバーを必要なときだけ使える時代になり、起業のハードルはぐっと下がりました。
そしてさらに、生成AIによってソースコードを書く労力が減り、少人数でも十分なサービス開発や運営が可能に。Yコンビネーターの投資先企業のように、売上が急激に伸びるスタートアップも出てきています。どれだけ人を集められるかという「数は力」のルールが、ここにきて揺らぎ始めたわけです。
具体的に言うと「ソースコード」って何?
「ソースコード」とは、プログラムの“設計図”や“作り方”を記述したもの。ウェブサービスの動き方やアプリの機能などは、このソースコードによって決まります。従来は人間のエンジニアがコツコツと書くのが当たり前でした。しかし生成AIが進化することで、エンジニアが書きたいコードをAIが予測・補完し、人間より早く・正確に仕上げることができるようになっています。要するに、“職人的なコーディングスキル”だけに頼らなくても、サービス開発をスピーディーに進められる時代が訪れているのです。

日本の課題と、世界とのギャップ
一方で、日本で生成AIを業務に使っている企業はまだ半数にも届かないという調査結果があります。個人での利用率はさらに低く、アメリカや中国と比べ大きな差がついているのです。周囲を見渡して「AIが仕事を奪う」という不安の声があるのも事実。しかしある教授はこう言います――「AIが人間を代替するのではなく、AIを使いこなす“別の人間”が人間を代替する」。つまり、AIそのものを拒むのではなく、どれだけ上手に取り入れられるかが未来を決めるカギ、という見方です。
変化の先にある「自由度」
サーバーを自分で買わなくてもいいし、コードを書くのもAIが助けてくれる。そんな時代になれば、場所の制約も大企業の後ろ盾も、それほど重要ではなくなります。日本の地方都市でも、あるいは海外の小さな村でも、新しいアイデアさえあれば世界規模のサービスを立ち上げられる。これは起業家にとって格段に「自由度」が高まったことを意味します。「大企業だから勝てる」「お金を持っているから優位」といった昔ながらの常識が、ゆっくりと音を立てて崩れているのです。
少数精鋭と多様性
AIを使うことで少ない人数で多くのことを実現できる。誰もがどこからでもアイデア勝負でチャレンジできる。これは同時に、多様な人材の活躍が期待できる時代が来た、ということでもあります。女性や高齢者、あるいは世界中の専門家が、それぞれの得意分野に集中しやすくなる。今まで大組織に吸収されがちだった才能が、より自由に羽ばたけるチャンスなのかもしれません。
「AIを使える人間」が未来を動かす
結局のところ、AIは魔法の杖ではありません。扱う人間の使い方次第で、その本領は変わります。日本ではまだ普及が遅れているようですが、それは「どこかで他人事」になっているからかもしれません。AIが奪う仕事もあるでしょう。しかし、その一方で新しい仕事が生まれ、人間とAIが協力する現場も増えていくはずです。
「AIに負けるんじゃなくて、AIを使わない人間が使う人間に負ける」。そんな言葉が、これから先どれほど真実味を帯びてくるか。ネズミが駆け回るラボでAIが猛スピードでソースコードを書く――そんな風景が当たり前になる未来は、案外すぐそこまで来ているのかもしれません。
Vamos学生メンバー募集
Vamosのメンバーになって、いろいろな企業にインタビューしながら自分なりの業界研究を深めてみませんか? 多くの学生が参加しており、リアルな体験談もたくさんシェアされています。興味がある方は、下記リンクで参加者の声をチェックしてみてくださいね。参加希望の場合は、以下のVamos公式LINEへ「説明会参加希望」とメッセージするだけでOKです!