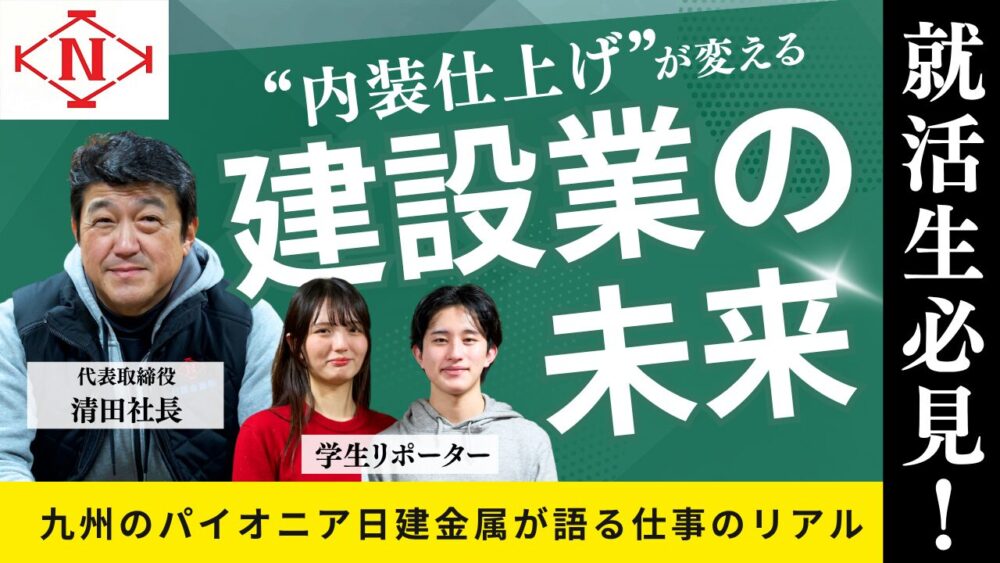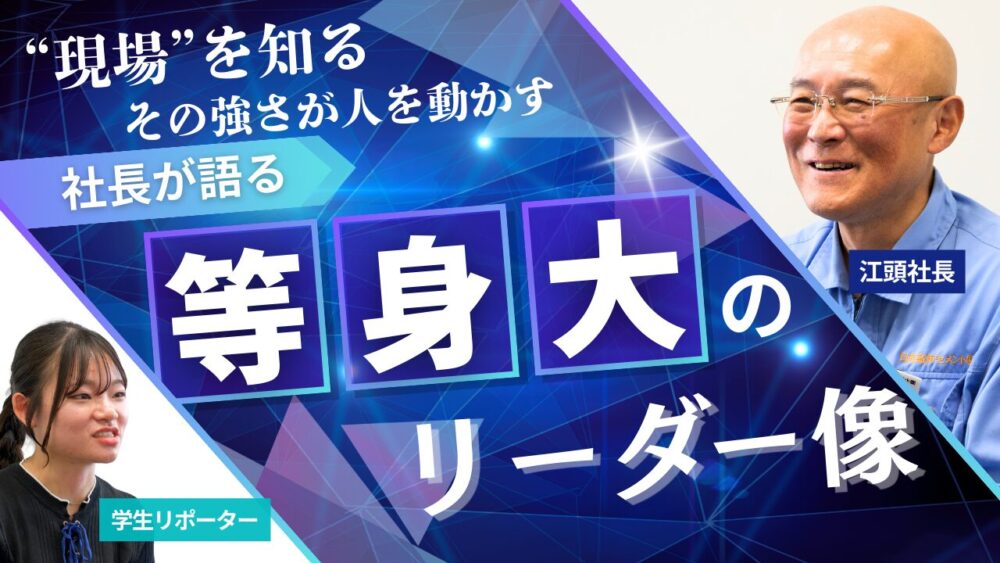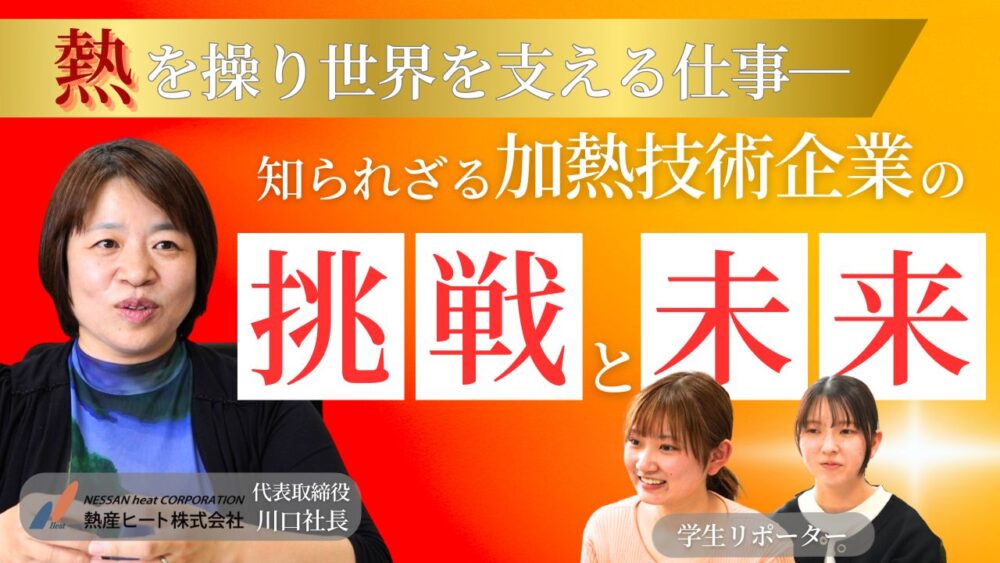今回は、長い歴史を持ち、九州でいち早く軽量鉄骨による内装仕上げ工事を導入してきた日建金属株式会社に注目しました。
橋や道路を作る建設業界の中でも、病院や学校、商業施設などの空間を形作る“内装仕上げ”の重要性をご存知でしょうか。壁や天井を組み、耐火や防音の性能を満たすために絶えず法改正や材料開発に対応しながら、大規模なプロジェクトを支える仕事。それを率いる清田社長の歩みや、現場管理の醍醐味、職人との連携が生むやりがいなど、貴重なお話をたっぷりお伺いしました。
建築に興味がある方はもちろん、「建設業って大変そう…」と感じる方にこそ読んでいただきたい内容です。ぜひ最後までお楽しみください。掲載したインタビューでは、清田社長がものづくりへの熱い想いや業界に潜むチャンスを存分に語ってくださいました。就活生や若い世代の皆にとっても、きっと新たな発見があるはず。

「内装仕上げ工事」って何?:枠組みから空間づくりまで
本日はよろしくお願いします! まずは日建金属のお仕事について伺いたいのですが、そもそも御社は“建設業”に分類されるのですよね?
はい、よろしくお願いします。当社は大まかに言うと建設業なんですが、その中でも「内装仕上げ工事業」にあたる会社です。建設業全体を見渡すと、橋を作る人や道路を作る人、家を建てる大工さん、配管を取り付ける設備屋さんなど、29種類もの専門工事があります。その中のひとつが、うちが担う“天井や壁などを作る内装仕上げ工事”なんです。
内装仕上げ工事っていろいろな工程がありそうですね。具体的にどんな作業をされるのでしょうか?
たとえば、病院をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。病院って、広い廊下の両側に4人部屋や6人部屋など、いろいろな病室が並んでいますよね。あれって最初は広い空間に仕切りが一切ない状態なんです。その状態から「ここに壁を入れて部屋を作る」といった作業を担当するのが、私たち内装仕上げ業者です。扉を付ける人、床材を貼る人、……それぞれ専門業者が違うんですよ。私たちは主に、“天井を組む”とか“壁の仕切りを作る”という部分を請け負っています。
建物の枠組みができてから、いよいよ中の空間を“使える形”にしていくわけですね。学校や公共施設でも、やっぱり同じような流れになるんですか?
そうですね。壁の厚さや耐火性能、防音性能など、建物の用途に合わせて仕様が変わります。たとえば学校や病院だと「天井が地震で落ちてこないようにしよう」といった法律があって、それに沿って施工するんです。東日本大震災のあとに耐震基準が強化され、面積や高さの条件を満たす施設では耐震天井が必須になりました。
確かに大きな地震で天井が落ちてしまうのは大惨事ですよね。そういう法改正があるたびに、工事の内容もどんどんアップデートされていく……。
時代とともに進化する施工:法改正と材料のアップデート
そうなんです。ですから図面(設計図)も、細かい法律や施設ごとの要件によって変わります。ここに扉を付けます、この壁は音を通さないように厚くします、向こうから火が来ても燃え広がらないように二重構造にします……などなど。図面に描かれた寸法や記号をもとに、いろんな専門業者が工程をすり合わせしながら工事を進めて行きます。
“内装仕上げ”って言葉のイメージ以上に、ものすごい専門性が求められますね。正直、扉やガラスまで別の業者とは知りませんでした。
先程もお話ししました様に建設の現場は細かく専門分野が分かれているんですよ。弊社は天井や壁を作るうえで、他の業者と密に連携しないといけません。「壁を閉じる前に電線を通してもらわないと困る!」といった調整が必要なんです。
すべて別個に動いていたら、たしかに工事の順番や工程管理が大変そうですね……。
その大変さこそ醍醐味でもあるんですけどね。図面上では問題なくても、現場で予想外のことが起きたり、仕様が一部変わったり。そのため他業者とのすり合わせが欠かせません。手間もかかりますが、完成したときの達成感はかなり大きいですよ。
リフォームにも対応しているんですか?
もちろんです。既存の建物を「ここで壁を壊して空間を広げよう」とか「もう少し部屋数を増やしたい」とか、そういう改修も請け負います。最近は軽量鉄骨で壁を作るのが主流なので、一度解体しても割と自由に部屋のレイアウトを変えられるんですよ。
そうなんですね! じゃあ、自宅を改造してカフェにするとか、オフィスの間取りをガラッと変えるときなんかにも、内装仕上げの仕事が必須なんですね。
まさにそうです。大工さんと同じようで実は違う。建物を支える外枠だけじゃなく、内部の使い勝手を左右する壁を作る――それが私たちのメイン領域です。
さっそくですが、日建金属株式会社は創業60年を迎えられるそうですね。もともとは大工さんが壁や天井を作っていた時代から少しずつ変わってきたと伺いましたが、そのあたりの歴史を教えていただけますか?
そうなんです。創業当時は壁や天井の工事は大工さんが木造で行ってました。でも法改正や材料の進化などが重なって、天井や壁を“軽量鉄骨”で組み立てる「内装仕上げ工事」が主流になっていったんですよね。実は九州ではうちの会社がその技術を最初に取り入れた一社なんです。
法律の変更で、使える材料や施工方法も変わるんですね。あの“姉歯事件”をはじめ、耐震基準とかいろいろニュースで見ました。
そうそう。姉歯事件では、設計段階で強度をごまかした建物が発覚して大騒ぎになりました。あれを機に基準も厳しくなりましたし、東日本大震災で天井が落ちて大怪我をした事例が出たときも、耐震の規定が強化されました。そうした法改正に合わせて材料も工法もアップデートしながら、お客に安全な建物を提供していくわけです。
法律が変わるたびにメーカーも対応が大変そうですね。今まで作っていた材料が使えなくなったりしたら…。
そうなんです。メーカーは一から作り直しになって苦労されることもあります。でも私たちは基本的に、変わった法律に従って「じゃあ次はこの材料を使います」「この施工方法を守ります」って対応するだけ。そうやって当たり前のことを当たり前に続けていけば、お客様に迷惑をかけることはありません。
なるほど。お客様への施工自体も、やっぱり個人宅というよりは大規模な法人案件がメインなんですか?
99%は法人ですね。ゼネコンや工務店から内装仕上げを依頼される形がほとんどです。スーパーゼネコンはもちろん、この近辺の中堅ゼネコンや工務店からもご注文をいただいています。
そうなんですね。そういえば、ホームページで大きなドームや結婚式場のような建物を拝見しましたが、どんな工事を担当されたんですか?
結婚式場で大きくカーブした天井がありますよね。あれも現場で1から組み立てるというより、工場で加工してパーツ化したものを持ち込んであの独特の曲面を造り上げて行きました。
それ、めちゃくちゃ難しそう……。曲面の寸法をどうやって測るんですか?
図面がすごく細かいんです。職人が見たら一目で「ここをこう曲げるんだな」って分かる仕組みになっています。足場を組んで高い場所で作業するときも、ちゃんと寸法が合うようパーツを工場で仕上げて持っていくんですよ。外から見えないだけで、裏にはエアコンの配管や電気配線が通っていたりするので、それもきれいに隠せるように計算します。
職人の技術力が大事ですね。そもそも清田社長は、もともとこういう施工のご経験があったんですか?
いえ、私自身はもともと自動車メーカーの営業でした。整備士学校の出身だったのですが、営業部に配属されてしまって(笑)。そこから妻の実家がこの会社をやっていて、何かと縁があって転職を決意したんです。
建築畑の人ではなかったんですね。最初は戸惑いませんでしたか?
そりゃ最初はもう何も分からなかったですよ。職人から「本当に何も知らないのか?」と馬鹿にされたりして。でもその分、必死に勉強して、だんだん現場の工程も頭に入っていった感じです。

大規模工事の醍醐味:段取りが7~8割を占める現場管理大規模工事
それにしても、99%の顧客がゼネコンとのこと。それだけ工事の規模が大きいと、職人もたくさん動員されるんでしょうね。全体を管理するのって難しそう……。
難しいですよ。工事するのは職人ですが、それ以上に大変なのは“人を動かす”ことです。たとえば1つの現場で70~80人が内装を担当する場合もあるんですが、その人たちが効率良く作業できるよう、工程管理をしなきゃいけない。段取りが7~8割、実際の施工が2~3割って感じですね。
“段取りが7~8割”っていうのは具体的にどういうことですか?
たとえば電動工具を使うなら、ちゃんと電源を各所に確保しておくとか、ゴミを捨てに行く動線をなるべく短くするとか、そういう細かい準備です。職人が余計な移動や手間をかけずに作業できるようにしてあげるのがポイント。結局それが職人との信頼関係に繋がるんですよ。
大きい声で「やれ!」と命じるより、環境を整えてあげるほうが仕事がスムーズになるんですね。
そうなんです。みんな自分の技術で“ちゃんとした仕事をしたい”というプライドを持っていますから、私たちはそこをサポートするというか、働きやすい環境を用意してあげる。安全面や効率、モチベーションにも関わってきますし。
職人同士や管理側との間で、こだわりがぶつかり合ったりはしませんか?
当然あります。やり方に対する意見の食い違いとか、工程をめぐるトラブルとか、いつも何かしら起きる。そこをうまくまとめていくのも現場管理者の腕ですね。お客から仕事を裁くよりも、職人さんとの調整のほうがよっぽど大変なくらいです(笑)。
やっぱり“人”を動かすのがいちばん難しいんですね。それにしても寒い屋外での朝礼や暑い環境での作業を考えると、現場仕事は敬遠されがちなイメージがあります。
それは事実ですね。若い人が敬遠して人手不足になっているのも事実。でも今は女性の職人も増えてきましたよ。TiktokやYouTubeでも、女性がカッコよく作業している動画が結構アップされてます。物理的に重い資材はありますが、軽量化が進んで昔ほどの重労働ではありません。
たしかに、壁のレイアウトを変えたり、天井を組み立てたりするのは面白そうだし、やりがいもありそう。
そう思いますよ。図面を見ながら自分で手を動かして空間を作っていくのは、クリエイティブな作業でもあります。毎回同じことの繰り返しじゃないからこそ「もっと上達したい」「もっと早く綺麗に仕上げたい」という向上心も生まれるし、やりがいを感じやすいんじゃないでしょうか。
最大規模の案件だと、どんなところを担当されるんですか?
ものによりますが、大型の病院や公共施設、商業ビルなど、工事費が数百億円のプロジェクトもありますよ。ただし、内装仕上げの部分はそのうちの5%前後。たとえば100億円の建物なら、内装の工事は5億円くらい。今は福岡の中心地で再開発が進んでいて、そこでは大きな工事がたく動いています。
そういう大きな施設を出来上がってから見ると「自分たちが作ったんだ!」っていう達成感がすごそうですね。
そうなんですよ。何十億、何百億という建物の一部分を担っているわけですが、完成したときの達成感は大きいですね。そしてまた次の現場も大きかったり、変わった形状の天井だったりして飽きないですよ。
先ほどのお話では、大規模工事になると数百億円のプロジェクトでも、御社が担当する内装仕上げだけで何億円単位の仕事になるとか。そこをまとめるのは相当大変そうですね。
ええ。やっぱり人手不足の中で、安全に、工期通りに良い仕事をお客様に提供するのは大変ですね。大手のゼネコンから「ここもお願いできないか」と追加の発注をもらえるということは、それだけ信用いただいてる証拠でもありますが、その分こちらも半年くらい前から準備して、事故なく工期どおり終わるように気を使わないといけません。
半年も前から段取りをするんですね。具体的にはどんな準備が必要なんですか?
たとえば、このフロアはいつから着工して何日で仕上げるのか、そこに何人の職人を配置するのか――そういった工程表を作って、職人を「遊ばせない」ようにシフトを組む感じですね。もし工期が少しずれれば、次の現場のスケジュールも狂っちゃいますから。
たしかに人員を確保するうえでも、先々まで見通して組まないと難しそうです。
うちの場合、施工管理担当が7人ほどいて、彼らがメインで工程を組み立てます。そのうえで現場へ行く職人を手配するんです。社内の職人もいますし、協力会社の職人もいるので、いろんな現場の都合を合わせるわけですね。
「施工管理」は、わりと稼げる職種としても有名ですよね。ゼネコンに入って1級施工管理技士を取ったら年収1000万円なんて話も聞きますが…。
ああ、それは主にゼネコン側の施工管理ですね。うちは内装仕上げの“専門工事業者”にあたるので、範囲は少し絞られます。ただ、2級でも1級でも国家資格を持っていれば「それだけで強み」になります。現場の進め方を理解するために、資格取得を目指す若手も多いですよ。
職人自身にもいろんな資格が必要なのかな、と思います。高所作業の免許とか、フォークリフトとか、内装仕上げ特有の資格とか…。
そうですね。実際に作業する職人なら、特別教育や技能講習を何種類も受講しないといけないケースがあります。耐火性能を満たすには「ここはこういう材料で貼らないとダメ」といったルールを守る必要があるんです。
法律の話が出ていましたが、建物によって求められる性能(耐火・防音など)は違うんですよね。違反すると大問題になりそう…。
「遮音壁なら〇デシベルまで音を通さない」とか、「隣室との仕切りは1時間耐火」など、法律で細かく決められています。そこを疎かにするとあとで発覚したときに大変なことになります。過去にも大手デベロッパーのマンションで一部施工不良が見つかって、大騒ぎになった事例がありますよね。
アスベスト問題とかも、昔の建物には使われていたけど今は法律で禁止されている、みたいなニュースを見ました。
昔は天井裏や柱の耐火被覆にアスベスト入りの吹き付け材を使っていたんですが、その後禁止されました。今は解体のときにアスベストが見つかると、宇宙服みたいな防護服を着て作業するんですよ。つまり、新築では使われていないけれど、解体現場で気をつけなきゃいけないという感じですね。
解体まで含めると、建設業は本当に守るべき法律が多いんですね。講習もいっぱいありそう…。
はい。会社としても「職人には講習を受けてもらって資格を取ってほしい」と思っていますし、その費用はうちで負担しています。とはいえ、資格を取った後に転職しちゃうケースもあるけど(笑)。それは業界としてのあるあるなんです(笑)。
でも若い人にとっては、キャリアアップにつながる可能性もあるわけですね。
そうです。たとえば国家試験の1級や2級を取ればステータスになりますし、次の現場で重宝される。やっぱり施工管理にしても職人にしても、法律や基準のアップデートが早いので、学び続ける姿勢がある人は伸びますよ。
建設業って単に“体力勝負”のイメージがありましたけど、実は勉強要素や資格取得もかなり重要なんですね。
そうそう。“地頭力”というか、図面を読み解く力も必須ですし。言葉で説明しにくいですけど、見たことのない記号が図面にびっしり書いてあって、それを理解して形にするわけだから。職人もそこはプロフェッショナルなんです。
自分が知らなかった世界ですごく面白いです。

多彩なキャリアパス:職人・施工管理・積算・バックオフィス
ここまで内装仕上げ業界の話ばかりしてきましたけど、だいたいイメージはつきました?
先ほどから伺っていると、本当に「家づくり=大工1人の仕事」とは違って、建設業にはものすごく多くの専門職があるんだなと驚きです。自分のイメージでは、テレビ番組の『ビフォーアフター』みたいに1社ですべてをやっているのかと思っていました。
実際には「内装仕上げ」「ガラス屋」「ドア専門」「シャッター専門」「左官屋」「タイル屋」「石工事」……といったように分業が進んでいます。1つの大きな建物を建てようと思ったら、大工の他にも本当にたくの専門職が関わるんですよ。
もし若手の新卒社員が日経金属に入社したら、最初はどんなフローで仕事を覚えていくのですか? やっぱり現場に出て、先輩職人の弟子入りみたいなイメージでしょうか。
現場で職人として技能を身に付けたい場合は、親方と呼ばれる熟練の職人について学んでいく形ですね。学校のような制度はほとんどなくて、実践を通じて徐々に覚えていくんです。もっとも、最初のうちは朝が早くてキツかったり、材料運びが大変だったりで、合わないと思ったら辞めちゃうケースもある。でもそこを乗り越えて続ければ、しっかり腕が身につくし、“一生もの”の技術になりますよ。
職人になるには体力と根気がいりそうですね。じゃあ、施工管理の方に進むケースもあるんですか?
はい。うちには施工管理を担当する社員が7人ほどいます。彼らは現場の工程を組んだり、職人との調整をしたりする役割ですね。あとは「積算業務」に携わるスタッフもいて、図面から壁や天井の面積を拾い出して「どれだけ材料が必要か」といった見積りを作っています。いわゆるバックオフィス業務もあれば、トラックの運転、経理、営業など、多彩な仕事があるんですよ。
建設業って「現場作業ばかりかな?」という勝手なイメージを抱いていましたが、裏方でパソコンを使うような業務もあるんですね。
そうです。とはいえ「体力仕事なんて絶対イヤ」って人もいれば、「外で体を動かして働きたい」って人もいる。いろんなタイプが活躍できるのが建設業の面白いところですね。たしかに現場は冬場の寒い朝礼がツラかったりしますけど、物づくりが好きな人ならやりがいは大きいはず。
“学ぶ意欲”が未来を拓く:清田社長から就活生へのメッセージ
最後に、就活生へ向けたメッセージってありますか? といっても、建設業って敬遠されがちなイメージがあるので……。
そうですね……。私自身、「建設業=キツい」だけじゃないぞって言いたいですね。大変な面はもちろんあるけど、社会インフラを支える仕事なので景気に左右されにくいし、やればやるほど専門スキルが身につく。あとは、一緒に現場を作る仲間同士のつながりも強いですよ。人と話すのが得意なら施工管理や営業もあるし、パソコン業務に興味があれば積算や事務系のポジションもある。とにかく視野を狭めずに、「建設業って実は面白そうかも」と思ってもらえたら嬉しいですね。
以前は「建設=体力勝負」というイメージでしたが、実際には法律の知識や調整力が求められたり、パソコン業務もあったりして、幅広い働き方があるんですね。
そうなんです。それに建設業は景気に左右されにくいので、安定感も高いと思いますよ。大手ゼネコンとの取引では、数百億円規模の建物の一部を任せてもらったりします。その分、人と人のつながりが何より大事。職人だってみんな誇りを持って仕事をしていますから、うまくバックアップすればしっかり応えてくれます。そこを楽しめる人なら、面白いと思いますね。
バックオフィスや現場、どちらにしても「人とのコミュニケーション」が大切そうですね。
はい。結局、人間関係なんですよね。だから僕は“どんな相手からも学ぶ”つもりで接しています。いろんな人がいるので、良い部分は吸収して、そうでもない部分は「反面教師」にして(笑)。若い方には、1秒1秒あらゆる場面で学ぶつもりでいてほしい。そうすれば、どの道へ行っても自分なりのキャリアが開けるんじゃないかなと思います。
今日は貴重なお話をたくさん伺えて、本当に勉強になりました。まさに“人とのつながり”や“学び続ける姿勢”が、建設業にとっても就活生にとっても大切だと改めて感じました。
こちらこそありがとうございました。学生の皆にも、建設の業界の実情や面白さが少しでも伝われば嬉しいです。
建物の「骨組み」だけでなく、空間をいかに使いやすく、安全に仕上げるか――そこには法律の改正や材料の進化に応じた高度なノウハウが詰まっています。職人との連携や施工管理、そして数十人規模の現場が生み出す達成感は、まさにこの業界ならではの魅力です。清田社長が語った「学ぶ意欲」や「仲間とのつながり」の大切さは、就活にも通じるメッセージでもあります。皆も、この記事をきっかけに建設業界に関心を持ち、自分なりのキャリアを思い描いてみてください。