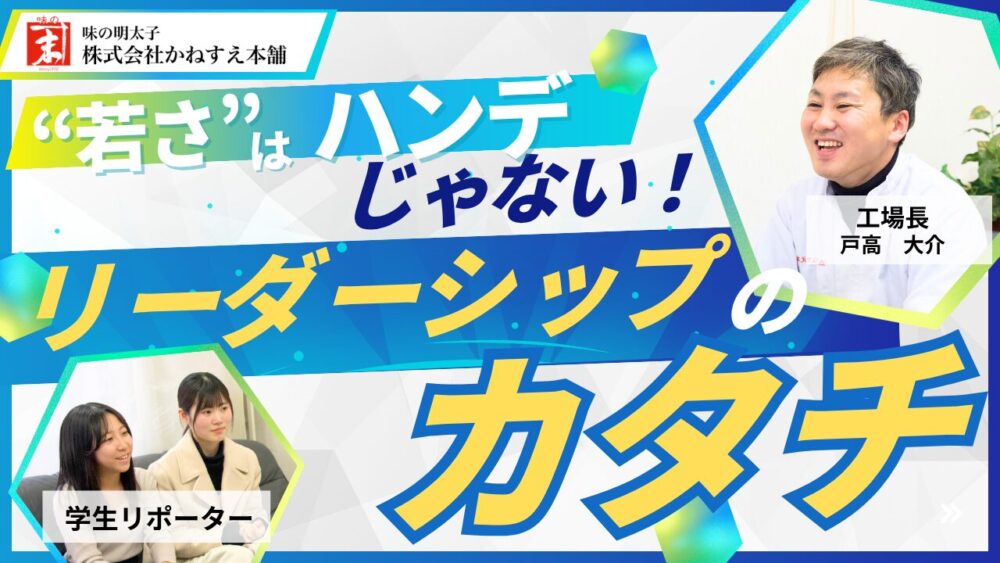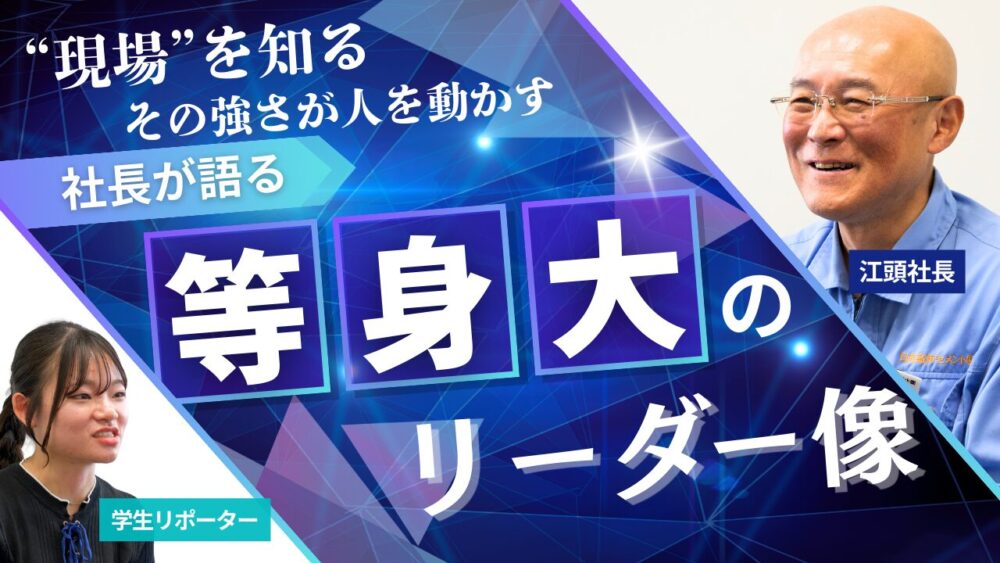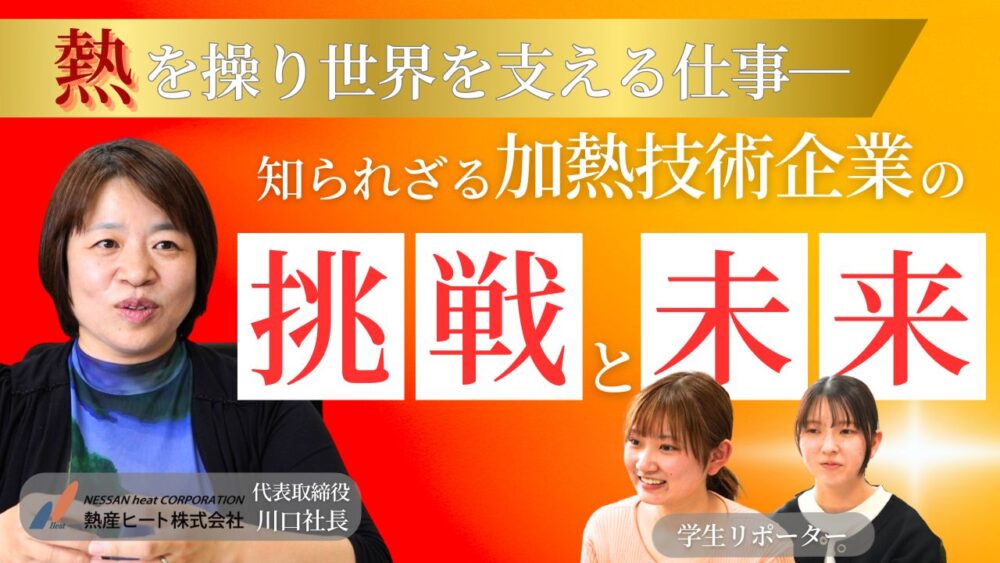「管理職=経験豊富なベテラン」というイメージ、ありませんか?
でも現実は、若いうちから責任あるポジションを任されることもある。
今回紹介するのは、30代で管理職として、周囲の無関心や不信を乗り越え、自ら動き、仲間を巻き込みながら現場を改革していったかねすえ本舗の戸高さんをインタビュー。
「言われた通りにやる」から、「自分で考え、動かす」へ。
そんな変化は、決して特別な人だけのものではなく、誰にでも訪れる可能性がある——。
“若手でも現場を変えられる”そのリアルに、学生リポーターが迫りました。

“38歳で工場長”に抜擢。
38歳で工場長になるというのは正直驚きました。私のイメージでは、工場長は50代くらいのイメージで工場全体をまとめるのはかなりの経験が必要そうだと思っていました。そこまでの経緯を詳しく教えていただけますか?
実は高校を卒業後、18歳でガス会社の下請け企業に入って営業兼工事を担当していたんです。そこでは細かい修理から大掛かりな工事までいろいろ経験をさせてもらっていて。そんな時に、交際相手との結婚が決まり、妻の両親が経営する「株式会社かねすえ本舗」が忙しい時期だったので事業を手伝ってほしいと言われたんです。でも、私は「何か一つ成果を出してから会社を辞めたい」という思いが強くあったので「最年少で役職に就く」という目標を立てて、全力で仕事に取り組みました。見事目標を達成させ、しっかりと成果を出したあと、24歳で会社をやめ、25歳でかねすえ本舗に入社。そしたら、わずか3年後の28歳で工場長を任されたという流れです。ただ、最初は本当に肩書きだけで「名ばかりの工場長」状態だったので、正直戸惑いも大きかったですね(笑)。
入社3年で工場長って、想像以上に早いですね…。私ならまだ研修中かもしれません(笑)。やはり早い段階で役職についた秘訣みたいなものがあるのでしょうか?
私たちの工場は女性従業員が多く、業界としても男性が管理者になるケースが多いんですね。だからこそ、私が入社したときには「どう現場を動かそうか」と考えました。その一番大きなポイントは「誰よりも現場に入り込み、手を動かすこと」だったと思います。最初は社長が他企業とのやり取りをしていたのですが、同席させてもらう機会も増え、自然と私1人で対応するようになりました。私に問い合わせがくるようになり、「実際の工場のことを分かっている人が対応したほうが早いし、正確だ」となっていったんです。また、「役職って人を育てる」という考えがあって、早めに責任を引き受けたほうが成長スピードも上がるだろうと考えました。
工場改革への挑戦と“スピード感”を活かした運営
工場長になってからは、具体的にどんな改革を行ったのでしょうか? 例えば製造工程の見直しなども含めて、気になるところです。
まず、うちは職人肌の社長の影響で、いわゆる「マニュアル」的なものがほとんどなかったんです。私自身はサラリーマン経験があったので、「ある程度の仕組みやシステムは必要だ」と感じ、工場の業務フローを一から整理して作り直しました。例えば誰がどの作業をいつ担当するかとか、機械のメンテナンス手順など、そうした“見える化”を進めたんです。
なるほど。一般的には工場ってむしろマニュアルだらけで、逆に変化がしづらいイメージもありますが…そことは違うんですね。
そうなんです。意外に「マニュアルがなくて困る」状態でした。うちは小規模な会社なので社長との距離が近く、「明日変えたい」と言えば翌日にも変更できるスピード感が強みなんですよ。大企業だと承認に時間がかかりますが、ここは思い立ったらすぐ行動できる。だからこそ、仕組みづくりと同時に、必要だと思ったタイミングでどんどん改善を重ねられます。
従業員の声を尊重するコミュニケーション
変化についていけない方や、新しい取り組みに抵抗を示す方も、正直いらっしゃるのでは…と思うんですが、そういう場合はどう対応していますか?
もちろんいますよ(笑)。人によっては「これまでこうやってきたのに、なんで急に変えるの?」と戸惑いがありますよね。でも、私は「なぜ変える必要があるのか」を必ず説明します。ただトップダウンで指示を出すだけでは不満が溜まるので、きちんと理由を伝えて納得してもらう努力をするんです。日頃からしっかりコミュニケーションを取って、現場の人が意見を言いやすい雰囲気づくりを心がけています。
現場の方が自発的に意見を出してくれるようになると、改革もしやすいですね。具体的に「大変だった出来事」などはありましたか?
毎年「目安箱」を置いて、匿名で従業員が自由に意見を書いて出せるようにしています。以前、20件くらい要望が集まって、そのすべてを改善したことがあります。例えば和式トイレを洋式に改装することや、冷房を増強することなど大がかりな改修もあって交渉や費用面で苦労しました。でも「働いてくれる皆さんに、意見が形になる会社だと感じてほしい」と思ったんです。それを契機に、従業員のモチベーションも上がったと感じます。
そこまで意見を尊重してくれる会社は、学生から見ても魅力的だと思います。
ありがとうございます。大企業に比べて規模は小さいかもしれませんが、大規模ではないからこそ「頑張った分だけ成長を実感できる」「筋が通った意見なら採用されやすい」という強みがありますね。
学生時代は「クズ」!? から始まった大逆転ストーリー
今のお話からは想像しにくいのですが、学生時代はけっこう自由奔放だったと伺いました。どんなタイプの学生だったのでしょうか?
いや、本当に「クズ」と呼べるレベルでしたよ(笑)。夜中まで遊んで、授業中は爆睡、昼頃にふらっと早退して遊びに行く…という生活を続けていました。先生も呆れていたと思いますね。
そこからどうやって社会に出たんですか? その生活リズムだと、社会人になるのは厳しそうに見えますが…。
高校卒業後、ガス会社の下請け企業で営業兼工事を始めましたが、19〜20歳くらいで挫折を味わいます。要領だけはいいつもりで「まぁなんとかなるだろう」と思っていたら、後輩にボーナスを抜かされてしまって。そこで初めて「動かなきゃ結果はついてこない」と思い知りました。
その挫折があったからこそ、今のストイックさがあるんですね。
そうですね。20歳で真剣に仕事に打ち込んだら数字が上がって、「やれば結果が出る」って実感しました。高校時代にもっと真面目にしておけばよかったなと思う部分もありますけど(笑)。でも若い頃に恥をかきまくったおかげで、「変にカッコつけない」「失敗を恐れない」性格になれたともいえます。

挫折と努力が生んだ“修理マスター”の力
それでも、ガス器具の修理や大工工事までできるようになるのは相当な努力が必要ですよね。途中で心が折れたりはしなかったんでしょうか?
不思議と、「やると決めたらやるだけ」だったのであまり不安はありませんでした。夜中に誰もいない会社へ戻って、捨てられた機器を一人でバラしながら構造を覚える日々を1年ほど続けたら、だいたいの修理はこなせるようになったんですよ(笑)。修理ができるとお客様からも「この人なら大丈夫」と信頼される。そこから「工事も自分でやれたら、もっと便利かも」と思って、今度は工事業者に同行させてもらって、1から教わったんです。
まさに“独学”と“行動力”の塊ですね。そこまでやりきれたのは、何かモチベーションが上がるようなやりがいがあったからですか?
一つは「お客さんから直接感謝されると嬉しい」という素直な気持ちでした。あと、「同じ会社で働く仲間に認められたい」という思いも強かったですね。仕事仲間と家族って、下手すると一日のうち半分以上の時間を共にするじゃないですか。その人たちに「戸高がいるから助かる」と思ってもらえるのがやりがいでした。
小さな目標の積み重ねとビジョンの大切さ
その後、明太子の製造会社に転職しても抵抗はなかったんですか?
全くなかったです(笑)。私は「毎日何か一つでも学ぶ」という積み重ねを大事にしていて、どこに行っても応用できると考えていました。前職で新人に「一日1個覚えて帰れ」と指導していたのを、自分自身でも実践したんですね。だから業種が変わっても「あれ?できるじゃん」と意外とスムーズに馴染めました。
30歳を超えた今は、その“一日1個”という短期目標だけではなく、長期的なビジョンも持つようになったと…?
そうです。若い頃は目の前のことに集中していればよかったけれど、ある程度年齢を重ねると「3年後はどうなっていたいか」「5年後のゴールは?」と考え始めたほうが、自分の成長にプラスになると感じます。私自身も年間目標や中期的な計画を立てていますよ。
「自分を採らなきゃ損します!」と断言できる就活マインド
就職活動中の学生の多くが「ありきたりなエントリーシートや面接じゃ埋もれてしまう」と悩んでいます。戸高さんならどうアプローチしますか?
もし今の私が学生に戻って就活をするなら、「私を採らないなんて絶対損ですよ!」くらいの気持ちで望みます。その代わり、企業研究や業界研究は徹底的にします。たとえばSNSや企業のウェブサイト、ニュース記事などを片っ端からチェックして、そこでしか得られない情報をまとめて面接でぶつける。みんな同じ書類選考を通って同じ面接を受けますから、差別化を図るには「ほかの人がしない行動」をするのが手っ取り早いと思います。
他の人と違う手段として、コネクションや直接アポを取る…というお話もありましたね。そこまでやる人は少ないかもしれません。
だからこそ効果的ですよね(笑)。それに自分自身の強みは意外と人に聞いてみないと分からないものなので、家族や友人、先輩、時には講師の方など周囲に聞いてみるのも良いです。私も妻から「やりすぎ」と言われることで初めて「それが自分の強みかもしれない」と気づきましたし(笑)。

地域活動など社外活動にも奔走…そこまで熱くなれる理由とは?
明太子の製造会社というと、どうしても商品自体に注目が集まりそうですが、戸高さんのお話を伺うと“人”が主体になっている印象が強いですね。実際に、会社以外でもさまざまなプロジェクトをされているとか…?
そうなんです。実は青年会議所で地域の活動に参加したり、兄が経営する弁当屋を立て直す手伝いをしたりと、週の半分以上は何かしら会議や企画に追われています(笑)。仕事が終わったら夜中まで資料づくりをして、そこから弁当屋の仕組みを整える作業にかかるなど、かなり詰め込んでますよ。妻から「やりすぎ!」と言われるのも仕方ないですね。
そこまで詰め込んで burnout(燃え尽き)状態になったりしないんですか…?
むしろ締め切りをギュッと詰めることで、自分の成長スピードが上がる感覚があるんです。普通なら「1年かけてやろう」というものを「今月中にやる」と決めると、なりふり構わず動くじゃないですか。その結果、いろんなアイデアが出たり、別のことに時間を使えたりもするので、「追われている感覚」が逆に楽しかったりします。
ご家族との時間は確保できていますか? 子どものサッカーが癒やしだとも伺いましたが。
日曜はなるべく子どものサッカーの応援に行きます。私は球技が得意ではないんですけど(笑)、試合を撮影して家族で動画を見ながら「ここをもうちょっとこうしたら?」なんてアドバイスするのが楽しみですね。子どもが少しずつ上達していく姿を見ると、「よし、自分も頑張ろう」と思えるんです。
ポジティブ思考と“失敗を恐れない”スタンス
すごいエネルギッシュだと思いますが、さすがに落ち込んだり失敗してどうしようもなくなることはありませんか?
ミスをしたら「今ここで失敗しておいてよかった」と考えます。大きな失敗を未然に防げたって思えるんです。これは妻の影響が大きいですね。昔、妻がものすごくポジティブで「そんなにネガティブだと損するよ」と言われたのがきっかけで、私も考え方をシフトするようになりました。いまは妻のほうがややネガティブ化してるんですけど(笑)。
そうだったんですね!部下や同僚の中にはネガティブ思考の方もいると思いますが、どうフォローしていますか?
とにかく最初は話を聞いて、「できない理由」じゃなくて「どうすればできるか」を一緒に考えるように促します。愚痴や文句を言うだけでは状況が変わらないですからね。少し視点を変えれば案外「ここをこうすれば解決するかも」と思いつくはずなんですよ。そうして動き出せれば、楽しい雰囲気に変わっていくものだと思います。
明太子へのこだわりと“最後の決め手は人柄”の精神
今回は明太子の話よりも戸高さん個人のお話をたくさん伺っている気がしますが、明太子の仕事の方はどんな感じでしょうか。
もちろん明太子には自信がありますよ(笑)。でも、やはり最後は「人柄」を知ってもらうことで商品が選ばれると思うんです。美味しいものは世の中にたくさんあるじゃないですか。その中でも「戸高さんやスタッフの人柄がいいからここで買う」と思ってもらえるのが一番嬉しいんですよ。
接客の面でも大事にしていることはあるんですか?
はい。閉店間際にお客さんが来ると、従業員は「早く上がりたかったのに」と思うかもしれませんが、私は「わざわざ時間を使って来てくれたんだよ。ありがたいことじゃない?」と伝えます。そういうちょっとした気持ちの持ち方が、会社全体の空気を変えると思うんです。
「仕組み化」と「還元」で“みんながハッピー”を目指す
会社が儲かれば従業員にも還元したい、とおっしゃっていましたが、具体的にどんなビジョンを持っているのでしょう?
やはり社員の給与や待遇を良くするには、利益を上げないといけません。そのためには仕組みづくりとコミュニケーションが重要だと考えています。今、私が工場長として「5年後にこうなっていたい」という目標を掲げて頑張っているところです。「あの時言ってたことが全部実現したね」と後で笑って話せるようになりたいですね(笑)。
そういう「先を見据える姿勢」は、正直、就活生にも参考になります。私たちは目の前のエントリーシートや面接に追われがちですから…。
うちの母親が「若いときの苦労は買ってでもしろ」とよく言っていたんですよね。私自身も、大変な道を選んだ分だけ後から大きなリターンがあると実感しているので、ぜひ若いうちはいろんな苦労を積極的に取りにいってほしいです。

大切なのは“行動力”と“ポジティブ変換”
ここまでお話を聞いて、最初は明太子の製造会社だと思っていましたが、実は“人”にめちゃくちゃフォーカスしている会社なんだなと感じました。とても興味深いです。
ありがとうございます。ちょっと変わり者かもしれませんけどね(笑)。でも、やはり学生の皆さんに伝えたいのは「失敗を恐れずに行動してみること」です。恥をかくのは一瞬だけど、その経験は長く活きます。しかも人と違う道を選んだほうが、後々の成長スピードも速いというのが私の持論です。
確かに「点と点が繋がる」というお話もありましたが、今すぐ成果が出なくても、いつか何かの形で活きるかもしれないですね。私も勇気をもらいました。
本当にそう思いますよ。10年ぶりに再会したお客さんが「まだここで働いてたんだ! じゃあお願いしたい」と連絡をくれたり、昔の繋がりが現在の売上に結びつくこともありますからね。一見無駄に見える努力が、後々自分を助けてくれるんだと実感します。
今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。今までの就活観がだいぶ変わった気がします。
こちらこそ、いろいろ質問してもらえて楽しかったです。就活でも社会に出てからでも、まずは行動してみることが大事だと思います。「自分ならこう動く」という強い意志を持ってアピールしていけば、きっと面白い道が開けるはずですよ。
わかりました! 恥をかくのも財産だと思って、チャレンジ精神を大事にしていきたいと思います。本当にありがとうございました。
ぜひ頑張ってください。いつか「実はあのときの話を聞いて、こういう仕事に就きました!」なんて報告してもらえると嬉しいですね。気が向いたらいつでも遊びに来てください(笑)。
はい、ぜひ伺います! 本日はありがとうございました。
「若いうちに苦労を買ってでもしろ」——
母の言葉を胸に、どんな困難も「チャンス」に変えてきました。
鍵は、“とにかく動くこと”と“ネガティブをポジティブに変換する力”。
その姿勢は、就職活動に悩む学生にも大きなヒントを与えてくれます。
「私を採らないなんて損ですよ」と言える自信は、裏付けとなる行動の積み重ねから生まれる。
変化を恐れず、誰よりも現場に入り込み、仲間と向き合い続けてきたからこそ語れる言葉です。
このインタビューが、あなたの就活における「一歩を踏み出す勇気」につながることを願っています。