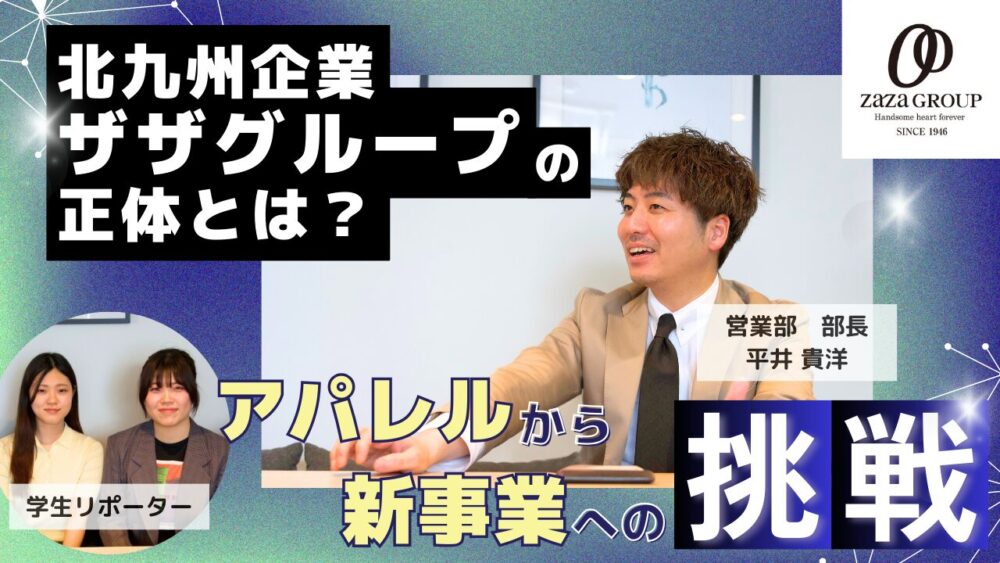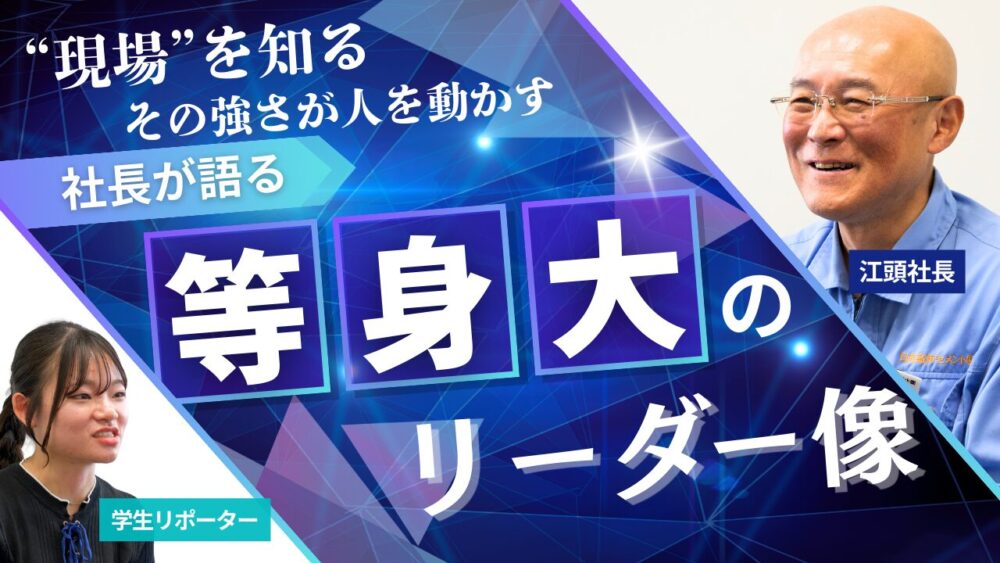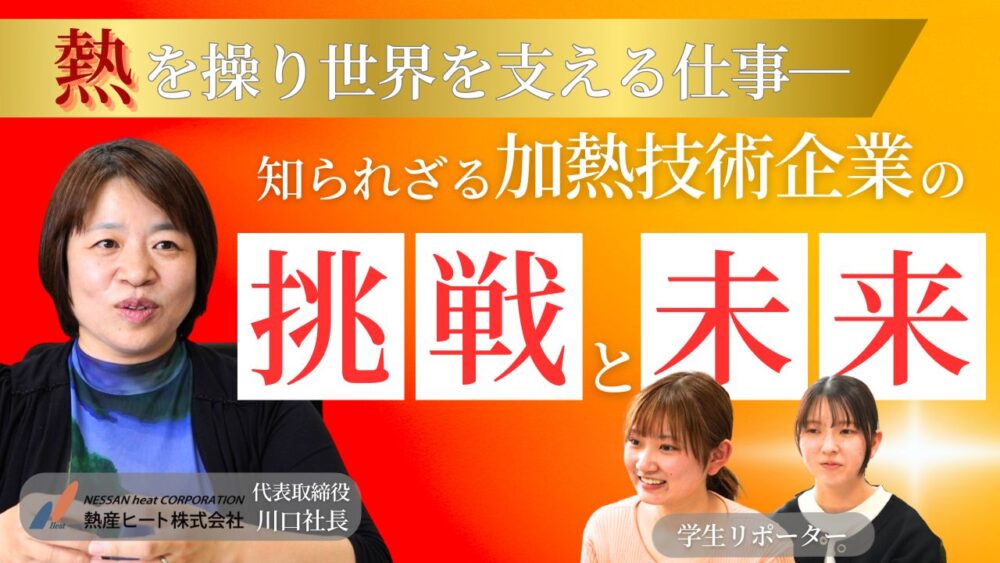“ザザ”って聞いたことあるけど、実際にどんな会社?——そんな学生も多いのではないでしょうか。
実はメンズ服やスーツの販売だけでなく、大きいサイズ専門店やチケットショップ、雑貨店、さらにはECや新規事業まで、幅広く展開している会社なんです。
今回は、学生リポーターが現場での経験を重ねてきた営業部の部長に、仕事のリアルや会社の魅力についてたっぷりお話を伺いました。

スーツだけじゃない!多角的経営のリアル
ザザグループって、最初は「スーツのお店かな?」って思ってたんですけど、実際にはいろんなことをされてるんですよね?
そうなんですよ。スーツの印象が強いかもしれませんが、実はアパレル以外にもいろんな事業を展開していて、グループ全体では全国に90店舗以上あるんです。
そんなに!? もっと小規模なイメージでした…。
よく言われます(笑)。主力は「ビッグエムワン」という大きいサイズ専門のアパレルブランドで、それに紳士服の「ザザ」と、オーダースーツの「オーダーボックス」が加わります。この3ブランドを組み合わせて展開している店舗が多いですね。
店舗の中に複数のブランドが入ってるんですね。
建物の1階に大きいサイズ、2階にオーダーやビジネススーツという形で構成しているところもあります。最近では、最初から価格を見直して、クーポンやセールに頼らない“わかりやすい価格設定”の店舗も出てきています。
価格が分かりやすいと安心ですよね。
まさにそこを狙ってるんですよ。どの世代にも伝わりやすくて、比較もしやすい。「あれ?結局いくらになるんだっけ?」ってならないのが大事かなと。あと、アパレルの他に意外と知られてないのが、金券ショップの「スーパーチケット」ですね。商品券や回数券などを扱っていて、福岡県内に数店舗展開しています。
それもグループの事業なんですか!? 全然知りませんでした!
ザザグループの名前は出していないので、気づかれないことも多いですね(笑)。他にも、春日市には「ファーミーホーミー」っていう生活雑貨のお店もあります。ちょっとこだわった雑貨を扱っていて、そこは1店舗だけですが根強いファンがいるんですよ。
スーツだけじゃなくて、想像以上に幅広いですね…!
さらに今は、ネット販売にも本格的に取り組んでいます。「ビッグエムワン」の商品をオンラインで買えるようにしていて、その運営は社内のWEBチームが担当しています。商品ページを作ったり、注文処理や発送業務まで一貫してやってますよ。
ネット通販まで社内で?それはすごいですね。
そうなんです。専任のスタッフがいて、日々の売れ行きやお客様の声を分析しながら、どんな商品が求められているかを考えて運営しています。さらに、大阪にはネット販売専門の子会社もあって、そちらではまた別のラインで動いているんです。
リアルの店舗とネット、両方をしっかりされているんですね。
どちらも「お客様とつながる場所」という考え方は同じです。実際に会わなくても、どうしたら安心して買ってもらえるか。写真の見せ方、商品説明、届くまでのスピード感——すべてがお客様との信頼関係づくりに関わってきます。
ネットも、ただ物を売るだけじゃないんですね。
そうなんです。だからこそ、対面でもオンラインでも、誠実に向き合うことが大事ですね。それは、どの事業でも共通して言えることです。
それだけ多くの事業をやってても、一つの軸がしっかりしてるからブレないんですね。
ありがたいことにそう言ってもらえることが多いです。実際、これまでに地元の大学と一緒に取り組みをしたり、学生さんにモデルとして協力してもらったりと、地域との関わりも大事にしてきました。もっと若い方にうちのことを知ってもらえる機会が増えると嬉しいですね。
店舗運営は「小さな経営」。ザザグループならではの働きがい
部長は営業部に所属されているんですよね? いわゆる「営業」っていうと、取引先をまわるイメージがありますが、店舗も営業部なんですか?
そうですね。ザザでいう営業部っていうのは、一般的なBtoBの法人営業とはちょっと違って、基本的には「店舗の運営」に関わる部門なんですよ。店頭での販売をはじめ、売上やスタッフのマネジメントまで含めて全部ですね。
じゃあ、いわば“店舗経営そのもの”を担っているような…?
まさにその通り。店舗ごとに数字の目標があるので、いかに売上を上げていくか、人件費をコントロールするか、在庫を回すか。まるで小さな会社を動かしているような感覚です。だからうちでは「店長=経営者」ってよく言われますね。
なんだか、思っていたよりもすごく責任のある仕事なんですね…。
でもね、うちは若いうちからそれを任せる文化があるんです。僕も高卒で入社して、3年目の21歳で店長になりました。
えっ、21歳で!? それってかなり早い方なんじゃないですか?
会社によっては考えられないかもしれませんね。でも当時の僕に特別なスキルがあったわけじゃなくて、「まずやってみなさい」っていう社風が大きかったんです。最初は全然わからないなりに、がむしゃらでしたよ(笑)。
でもそうやって、現場で学ぶことができるのって強いですよね。
そうですね。座学より現場。特に接客業って、お客様と直接向き合うからこそ、反応がダイレクトに返ってくる。うまくいけば売上が伸びるし、うまくいかなければ目標に届かない。悔しいけど、そこが面白いところでもあるんですよ。
確かに、成果が数字で見えるとやりがいも大きそうです。
僕も最初は失敗ばかりでした。でも、試して、反応を見て、また変えてみる。その繰り返しがどんどん楽しくなっていって。「どうしたら売れるんだろう」って考えるクセが自然とついてきましたね。
なるほど。試して、ふり返って、またやってみる…その積み重ねが大事なんですね。
まさにそうです。あと、店舗の中でのマネジメントもやっぱり大きいですね。スタッフの配置をどうするか、パートさんにどう声をかけるか、シフトや教育まで、全部がつながってるんです。
どこかの一部分だけやる仕事じゃなくて、全体を見るってことなんですね。
もちろん、最初から全部うまくできるわけじゃない。でも任せてもらえる環境があるから、自分で試行錯誤できる。失敗したら「次どうする?」って考えて、また挑戦できる。それがこの仕事の面白さだと思います。
部長ご自身も、やっぱり現場をしっかり経験してから今の立場になられたんですよね?
そうです。僕は2店舗しか店長経験してないんですけど、そこからブロック長やマネージャー、いまの部長っていう流れでやってきました。いきなり“上から見てください”じゃなくて、ちゃんと現場を踏んできた上でマネジメントをしています。
それなら、現場の気持ちがわかるし、現場にも信頼されそうですね。
そうでありたいですね。現場があってこその会社なので。ザザでは「マネージャーも売場に立つ」が当たり前。僕も週末は普通に店頭に出てますよ。
部長が!? それはちょっと意外です!
どんな立場になっても、現場を知っておくことは大事だと思ってます。お客様の声やスタッフの動き、商品がどう見られているかっていうのは、やっぱり現場にいないとわからないですからね。

店長から部長へ。スピーディーなキャリアップと仕事の本質
21歳で店長ってかなり早いと思ったんですけど、その後もずっと順調に昇進されてきたんですか?
うーん、順調かどうかって言われると…正直、そんなかっこいいものじゃないですよ(笑)。気づいたら今の立場にいた、っていう感じかもしれません。
え、そうなんですか? てっきり順調にステップアップされてきたのかと…。
いやいや、むしろ毎回「もう無理かも!」って思いながらやってましたね(笑)。でも、続けてこれたのは、やっぱり「やらせてもらえた」環境があったからだと思います。任されて、失敗して、それでもまたチャンスをもらえて。それが繰り返されて今に至るって感じです。
そういう環境って、けっこう貴重ですよね。普通は失敗したら評価が下がっちゃいそうな…。
たしかに。でも、うちは「まずやってみろ」っていう文化が強い。結果が出なくても、「じゃあ次どうする?」って問いかけてくれる風土があるんです。だから、自分でも自然と「次はこうしてみよう」って思えるようになったし、失敗することを怖がらなくなりました。
それってすごく働きやすいし、成長しやすい環境ですね。
そう思います。僕自身もたくさん失敗してきたけど、その都度まわりが支えてくれたし、「とにかく動け」「考えすぎるな」っていうのをずっと言われてきました。
それで実際に結果がついてきたってことですよね?
うーん、どうなんだろう。結果っていうより、「やり続けてたら見える景色が変わってきた」って感じですかね。最初は売上を作ることに必死だったけど、途中から「チームで成果を出すにはどうしたらいいか」とか「後輩を育てるには何が必要か」とか、視野が広がっていったと思います。
責任が増えるにつれて、見えてくるものも変わるってことですね。
そうだと思いますよ。店長の頃は自分の売上とお店の数字しか見てなかったけど、今は九州全体を見てるから、「どうやって人を動かすか」ってことの方が大きい課題になってきてますね。
そこは苦労も多そうですね!
もちろん数字を上げるのも大変だけど、人を育てるのはもっと難しいです。でも、それがうまくハマったときってめちゃくちゃ嬉しいですよ。「あの子、前はコミュニケーションが苦手と言っていたのに、店長になった」とか、成長を目の当たりにできるのは本当に感動します。
そうやって成長の瞬間を現場で見守れるのって、やっぱり嬉しいですよね。育てる立場になった今でも、現場での関わりは大切にしてるんですか?
大事にしてます。現場の声を知らない人がマネジメントしてもうまくいかないと思うし、だからこそうちでは上の立場になっても現場に立つことが普通なんです。
そういう一貫性があるから、若手も安心して働けるのかもしれないですね。
そうだったら嬉しいですね。ザザグループでは「優秀だから昇進する」っていうより、「手を挙げた人が任される」っていう文化なんです。だから、僕も人が足りないときに自然と「やります」って言ってきただけかもしれません(笑)。
でも、やりますって言えるのがすごいことだと思います!
ありがとう(笑)。でも、そういう小さな「やります」の積み重ねは、どこの会社に行っても自分のキャリアをつくっていく大事なものだと思います。
なぜザザグループは女性が強い?現場でわかった本当の理由
ザザグループでは、結婚や出産を経ても女性がいきいき働いているって聞いて素敵だなと思いました。現場で働いていて、そういう強さや粘り強さを感じることってありますか?
めちゃくちゃ実感してます(笑)。もちろん性別に限らず頑張っている人はたくさんいますが、ザザグループでは特に女性が多く活躍していて、粘り強く最後までやり抜く姿に学ばされることも多いです。
どういうところでそう感じるんですか?
たとえば新しい仕事を任せたとき、男性は「無理そうだったら一旦引いて考える」ことが多いけど、女性は「とりあえずやってみる」って姿勢がある。もちろん人によるけどね。でも、あきらめないで続ける人は女性が多いなって現場で感じます。
それって、育成する立場からしても頼もしい存在なんでしょうね。
ほんとにそうですね。こっちが「無理しないでいいよ」って声かけるくらい、真面目に向き合ってくれるんですよね。もちろん、最初からうまくいく人なんていないんですけど、それでも「一回やってみます」って言ってくれる人が多いですね。
たしかに、「できるかどうか」じゃなくて「やってみる」って姿勢がある人って、成長も早そうです。
それに加えて、観察力もすごく高いと思います。細かい変化に気づいたり、お客様との距離感をうまく取ったり、相手の気持ちを察する力がある。接客業ではめちゃくちゃ強みになりますね。
たしかにそれは納得です。人との距離感って、意外と難しいですもんね。
そうそう。あとは、やっぱり責任感が強い。パートさんの中でも「このお店は私の店だ!って思ってるんじゃないか」ってくらい、主体的に考えてくれる人も多いですよ。
会社としても、女性が活躍できるように何か工夫されているんですか?
大げさな制度とかではないですけど、「任せる文化」があることが大きいかもしれませんね。年齢や性別に関係なく、手を挙げた人にチャンスがある。だから女性の店長も多いし、中には10ヶ月くらいで店長になった人もいますよ。
えっ、入社して1年経たないうちに店長って、すごいですね!
もちろん、その人が前職で販売の経験があったというのも大きいですけど、それでもスピード感はかなりある方だと思います。やっぱり「この人なら任せられる」と思ったら、迷わず任せるのがうちのやり方なんです。
でも、いきなり店長って不安もありそうですよね。
そうですよね。僕が見ても「まだ早いかな」って思うこともあります。でも、任せる以上は周りがサポートしますし、何より本人が「やってみます」って言ったら、あとは信じて任せる。それが育てるってことだと思ってます。
そういう信頼のされ方って、働くうえですごくありがたいですね。
任せることはプレッシャーでもあるけど、同時に期待でもある。期待されるって、やっぱり人を伸ばす力になりますよね。そうやって、女性もどんどん前に出られる環境になっているんじゃないかなと思います。
なるほど…。制度じゃなくて、「人をちゃんと見る風土」が根づいてるんですね。
そう言ってもらえると嬉しいですね。うちは本当に、性別で判断しないし、「この人ならできる」と思えばちゃんとチャンスを渡します。そのチャンスをつかんでるのが、たまたま女性が多いってだけかもしれないですね。
自由だけど厳しい!?ザザグループのリアルな企業風土
ここまでお話を聞いていて思ったんですけど、ザザグループって、かなり自由度が高い会社ですよね?
うん、そうですね。正直、ザザはかなり「自由」です(笑)。でもそれと同じくらい「責任」もセットになってると思います。
自由と責任…具体的にはどんな感じなんでしょう?
例えば、ザザグループの店舗って全部「単独採算制」なんですよ。つまり、お店ごとに収支を管理していて、人件費や水道光熱費、広告費まで、ある程度店長に裁量があります。
えっ、店長がそこまで判断するんですか!?
そうなんです。「経営者感覚でやってほしい」という会社の方針があるので、仕入れや販促に関しても、現場の判断が重視されます。「このエリアのお客様には、こういう打ち出し方が合うんじゃないか」って考えて、自分たちで企画して動かせるんですよ。
すごい…それって、めちゃくちゃやりがいがありそうですけど、プレッシャーもありますよね。
ありますね(笑)。でも、だからこそ面白いとも思います。たとえば同じブランドでも、A店は人件費を抑えて店長自身が売場に立ちまくって利益を出すタイプ、B店はスタッフに任せてマネジメントに注力するタイプ、といった具合に、お店ごとの「色」が出るんですよ。
店舗によって経営スタイルが違うって、ちょっとベンチャー企業みたいな感じですね。
でもね、その分数字はしっかり見られます。何にいくら使って、どれだけ売れたのか。結果が出なかったら「何が足りなかった?」って、ちゃんと検証されます。
自由な分、結果に対する説明責任も求められるってことですね。
その通り。だから店長って、ただの現場リーダーじゃないんです。店舗の戦略も、売上計画も、在庫管理も、全部任されてる。裁量がある分、自分の判断で店が良くも悪くもなる。でも、逆に言えば、「自分の力でお店を育てていける」っていう面白さもあるんですよ。
マニュアル通りに動くのとは、まったく違うんですね。
マニュアルも最低限はありますけど、それよりも「その地域に合うやり方を、自分で考えて実行する」ってことを大事にしてます。自由って聞くとラクそうに聞こえるかもしれないけど、実際はめちゃくちゃ考えるし、動かないと結果が出ない。だから「自由だけど厳しい」って言うのがぴったりかもしれませんね。
なるほど…。たしかに「自由=ラク」ではないですね。
あともうひとつ。ザザグループには「トップも現場に立つ」文化があるんです。うちの社長も正月から店に立ってますし、僕も週末は普通に売場に入ってます。現場感覚を失わないようにっていうのもあるし、実際にお客様と接することで、数字だけではわからないことが見えてくるんですよ。たとえば、売れてない商品があったとして、「これ写真と実物の印象が違うな」とか、「説明が伝わってないな」とか。現場に立つと、そういう気づきがあるんです。
それを部長クラスがやっているって、すごくリアルですね…。
自由にやらせてもらえるのもありがたいですが、うちの会社がすごいのは「現場主義」がちゃんと続いてるところだと思います。上も現場を知ってるから、判断に説得力があるし、スタッフからも信頼される。だから責任ある立場でも、孤独にならないんです。
信頼関係があるからこそ、自由な判断も成立するんですね。
自由って、実はすごく高度なんですよ。だからこそ、うちは若いうちから任せていく。挑戦する気持ちがある人には、ぴったりな会社かもしれませんね。

「お客様の喜び」が売れる営業の原点。成功する接客術とは
営業とか販売って、なんとなく「数字を追う仕事」ってイメージが強いんですけど、実際にはどうなんでしょう?
たしかに数字はついてきますけど、ザザでいちばん大事にしてるのは「お客様に喜んでもらえるかどうか」です。結局そこが原点であり、ゴールだと思ってます。
喜んでもらうっていうのは、具体的にどういうことなんでしょう?
たとえば、何気なく立ち寄ったお客様が「今日は買うつもりなかったけど、来てよかった」って言ってくれたら、僕らにとってはそれがいちばん嬉しい言葉なんですよ。その“満足のひとこと”があるかないかで、売上以上に自分たちの手応えが変わっていきます。
たしかに、自分がお客さんの立場でも「楽しかったな」と思える接客って、心に残りますよね。
そうそう。営業っていうと、「売り込む仕事」って思われがちだけど、実際にはその逆で、「信頼されること」「納得してもらうこと」が本質なんです。押し売りしても絶対に続かないし、次にはつながらない。
売るためにはどうすればいいんですか?
僕がよくスタッフに伝えてるのは、「商品じゃなくて、お客様の気持ちを見ること」。何に困っているのか、どんな場面で使いたいのか、ちょっとした会話の中からヒントを拾っていくんです。
そういう観察力とか、空気を読む力も大事なんですね。
めちゃくちゃ大事です。でも、それって特別な才能じゃないんですよ。たとえば最初のうちは「このスーツ、似合いますよ」しか言えなかった子が、回数を重ねていくうちに「こういう場面ならこの色がいいですよ」って提案できるようになっていく。その積み重ねです。
つまり、「型」を覚えるだけじゃなくて、「人を見て対応を変える」ことが大切なんですね。
その通り。同じ商品でも、お客様によってアプローチの仕方は違います。でも、ここで大事なのは「提案をあきらめないこと」。これが意外とできてない人、多いんですよ。
えっ、どういう意味ですか?
たとえば、「このお客様には高いから無理だろうな」って勝手に決めつけて、提案そのものをやめてしまう。でも実際は、その人にとって“価値ある一着”なら、ちゃんと選んでくれるかもしれない。だからこそ、全員にきちんと向き合って、同じように丁寧に提案するってことが大切なんです。
なるほど…。お客様を“選ばない”って、実はすごく大事なことなんですね。
そうなんです。そして、何より「この人は本当に私のために考えてくれてるな」って伝わる接客ができれば、自然と結果もついてくる。商品知識より先に、人への興味と気遣いがあるかどうか。そこが営業の原点だと思いますね。
たしかに。自分のことをちゃんと見てくれてる人からの提案って、受け入れやすいです。
逆に「この人、売りたいだけだな」っていうのも、意外とすぐ伝わるんですよ(笑)。だからこそ、心の底から「この人に喜んでほしい」と思えるかどうかが大事。そういう気持ちがある人は、必ず接客が上手になります。
それって、就活でもちょっと似てる気がします。話す内容より「どう向き合っているか」を伝えられることが大事ですよね。
そうだね。どんな仕事でも“相手視点”があるかどうかで、結果は変わる。営業も接客も、突き詰めると「人と向き合う力」がすべてなんだと思います。
現場主義、挑戦、自由と責任——ザザグループの話を聞いていると、社員一人ひとりの「やってみたい」という気持ちに本気で向き合う会社だということが伝わってきます。若くして店長やマネージャーを任されるのも、経験よりも意欲を重視する風土があるからこそ。アパレルの枠にとどまらず、事業の幅を広げ続けるこの企業には、まだまだ多くのチャンスが眠っていると感じました。「会社をつくる一員」になって働きたい。そう思った人にこそ、ぜひ知ってほしい企業です。