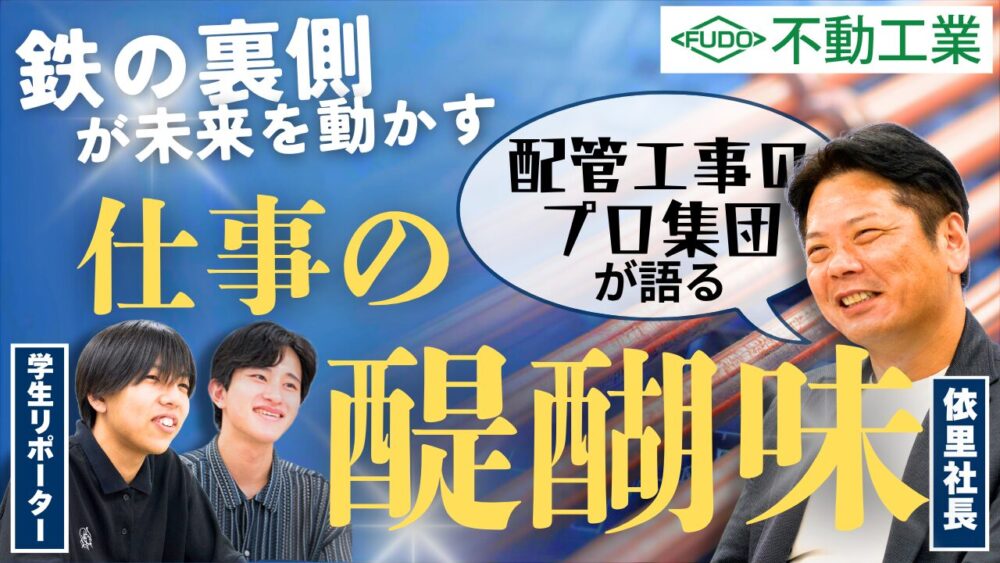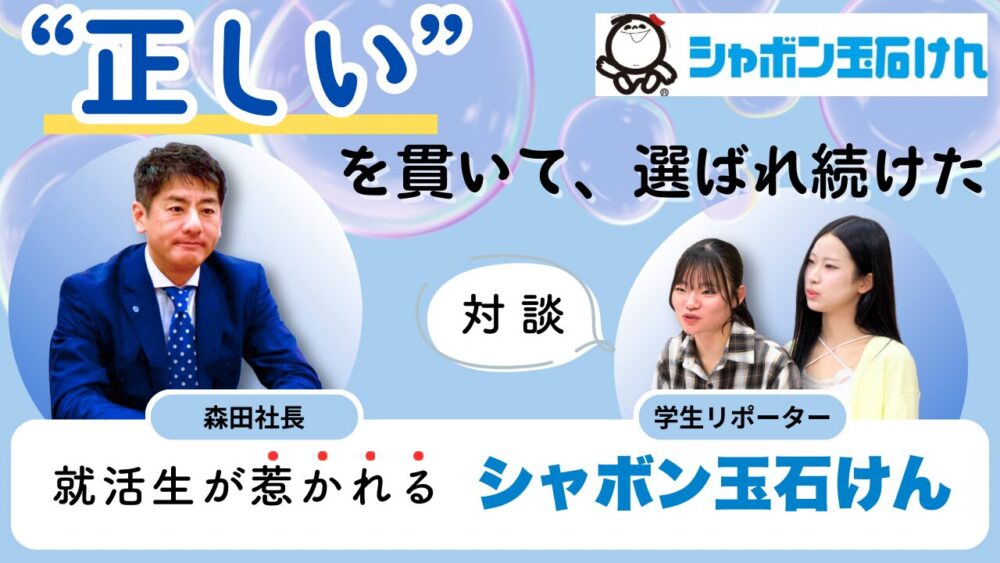陸の上からはじまる、水産業
海じゃなくても、魚は育つ
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日経ヴェリタスの記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
魚って、やっぱり「海で泳いでいるもの」だと考えますよね。ところが最近、「陸の上」で魚を育てる動きがじわりじわりと広がっているらしいんです。まるで畑で野菜を育てるみたいに、ビルや倉庫の一角に大きな水槽を置いて魚を養殖する。そんな光景が、近い将来ふつうに見られるかもしれない。
記事によれば、日本の水産資源はいま大きな岐路に立っているそうです。水揚げ量が落ち込み、漁港にはかつてのにぎわいが戻らない。海面養殖も限界がある。だけど「魚を食べる文化」は、日本人のアイデンティティみたいなところもあって、そう簡単に手放せない。どうする? そこで登場するのが、「陸上養殖」という技術です。
ぼくはこれを知ったとき、「魚は海で獲るもの」という思い込みがバリバリにあったんだと気づきました。でも、よく考えてみれば、陸上養殖なら海の環境変化や乱獲の影響を受けにくいし、AIやIoTを使った水質管理やエサやりが可能になる。さらに、土地さえ確保できれば新しい人や企業も参入しやすい。これはなにか、大きな転換点なんじゃないかと思うんです。
いま、魚が減ってきているというリアル
ここ数年、さんまやイカが不漁だって騒がれたのは記憶に新しいですよね。価格がグッと上がったり、「昔はどこでも安く食べられたのに」って嘆く声を聞いたり。ひとつの原因は、地球温暖化などで魚が回遊するルートが変わったり、世界的に漁獲圧が強まったりと、いろんな要因が重なっているそうなんです。
日本近海でも、海水温が上がると、魚が南から北へ移動しはじめる。外国船が日本のすぐ近くまで来て、大量に漁をする――なんて状況もあるみたい。世界全体の漁獲量は頭打ちで、記事によれば2000年比で2022年は2.5%減少しているとか。こういう話は、どこか遠い国の問題のようで、実はじわじわと日本の食卓をむしばんでいるんです。
日本の自給率と「陸」からの挑戦
かつては魚介類の自給率が100%を超えていた時代もあったらしいんですよ。それこそ「魚なら日本の海にいくらでもいるだろう」みたいな感覚。でもいまは50%台まで落ち込んでしまった。そもそも魚を育てる養殖といっても、海面養殖には漁業権のハードルがあるし、沿岸部の適地も限られている。そこで、海ではなく陸の上で“魚を育てる”っていう発想が浮かんでくるわけです。
陸の上なら、必要なのは海水を循環させるシステムと、水槽を置くためのスペース。AIが水質や水温、酸素量をモニタリングして、魚に最適な環境をキープしてくれる。大手企業が参入すれば投資も大きいから、大規模設備を作って生産性をガツンと上げられる――なんて話も現実味を帯びてきました。
もちろん最初は小規模な試験的養殖からスタートするでしょうけど、うまくいけば「生け簀を陸上に持ってくる」イメージですね。これまでは漁船に揺られて沖まで行き、潮や天候に左右される毎日だった漁師さんたちも、もしかすると「最先端の管理システムを扱うオペレーター」になるかもしれない。そんな変化が起こる可能性がある。

魚にテクノロジー、意外と合うかも
就活と聞くと、真っ先に浮かぶのは大企業のオフィスワークとか、ITベンチャーのエンジニアとか、そんなイメージかもしれない。でもね、「魚を育てる仕事」も、いまどきAIやIoT、ビッグデータ分析といった先端技術の宝庫になりつつあるんですよ。
なんせ、魚が何匹いるか、どのタイミングでエサをやるか、水質が変わったらどう対処するか――全部モニタリングした上で最適化するのは、かなり難易度の高いシステム設計ですよね。それこそ、ゲーム感覚で「魚の健康を管理する」ことになるかもしれない。まるでファンタジーの世界でドラゴンを育てるかのように、魚を自分たちの手でコントロールしていくんです。
一方、「海で漁をするのが漁業だ」という伝統的な考え方も根強いです。そこには長年のノウハウや職人気質があって、むやみに新技術を導入するだけじゃうまくいかない場面もあるかもしれない。でも、だからこそ、伝統を守りながら新しい知見を取り入れる“架け橋”になれる人がいると、面白い化学反応が起きるんじゃないかと思うんです。
未来の食卓と「安全保障」
記事によると、国は「2032年度までに、魚介類の自給率を94%にしたい」という目標を掲げているそうです。いまの50%台から一気に上げるというのは、正直なかなか大変です。でも、これはただの数字というより、「日本はこれからも魚を食べ続けたいし、自分たちで確保できる体制を整えたい」という意志の表れじゃないかと。
いまや食料の自給は、安全保障の一部とも言われるようになりました。「日本食といえば魚」なんて世界中に知られているのに、気づいたら魚の多くを輸入に頼っている――というのは、ちょっと寂しい。だったら、陸上養殖であれ海面養殖であれ、自分たちの国で魚を育て、食卓に載せる術を拡大していこう、というわけです。
想像してみましょう。駅前のビルの屋上でブリを泳がせていて、エレベーターで地下の鮮魚店へ直行させるなんてこともできるかもしれない。物流コストも抑えられて、何より新鮮。気軽に手に入れられるとなれば、魚離れなんて言葉も過去のものになりそうです。
ゆくゆくは魚と「共生」していく感じ?
ぼくは子どものころ、海釣りに行くと釣れた魚を持って帰って、刺し身にしてもらうのが楽しみでした。海で生きていた魚を、その日のうちに自分で釣って食べる――あのワクワクした気分は、いまでも忘れられません。
陸上養殖なら、自然界の激しい変動に左右されにくい分、しっかりした管理のもとで魚を育てられる。しかも、環境に合わせた養殖方法が確立できれば、自然の海への負担も減るかもしれない。新しいテクノロジーの力で、「食べるために魚を育てる」こと自体が自然への配慮にもつながる、そんな可能性だってあるんです。
ちょっと立ち止まって考える
就活生のみんなにとっては、「水産業」と聞いただけで敬遠する人もいるかもしれません。だけど、いまこの瞬間にも、大企業やベンチャーがこぞって陸上養殖に注目している状況を見ると、実は“旬な業界”とも言えるんじゃないでしょうか。
自分は文系だから、理系だから、ITが得意だから――そんな区切りで考えるより、「食べる」ことや「自然と共存する」ことに興味があるなら、一度は覗いてみる価値があるかもしれないんです。AIやIoTのスキルを生かしながら、日本の新しい食文化の形を創り出す。そう考えたら、すごくエキサイティングじゃないですか。
ぼく自身、夜にお寿司を食べながら「この魚はどこで獲れたのかな」と思うことがあります。もし陸上養殖が一般的になったら、「実はこのブリ、隣の街のプラントで育ったんだよ」なんて言葉が交わされるかもしれない。きっと食べる体験そのものが、どこか“身近”に変わるんだろうなあ。
さいごに
海じゃなくても、魚は育つ。なんだか不思議だけど、よく考えれば人間が野菜や果物を品種改良して、おいしく、安全に育てているのと同じ延長線上にある話ですよね。そこに最先端のテクノロジーが混ざると、水産業はこの先どんなふうに変わっていくんでしょうか。
海の大自然から離れた場所で魚を育てることに、まだちょっとした違和感も覚えます。でも同時に、「魚を一生懸命育てる人が増えるかもしれない」という未来は、どこか優しい響きがある。人間と魚の距離が縮まったら、もっと豊かな食卓になるんじゃないか――そんな想像が膨らむんです。
就活生も、社会人も、「食にまつわる仕事」には可能性がたっぷり詰まっています。もしあなたの心がちょっとだけピクッと反応したなら、水産業に思いきって飛び込んでみるのも悪くないかもしれません。
Vamos学生メンバー募集
もし「もっといろんな企業のリアルな話を聞きたい」「直接インタビューで学びたい」と思ったら、ぜひVamosの活動に参加してみましょう。先輩たちの体験談をリンクから覗いてみると、きっとガクチカ(学生時代の活動実績)にもつながるヒントが見つかるはず。参加したい方は、Vamos公式LINEに「説明会参加希望」と送るだけで大丈夫です!

Vamos公式LINEはこちら