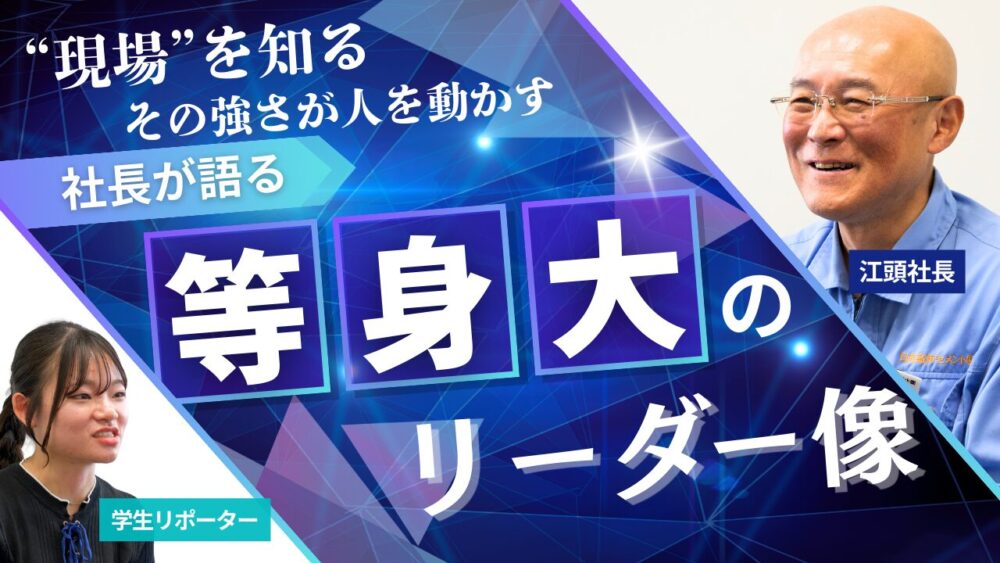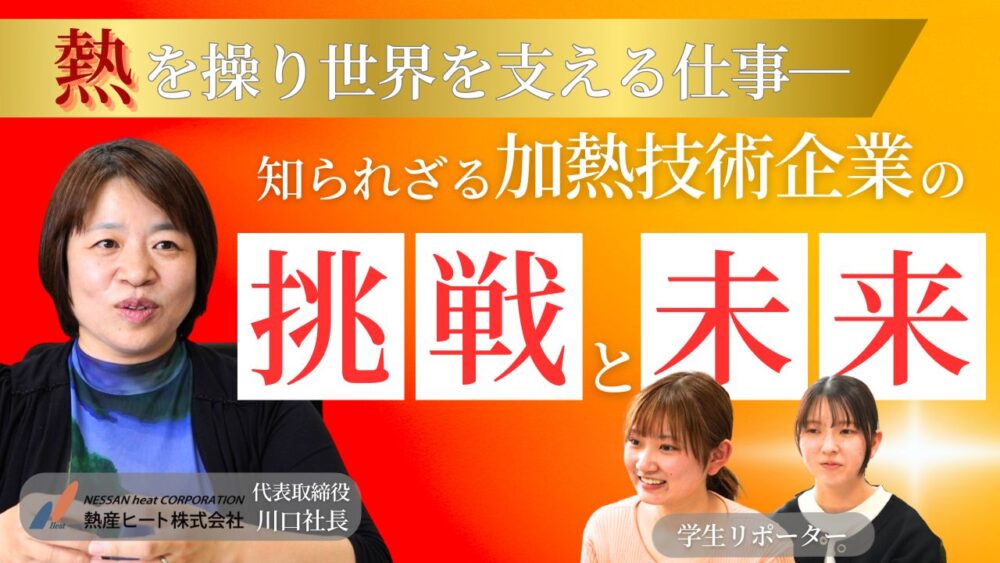北九州市を拠点に、廃棄物処理から再生油製造まで幅広く手がけるサニックスひびき工場。かつて公害の地として環境問題に苦しんだ北九州市が、“環境モデル都市”へと変貌を遂げたように、サニックスも「次世代へ快適な環境を」を企業理念に、環境問題を解決する仕事をしています。今回、私たちは宗政社長にお話を伺い、廃棄物を資源化する技術や、微生物が主役となる廃液処理工程など、多面的な事業領域を垣間見ることができました。“現場主義”や“困りごとを解決する”企業文化とは、いったいどのようなものなのでしょうか? インタビューを通じて見えてきたサニックスの魅力を、じっくりご紹介します。

1.廃棄物が生む新エネルギーの魅力と可能性
「当社の環境ビジネスについて、少し説明しますね。①シロアリ防除や給排水管の保全などの住環境メンテナンス事業、②太陽光発電などのエネルギー事業、③産業廃棄物の処理・リサイクル事業、主にこの3つの事業を展開しています。ここひびき工場は、3つ目の廃棄物処理・リサイクルを行う部門のひとつ。廃液を浄化処理する工場です。今は、廃液の浄化だけでなく、飲食店などから排出されるグリストラップ汚泥を燃料としてリサイクルする仕事も行っています。」
※グリストラップ…飲食店の厨房などから出る油や残飯を、排水と分離する仕組み。
「私、大学時代に飲食店でアルバイトをしていましたが、グリストラップの掃除って大変でした…。あれって実際にどこへ行くのか疑問でした。」
「専門業者が定期的に回収します。サニックスでは、その回収物を受け入れて処理しているんですよ。」
「油って、冷えると固まってしまうし、生ゴミと混ざるととても臭くなるイメージがありました…。それでも再利用できるんですか?」
「ええ。最初は油にゴミや水分が混ざった状態ですが、油分のみを分離抽出する技術を開発し、“再生油Bio”と呼ぶ燃料を製造しています。重油の代替燃料として販売しています。」
「再生バイオ燃料…いわゆる“ゴミ”から作られるとは驚きです。実用化までの道のりは大変だったのでは?」
「2018年頃から本格的に取り組み始めました。油分だけを分離する方法を試行錯誤しながら確立しましたが、製品ができた当初は、あまり世間に認知されていなかったこともあって、評価されにくかったですね。ところが、2021年に「北九州エコプレミアム」に選定されたことをきっかけに、認知度が上昇。また、SDGsやCO2排出削減が重要視されるようになったことや、原油価格高騰で化石燃料のコストが上昇していることもあって、企業が代替エネルギーを探す動きが加速しました。そうした追い風も受け、徐々に引き合いが増えてきたんです。」
「なるほど。CO2削減だけじゃなく、コストダウンにも直結する可能性があると。」
「そうです。さらに“廃棄物を捨てる”だけよりも、“新たな価値に変える”ほうが企業としてもイメージアップにつながりますよね。化石燃料に代わるエネルギー源として、企業のPRにも使われるケースが増えています。」
【重油とのコスト比較とビジネスモデル】
「燃料として使えるようになるまで、結構手間がかかりそうですが、なぜ安く提供できるんでしょう?」
「廃棄物は処理費をいただいて受け入れています。つまり、原料代がかからないということです。それで、石油由来の燃料よりも安く提供できるわけです。」
「なるほど。処理委託費と燃料販売が両輪になっているわけですね。“サステナブル”への関心が高まっている今、時代の後押しもありそうです。」
「おっしゃる通りです。廃棄物の再資源化は、単なる廃棄物処理から“エネルギービジネス”へとシフトしており、今後さらに発展の余地があると感じています。」
2.微生物が主役!? 24時間稼働の巨大プラントの裏側
「廃棄物から燃料を作るのに、具体的にはどうやってつくっているんですか? 」
「廃液を微生物で浄化するのが、この工場のもともとの仕事なんですが、飲食店などから出る廃液は、動植物性の油脂分が含まれていて、そのほとんどが、常温ではバターのような固体で、汚泥や廃水などを取り込んだ状態。このような油が混じった廃液は微生物処理ができないため、先に取り除きます。従来、ただ取り除いて処分していただけだった油混じりの汚泥や廃液を、油とそれ以外に分離する技術を開発した。それで生まれたのが、再生油Bioです」
【工場見学を通じて学生が得る気づき】
「実際に工場見学をすると、そのスケールに圧倒されました。廃液を処理する大きなタンクや配管、廃液を微生物で浄化する設備など、想像を超える施設でした。」
「ええ、皆さんも驚かれます。『こんなにたくさんの人が携わっているんだ』とか、『廃油がこんなふうにして燃料になるんだ』と実感してもらえる。特に環境やバイオ技術を学ぶ学生さんにはとても刺激的な現場だと思いますよ。」

3.海外展開と“日本の綺麗さ”:社長の現場主義とグローバルビジョン
「日本国内だけでなく、海外からも廃液処理の技術相談を受けたと聞きました。実際にどんな国からの依頼だったのでしょうか?」
「東南アジアなど、まだ法整備が十分でない地域ですね。大都市でも排水を適切に処理するインフラが追いついていないケースが多く、河川にそのまま垂れ流してしまっている状況もあるんです。そういう地域から廃液処理に関する相談を受けたこともあります。
「日本は公害を早い段階で経験した分、ノウハウが蓄積されているんですよね。北九州市も“公害克服のモデルケース”ですし、その実績を持つ企業に学びたいというニーズがあるのかなと感じます。」
「北九州市は国際的に見ても“公害を克服した都市”として知られているので、視察ツアーが頻繁に組まれていて、その際に当社の工場を見学し、『こういう形で微生物処理を行っているのか』とか、『再生燃料の精製工程はどうなっているのか』と興味を持ってもらえるわけですね。」
【社長のエピソード:現場主義と海外への視野】
「先ほど他の社員の方に話を聞いたのですが、社長が、休日に突然工場に現れてトイレ掃除をしたというエピソードが印象的でした。そういう“現場を大事にする”姿勢が、経営にも活かされているのでしょうか?」
「そうですね。私はとにかく“自分の目で見る”タイプです。トップダウンでやれと言うのではなく、実際に工場や設備を見て問題点を探す。廃油の再生バイオ燃料のアイデアも『臭くてどうしようもないものほど、実は価値があるんじゃないか』という現場でのひらめきから生まれています。海外でも“日本の清潔さ”を見せることで、新たなビジネスチャンスや貢献ができると考えているんです。」
「国内外の高校生のスポーツ大会に協賛し、来日した海外の高校生に、日本の「きれいさ」「清潔さ」を肌で感じてもらう取り組みもされているとか?」
「ええ。ラグビーやサッカー、柔道など、さまざまな大会を通じて海外の若い人が福岡県(宗像市)に来て、競技だけでなく、お互いの文化を理解し合います。それと同時に、日本のきれいさ、清潔さを体験してもらうことにも意義があると考えています。地道かもしれませんが、そうした経験が、将来にわたる環境意識の向上にもつながるのではないかと 。」

4.“お困りごと”がビジネスを拡大する:サニックスの歴史と社長の執念
「サニックスさんは、もともとは住宅のシロアリ駆除などの住宅のメンテナンス事業から始まったそうですね。そこからどうやって廃棄物処理へと広がっていったのでしょうか?」
「最初は一般家庭のシロアリ対策や害虫駆除など、“家を守る”サービスがメインでした。そこから、飲食店や病院などの衛生管理へと事業が広がりました。そして現場でお客様の話を聞いていると、『実は病院の廃棄物処理に困っている』など、まったく別の困りごとが耳に入ってくるんです。」
「なるほど。そこで“それなら我々がやってみましょう”という姿勢になったんですか?」
「そうですね。廃棄物処理は“汚い”という後ろ向きのイメージが強いかもしれませが、“お困りごとを解決する”という当社の基本スタンスがあったので、医療系廃棄物を含む、産業廃棄物の中間処理(焼却)事業に乗り出しました。そこが大きな転機になり、リサイクル事業へと広がっていったのです。」
【プラスチック発電や廃油リサイクルへの挑戦】
「プラスチックは埋め立てられることが多かったと聞きますが、燃やせば燃料になるんですよね?」
「そうなんです。プラスチックはもともと石油由来ですから、燃やせば高いエネルギーが出る。埋め立てるよりも、発電などエネルギー回収をしたほうが有効ですよね。そこに着目して“廃プラスチック由来の燃料による発電”を事業化しました。当社では『資源循環型発電』と呼んでいます。一方で、廃液処理においても、『廃油から燃料は作れないか?』という話になって今に至るわけです。」
「廃油こそ、悪臭や汚れがひどくて扱いづらい印象がありますね。」
「そうですね。最初、社員たちは『そんな臭いもの誰も使わないでしょう』と否定的でした(笑)。でも“カロリーがあるから、燃やすことができる。必ず需要はある”と信じて、他社の似たような取り組み事例を探したり、実験を繰り返したりして、再生油Bioとして製品化できたんです。」
【社長のエピソード:お酒の醸造所を黒字化した“糖質ゼロ”戦略】
「社長の今までの経歴も教えていただけますか?」
「色々やってきましたね。お酒の醸造所で“糖質ゼロ”を打ち出して赤字を黒字にした時のことはその後のビジネス感覚にも影響を与えています。」
「どういった内容だったんですか?」
「関連の酒造会社で働いていたんですよ。でもあまり売れなくて、どうしたもんかなと悩んでいたんですが、やっぱり現場に行かないとわからないと思い、販売してくれているスーパーに行きました。そこで販売するために売り場に立たせてほしいとお願いしたんです。しばらく立っていると、お客さんが「糖質ゼロ」と表示した商品をよく手に取られていることに気づきました。実は、焼酎はすべて糖質ゼロなんですけど、どの商品にも貼っていないですし、みんな知らないですよね?」
「知らなかったです!」
「そうでしょう?だからお客様に『糖質ゼロですよ!』と声がけをしたら売れるようになったんですよ。そこからPOPやデザインにもちゃんと入れるようにしていって焼酎の売上が一気に変わったんです。それ以来、自分もそうですが、よく社員にも『自分で現場を見て、どうやったら売れるか考えろ』と伝えています。」
「なるほど!“困りごと”や“埋もれている強み”に着目してビジネスを拡大するスキルは、サニックスの廃棄物リサイクル事業にも通じるものがありますね。」
「まったく同じですね。“手をつけていない問題”ほど実は大きな需要がある。その視点を持ち、先入観にとらわれずに挑戦することがサニックスの企業文化になっているんだと思います。」

5.人材育成と「前向き」の精神:社員が創る“快適な環境”の未来
「サニックスさんのホームページを拝見すると、人材育成にも相当力を入れている印象を受けました。特に“自分で考えて動く経験を重視する”とありましたが、どんなプログラムになっているんでしょう?」
「まず入社したら、2週間ほどの研修で、当社がどんな事業をしているのかを肌で感じてもらいます。その後も定期研修はあるんですが、最近はとくに“自分で気づいたことを自分で改善してみる”という体験を積んでもらいたいんですね。」
【座談会スタイルの意見交換:部署を超えたコミュニケーション】
「会社をよくしていくために考えられていることはありますか?」
「私自身『やろうと思って、本来で取り組んだらどうにかなる』と思っていて、社員にもそのことをわかってほしいなといつも思っています。みんながやれるようになっていけばいいなと。だって楽しいはずなんですよね。自分が『こうしたいからやってみる!』と突き進んで思うように進んだら。そういう場所や経験ができる場所を作って行きたいですね。」
「何か具体的に取り組まれているんですか?」
「そういった思いから、社員3人ずつくらいを集めて、“自分が思う快適な環境”について、大きい小さいは関係なく話してもらう座談会を昨年から開いています。例えば小さいものだと、お手洗いの流しのところが濡れていて嫌だなと感じたから、スポンジを用意してすぐに掃除ができる環境を作ろうとか。本当に小さくてもいいのでまずは半年くらい、自分がやろうと思ったことを継続して続けてみてほしいですし、みんなが思う快適な環境に少しずつでもなっていけばいいなと思って、座談会を続けています。」
学生
「社長自らが毎回座談会に参加されているんですか?」
「そうですね。社員が2000人くらいいるので、まだ全員とは話せていませんが、今まで300人くらいと話しました。あと数年はかかりそうです。」『あなたが考える快適な環境とは』っていう題材で、各自、意見を出します。”部門を超えてレクレーションをやりたい”とか、“人事制度を見直す必要があるのでは?”といった大きな提案が出たりとかいろいろ出ますよ。座談会で出た意見は、前向きに話し合っていますし、私もいろんな意見が聞けて新鮮ですね。」
学生
「すごいですね!そんな取り組み初めて聞きました!その提案が実際に採用されることもあるんですか?」
「はい。例えば『健康のためにバランスボールに座って仕事をしたい』という声がありました。私も意見を聞いて『はい、いいですよ』ではなく、『じゃあ自分で取り組んで進めてみて』と、自分で実現させるように促しました。上司に許可を取って、まずは部内で始めたようですが、それを他部署の人が見て、「私も」「私も」と徐々に、いろいろな部署に広がりました。 “ちょっとやってみようか”というチャレンジ精神が、うちの社風ですから(笑)。試してみてダメなら別の方法を考えればいい。そんな気軽さが、良い意味で社内に浸透していると思います。」
【教育参観や子どもとの交流:次世代へのメッセージ】
学生
「ホームページには“教育参観”という言葉もありました。社員の子どもたちにも参加してもらう行事があるんですか?」
「子どもたちに“親がどんな仕事をしているのか”を伝える場を作り、彼らにも“環境”や“SDGs”に興味を持ってもらおうという狙いがあります。自分の親の働く姿を知ることで、家族の会話も増えるでしょうし、『汚れたものをきれいにしているお仕事』として理解してもらえれば嬉しいですよね。」
学生
「親子で環境への意識が高まると、子どもたちが将来“環境問題を解決したい”と志すきっかけになるかもしれませんね。企業が教育に関わるのは素敵な取り組みだと思います。」
「まさにそこがポイントです。廃棄物処理には、社会を支える大事な役割がある。それを身近に感じて、次世代が“汚れたものをきれいにして、新しい価値を作る”という面白さに気づいてくれたら嬉しいですね。」
【就活生へのメッセージ:とにかく“前向き”に】
学生
「たくさんのお話ありがとうございます!最後に、就活生へメッセージをお願いします。」
「“前向き”であることが何より大切だと思います。やってみれば失敗もあるでしょうけど、その過程で学べることは大きい。世の中には解決されていない課題がたくさん転がっていて、それをどうやって形にするか。就活だって同じです。企業をたくさん見て、直接話を聞いて、自分が面白いと思える道を探してほしいですね。」
学生
「私も環境ビジネスやバイオ技術の世界に興味を持っていましたが、今回の取材でますます関心が高まりました。ここまでお話を伺えて本当に良かったです。」
学生
「改めて、本日は貴重なお話をありがとうございました。廃棄物処理から再生バイオ燃料まで、想像以上に幅広い分野をカバーされていて本当に勉強になりました。」
学生
「環境ビジネスと聞くと“クリーンエネルギー”ばかりを想像していましたが、こうして地道な廃棄物処理が社会を支えていると知ると、むしろそちらの方が本質的な仕事に感じました。ぜひ視野に入れて、今後の就活にも役立てたいです!」
「そう言っていただけると嬉しいです。技術的な面はもちろんですが、一番大事なのは“困っている人を助けたい”という思いだと思います。私たちの仕事は、社会のどこかで誰かが困っている現実と向き合うこと。そこにこそやりがいがあります。就職活動も頑張ってください。皆さんの将来を応援しています!」
学生
「はい!今日は、本当にありがとうございました!」

北九州市が歩んだ公害克服の道と同じように、「汚いところをきれいにする。不潔なところを清潔にする」という精神で成長してきたサニックス。その原動力は、目の前の“困っている人”をどう助けるかを最優先に考える姿勢と、常に“現場”に寄り添う行動力にあるようです。
廃棄物の処理、再生油Bioをはじめとする新エネルギーの創出、そして社員の自主性を引き出すユニークなプログラム――どれもが社会に求められる役割を担ってきました。廃棄物処理が単なる“地味な仕事”ではなく、地球の未来を支える重要な事業であることを実感できました。