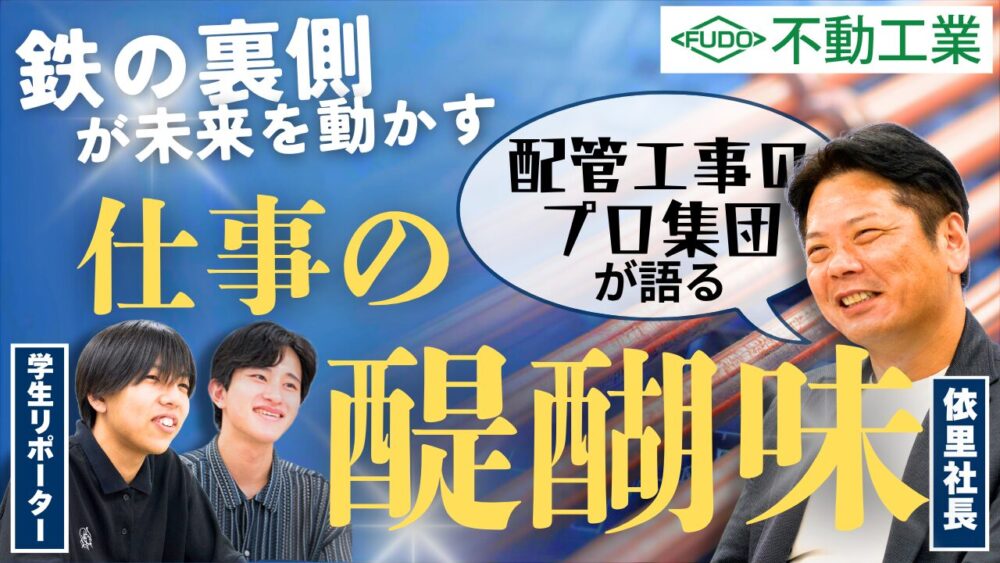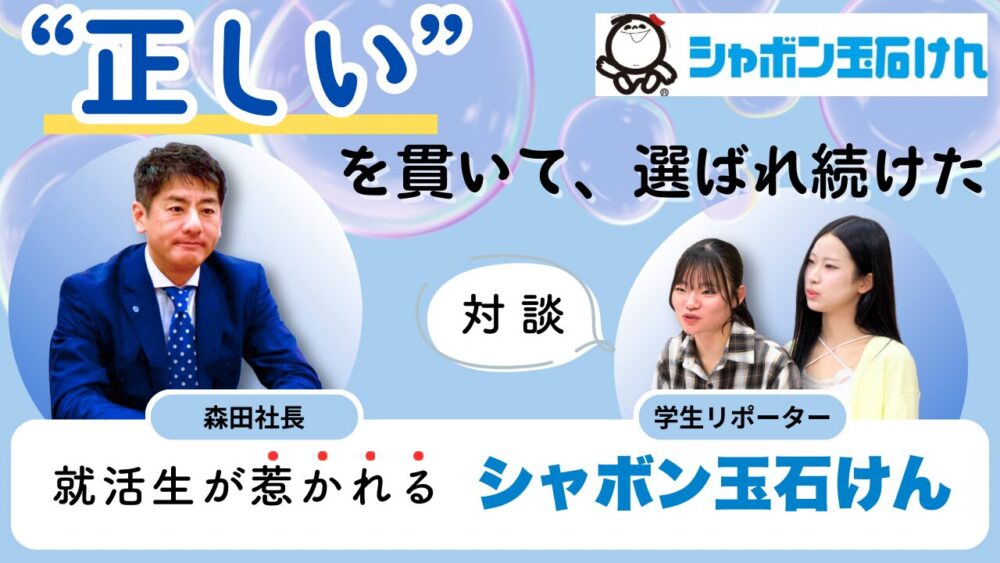うるる 埋もれた時間が未来を変える
「埋蔵労働力資産」が語る新時代
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日経MJの記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
日経新聞に掲載された、在宅ワーカー向けクラウドソーシング事業を行う「うるる」が発表した“埋蔵労働力資産”。なかなか働けない人や今後AIなどで代替される仕事を、いまは眠っている“潜在的な労働力”として数値化したというお話です。
その推計によると、現在の日本には15兆円分もの「働きたくても十分に働けない人の時間」が埋まっている。そしてこれから技術革新が進むと、さらに120兆円分もの「AIが代わりにやってくれるからこそ生まれるヒマ」ができる――そんな見通しが示されています。
僕らの生活のそばにある膨大な時間。ふだん意識しないけれど、よくよく考えてみると、世の中の変化と人間の時間は背中合わせに存在しているのかもしれません。この記事は、その時間を「ただのヒマ」ではなく「価値のある資産」と呼ぶことで、新しい働き方や社会の可能性を示してくれます。
「埋蔵労働力資産」や専門用語をやさしく解説
埋蔵労働力資産ってなに?
「埋蔵労働力資産」という言葉は、直接的にはあまり耳なじみがないかもしれません。これは、「働く意欲や能力がありながら、家庭や介護などさまざまな事情で希望通りに働けていない人の余っている時間」や、「AIやITが代替してくれることで浮かび上がってくる余裕の時間」を合計したものです。働き手不足が叫ばれる日本において、こうした隠れた労働力をどう活かすかが大きなカギになっています。
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)って?
記事中で登場するBPOは、企業の間接的な業務(経理事務や採用業務など)を外部の専門企業に委託すること。昔から存在はしていたものの、今のAI技術やクラウドソーシングと合わさることで、劇的にその形が広がりつつあるそうです。「苦手な作業を得意な人や機械にまかせてしまおう」という発想が、さらに高まっているわけですね。

数字の裏から見えてくる時代背景
ある人にとっては「まとまった時間をどう使うか?」が新たな課題になり、別の人には「専門性を活かして仕事の一部を受注する」チャンスが生まれています。さらに技術革新が進めば、自分の仕事を「ロボットやAIに置き換えられるかもしれない」という不安を抱く人もいるでしょう。
けれど、この記事が教えてくれるのは「時間が生まれること=一方的な不幸」ではないということです。仕事の分担が変わるだけでなく、新しい仕事やサービスが続々と生まれ、人が持つクリエイティビティや“人間らしさ”がもっと必要とされる可能性も大いにある。言い換えれば「自分の時間を、どんなふうに活かすか」が、よりいっそう問われる時代が来る、というわけです。
埋もれた可能性と、これから
たとえば育児中の親御さんが、数時間だけ子どもを預けて自宅で働く。あるいは定年後にインターネットを使って、好きな分野の仕事を受注する。こうした未来の断片が、すでにそこかしこで始まっている。そこには、人にしかできない仕事が見え隠れし、機械が効率を高めてくれる分、人間はもう少しゆとりを手にすることができるかもしれません。
もちろん、そのためには社会のしくみや制度がもっと整う必要があります。この記事でうるるの取締役が強調しているように「多様な働き方に対応した制度を拡充すべきだ」という声は、近い将来さらに大きくなっていくでしょう。
僕らが「埋蔵労働力資産」というキーワードを意識するとき、それは“無駄に見えた時間を、大切な資源に変える”という考え方を思い出すことでもあります。時間は、気づかれるのを待っている。見過ごされているだけで、そこには大きな可能性が眠っている――そんなふうに思えてきます。
Vamos学生メンバー募集
Vamosのメンバーになって、いろいろな企業にインタビューしながら自分なりの業界研究を深めてみませんか? 多くの学生が参加しており、リアルな体験談もたくさんシェアされています。興味がある方は、下記リンクで参加者の声をチェックしてみてくださいね。参加希望の場合は、以下のVamos公式LINEへ「説明会参加希望」とメッセージするだけでOKです!

Vamos公式LINEはこちら