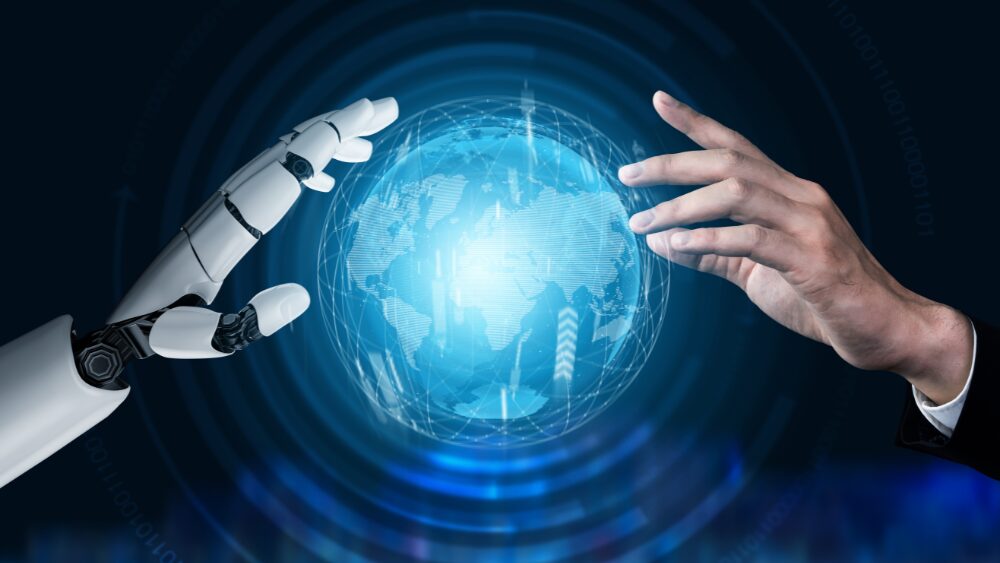サムスンから読み解く家電の次なるステージ
サムスンAI家電「1~3月増収減益」の背景
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
サムスン電子が発表した2025年1~3月期の業績は、売上高の伸びこそ好調だったものの、営業利益は前年同期比ほぼ横ばいとなりました。その理由のひとつとして、世界的な半導体不況に直面し、さらにスマートフォンやテレビ、家電を含む「DX部門」においても採算性が落ち込んでいたことが指摘されています。
そこでサムスンが注力しているのが「AI搭載家電」です。冷蔵庫やエアコンにAIを搭載し、ユーザーが自然に話しかけると温度やレシピを提案してくれる――そんな“会話型家電”を広げることで、高付加価値を実現しようという狙いが垣間見えます。
「生成AI」と「Bixby」をやさしく解説
家電に組み込まれるAIのなかでも、最近特によく耳にするのが「生成AI(Generative AI)」です。これは大量のデータを学習し、新たな文章や画像、反応などを生成する高度な技術を指します。たとえば「今日は暑いから涼しくしてほしい」と話しかけると、それを文脈ごとに理解し、エアコンを自動設定してくれるわけです。
一方、サムスンが独自に開発・強化を進めているのが「Bixby(ビックスビー)」というAIプラットフォーム。スマートフォンやテレビだけでなく、冷蔵庫や洗濯機などにも搭載することで、利用者との“会話”をベースに操作を行うことが可能になります。これにより、従来はリモコンやボタン操作が必要だった場面が、音声だけで進むようになるのです。
家電を中心に見る時代の変化
このAI家電の広がりは、単なる新技術の導入にとどまりません。そこには「会話型インターフェース」へ移行する時代背景が大きく影響していると考えられます。スマートフォンに話しかけて情報を得るのはもはや当たり前。さらに家の設備や家具などもネットワークでつながり、暮らしとテクノロジーの境界がどんどんあいまいになってきています。
サムスンはそうした流れを背景に、AI家電を3倍に増やして巻き返しを図る戦略を打ち出しました。半導体の不振を早期にカバーできない状況だからこそ、利用者の心をキャッチして収益性を高める“次の柱”が必要なのでしょう。新たにイタリア出身のデザイン責任者を迎えるなど、外部人材を取り入れて組織体制を強化する姿勢も、世界の消費者に向けた魅力づくりに本腰を入れ始めた証といえます。

会話が生む新しい可能性
人は長いあいだ、“道具”を使うために手や指先で操作してきました。しかし、AIによって「声」でつながり、「気持ち」を理解してくれる家電が増えると、道具との関係が変わってくるように思います。そこには製品を超えて、生活スタイルそのものをデザインし直す可能性が広がっているのです。
また、関税の問題や原材料高など、グローバルな経営環境の変化はサムスンをはじめ各社にとって大きなハードルです。その中でどれだけ柔軟にリスク分散を図り、デザインや技術革新でユーザーの生活価値を高められるかが、今後の勝敗を分けるのでしょう。
亡くなった前トップの構想を受け継ぎながら、サムスンは「会話できる家電」を広めようとしています。これは同社だけでなく、あらゆるメーカーがAIを活用して暮らしをどう変えるかという大きな問いでもあるはず。私たちがごく当たり前に声で“道具”とやりとりし、その“道具”が私たちを深く理解してくれる――そんな未来はもう、すぐそこまで来ているのかもしれません。
Vamos学生メンバー募集
Vamos学生メンバーとして一緒にWebマガジンの運営にチャレンジしてみませんか? Vamosの一員として企業取材を進めていくと、自然と業界研究やマーケティングスキルが身につきます。すでに多くの学生が参加しており、インタビュー経験を就活に活かしている人も多数! 詳しくは参加者の体験談をリンクからご覧くださいね。参加希望は、Vamos公式LINEに「説明会参加希望」と送信するだけです。

Vamos公式LINEはこちら