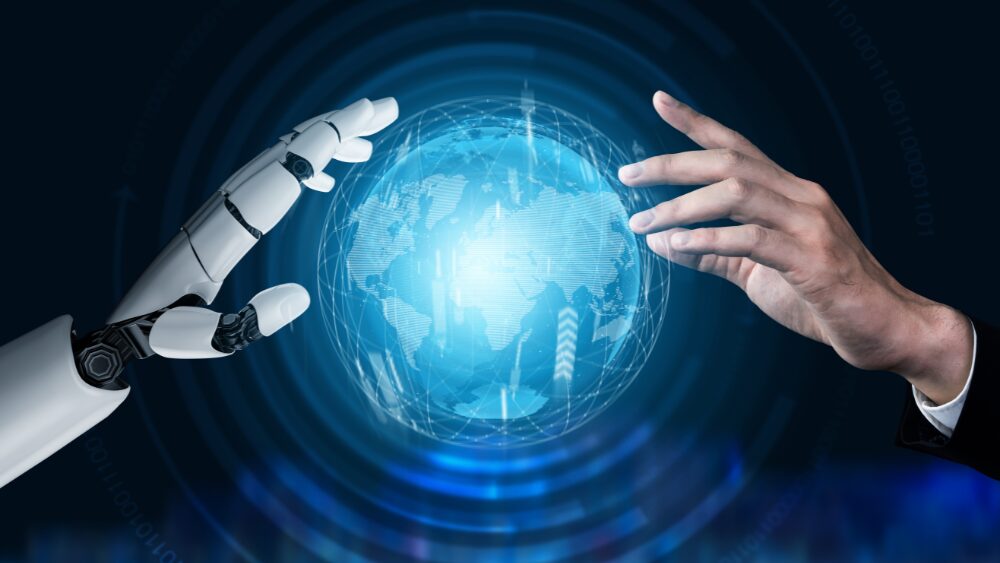アクセルスペース小さな衛星が変える大きな未来
小さな衛星が切り開く新時代
本記事では、著作権の関係上、具体的な内容の詳細な引用は避けつつ、リンク先の記事を参考にして執筆しています。記事の全文をご覧になりたい方は、以下のリンクから原文をご確認ください。
※リンク先は日本経済新聞の記事です。閲覧にはログインが必要な場合があります。
先日、日経新聞で報じられたアクセルスペースの動きが、ちょっとした話題になっています。2026年に小型の地球観測衛星を7基も打ち上げるというのです。小さな衛星を組み合わせて、地上の同じ地点を毎日撮影できるようにする。この動きが、地図や森林監視といった従来の用途を越えて、金融や不動産など新たなフィールドへ踏み出そうとしているとのこと。宇宙の話といえば、映画やロケットの大きな打ち上げなんかを想像しますが、こういう地球観測衛星が、「知る」ためのインフラとして活躍しはじめるのは、まさに“新しい宇宙利用”の形なんじゃないかと思います。
小型地球観測衛星「GRUS-3」の魅力
アクセルスペースが開発する「GRUS-3(グルーススリー)」は、一人暮らし向けの冷蔵庫くらいのサイズしかありません。それでも分解能は約2.2メートルと、地上の物体をかなりはっきり見分けられる性能を持っています。25年夏には米国カリフォルニア州から実証機の打ち上げを予定し、続けて26年に7基を一気に送り出すそうです。現状、2~3日に1回だった撮影頻度が、なんと1日1回になる。1日に230万平方キロメートルを撮影できるということは、日本の国土の6倍にもなるらしい。こう聞くと「宇宙って意外と身近なんだなあ」と実感がわいてきます。
知っておきたい専門用語「分解能」とは?
ここで出てくる「分解能」という専門用語。これは、衛星が地上の物体をどれくらいの大きさまで区別できるかを示す指標です。たとえば分解能2.2メートルなら、2.2メートル四方のサイズのものがなんとなく認識できるイメージ。バスやトラックくらいなら、形として判別できる可能性があるというわけです。
用途拡大の背景にある時代の変化
宇宙から得られる“映像”や“データ”というのは、環境や地図づくりだけに役立つわけではありません。記事によれば金融や不動産、あるいはESG投資なんて分野でも活躍できるそうです。たとえば、鉄鉱石の採掘量や農作物の生育状況など、現地に行かずとも衛星データからおおまかな動きを把握できる。これが商品取引の裏づけや不動産の工事管理に使われれば、投資判断や経済活動全般に新たな透明性がもたらされる可能性があります。もともとレーダーや大きな望遠鏡でしか見られなかったような“地球の状態”を、もっと手軽に、もっと頻繁に観察できる。この背景には、ロケット打ち上げコストの低減や衛星技術の急速な小型化・高度化といった時代の変化があります。
小さなチームが創る大きな挑戦
アクセルスペースは2008年設立で、東大の研究室メンバーによる“手のひらサイズの超小型衛星”からスタートしました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)からの受託開発をこなしつつ、自社で「GRUS-3」を開発・運用するまでに成長しています。大企業が大金を投じて進めるプロジェクトとは違い、少人数のチームが創意工夫で道を切り拓いてきた。その結果、小型衛星で世界初の北極海の海氷観測に成功したり、これまで10基の衛星を無事に打ち上げたりと、実績を積み重ねています。
宇宙利用の未来と私たちの生活
「宇宙ビジネス」なんていうと、まだまだ遠い世界のように思われがちですが、実はこうした地球観測衛星の活躍によって、私たちの暮らしはすぐ足元から変わりつつあります。リスク管理や投資の精度が上がれば、金融業界はより正確な予測と判断が可能になりますし、不動産の工事状況や進捗を定期的に観察できれば、工期の見直しや資金の配分といった調整もスムーズになるでしょう。地球の動きを正確に知ることで、環境問題への取り組みや農作物の収量管理も効率化される。こうしてみると、宇宙の利用は決して特別な人たちだけのものではなく、いつのまにか私たちの日常の一部に入り込んでいるのです。
未来は、遠いところにぽっかり浮かんでいるのではなく、こうした衛星のような小さなステップの集合体として、すぐここにあるような気がします。アクセルスペースの挑戦は、その一つの象徴なのかもしれません。
Vamos学生メンバー募集
Vamosのメンバーになって、いろいろな企業にインタビューしながら自分なりの業界研究を深めてみませんか? 多くの学生が参加しており、リアルな体験談もたくさんシェアされています。興味がある方は、下記リンクで参加者の声をチェックしてみてくださいね。参加希望の場合は、以下のVamos公式LINEへ「説明会参加希望」とメッセージするだけでOKです!

Vamos公式LINEはこちら