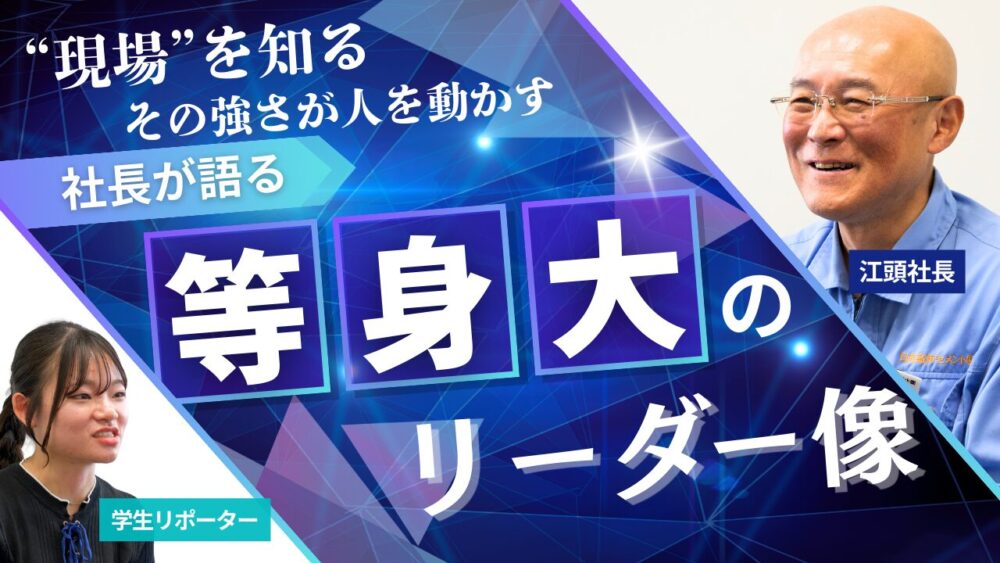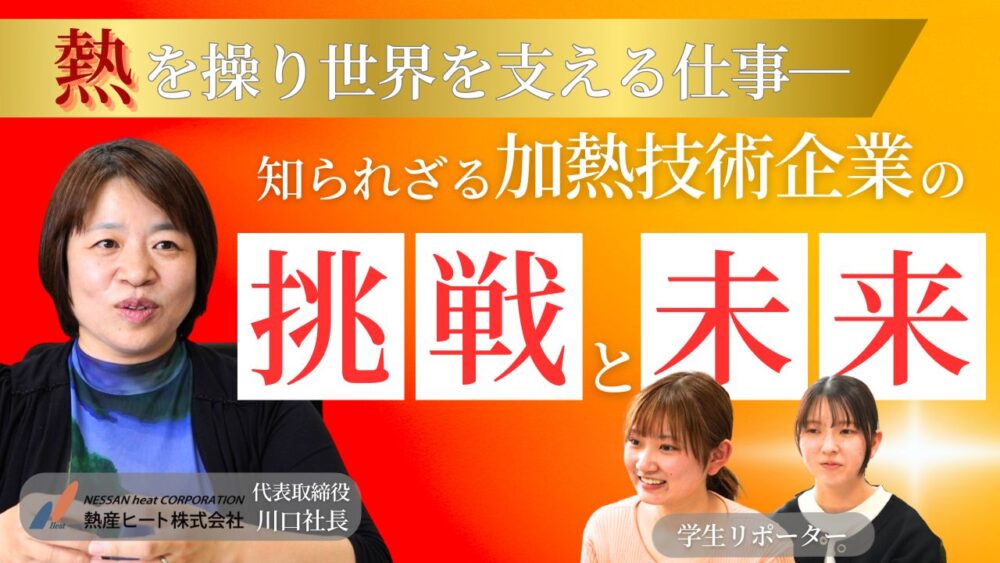「言葉で世界をひとつに!」──そんな大きな志を抱き、北九州という重工業の街であえて“ソフトサービス”の旗を掲げ続けてきた企業があります。それが、多言語通訳や英語教育、国際会議の企画・運営などを展開する株式会社アウルズです。創業からすでに35年以上が経過しているにもかかわらず、その挑戦心は衰えるどころか、ますます活発化していると言っても過言ではありません。海外との太いパイプと豊富な人脈を活かし、“言語”というツールを武器に地域や企業の国際化を後押ししてきたアウルズ。今回、就活応援Webマガジンの学生が実際にアウルズを訪問し、創業者である木下会長へインタビューを行いました。「そもそも北九州で言語サービス?どんな需要があるの?」という疑問から始まった取材でしたが、聞けば聞くほどその可能性に圧倒。あなたもぜひ、この記事を通じて“言葉の力”を再発見してみてください。

1.「アウルズ」とは? 北九州で“言語サービス”を35年以上
1-1. 社名の由来:One World Aimed Language Service
本日は取材の機会をいただき、ありがとうございます。まず、“アウルズ”という社名やロゴの由来がとても気になるのですが、フクロウ(Owl)から付けられたのでしょうか? それとも何か別の意味合いがあるのでしょうか?
今日はようこそいらっしゃいました。私たちは“OWLS”とアルファベット表記にしているのですが、これは One World Aimed Language Service の頭文字を取ったものなんです。直訳すれば“1つの世界を目指す言語サービス”という意味合いになります。重工業のイメージが強い北九州だからこそ、“ソフトサービスで世界とつながる”という思いを込めました。ロゴには知恵の象徴として知られるフクロウをあしらっているんですよ。
なるほど、まさに“言葉で世界をひとつに”という理念が社名に凝縮されているのですね。当時は通訳や翻訳などを主とするサービスは珍しかったと思いますが、周囲からの反応はいかがでしたか?
『本当にそんな事業で成り立つのか?』という声もありましたが、一方で『新しい風を吹き込んでほしい』『ミネルヴァの梟のように知恵を授けてほしい』と応援してくださる方も多かったんです。ちょうどバブル期で国際会議を地方都市に誘致しようという動きも活発でしたし、海外とのやりとりが増えれば言語サポートが不可欠になりますから。その追い風もあって、意外と早い段階でニーズをつかむことができました。
1-2. 「ミネルヴァの梟」になれるか──北九州の新たな可能性
“ミネルヴァの梟”という比喩は哲学的で興味深いですね。とはいえ、北九州といえば“鉄の街”という印象が強いですし、ソフトサービスが根付くイメージがわきにくいのですが……。
おっしゃる通り、当時の北九州は重厚長大産業が街の主力でした。ところが、海外企業との協力や外資の進出が話題になるにつれ、通訳・翻訳のみならず、国際会議を運営できる人材やコーディネート力が求められるようになってきたんです。そうした流れのなかで、私たちが『じゃあ通訳だけでなく、会議全体をプロデュースしましょう』と提案していくうちに、“言語サービス企業”という立ち位置が徐々に確立していきました。
2.創業のきっかけは“市長のひと言”──個人通訳から法人化へ
2-1. 市長の後押し、「とりあえずやってみる!」で一気にスタート
木下会長は市長の通訳を務めていた時期があったそうですね。そこから法人化して会社を立ち上げるまでの経緯をもう少し詳しく教えていただけますか?
私はもともとフリーの通訳者として、市の海外出張や国際会議などのサポートを引き受けていました。当時は国際会議を招致するために市長が海外に頻繁に赴いていましたので、英語ができる人間を同行させたいというニーズが強くあったわけです。そんなある日、市長から『個人でやっているより、法人化してきちんと会社組織として取り組んだほうが可能性も広がるんじゃないか』と言われました。ちょうどバブル経済の時期で、『じゃあ作ってみようか』と勢いよく踏み切ったのがアウルズ設立の始まりですね。
なるほど、時代の勢いもあって、大きな決断を後押ししてくれたわけですね。実際に会社を構えてからは順調だったのでしょうか?
正直、最初はあまり細かい事業計画なんて立てずに『まずやってみよう』という感覚でした。国際会議の企画運営に携わると、通訳だけではなく『海外からスピーカーを呼ぶ』『会場設営を整える』『レセプションを盛り上げる』といった総合的な仕事が必要になります。結果的にそこが強みになったんです。『通訳者がいるだけでなく、会議の企画も進められるなら一緒にやってほしい』という声が広がって、自然に依頼が増えていきました。
2-2. 青年会議所や経営者仲間の応援、「北九州を国際化してくれ」
個人通訳から法人化し、しかもここまで事業を広げられるのは相当な努力があったのではないかと思いますが、一番の理由は何だったのでしょう?
私自身の力というより、市長や青年会議所(JC)などの経営者仲間からのサポートが大きかったです。『英語が得意な人材が必要なんだから、もっと前に出て活動してほしい』『法人になればビジネスとしても発展しやすい』と周囲に後押しされたことで、私も『よし、やってみよう』と腹をくくれました。北九州は見た目は男の街でちょっと硬派なイメージがあるかもしれませんが、実は新しい挑戦を歓迎する土壌があるんですよ。

3.会議運営×英語教育──二本柱で地域を国際化
3-1. 英語教育:プリスクールからALT派遣、大人向け研修まで
アウルズさんは英語教育にも力を入れているとお聞きしました。具体的にはどのような形態で行っているのでしょうか?
私たちの事業は大きく“コンベンション(会議運営)”と“英語教育”の二本柱になっています。そのうち英語教育では、プリスクール、ALT(外国語指導助手)の派遣、大人向け研修、そして英語講師の育成支援など幅広く手掛けているんですよ。2歳から参加できるプリスクールでは、ネイティブ講師と日常的に過ごすことで、自然な形で“音の英語”を身につけられるようカリキュラムを組んでいます。外国人講師は100名以上在籍しているので、小学校や中学校、高校への派遣や、企業の研修などにも柔軟に対応できるんです。
2歳前後から英語に触れられるとなると、やはり聞き取りや発音などは強くなるものでしょうか?
ええ、最初に“音”や“リズム”として英語を取り入れるのは大きいですよね。日本の学校英語は中学から文法を中心に始めて、“読む・書く”を先行することが多い。でも、それだと『文法ばかりで会話ができない』という弊害が生まれがちです。一方で小さいころから“会話優先”で学ぶと、文法は後からでも習得しやすい。自分が実際に使える表現に紐づけて学べるので、理解が深まるんです。何より“英語って楽しい”という感覚を失わないまま育つのが一番大きいですね。
まさに“遊びながら学ぶ”というスタンスなんですね。英語を苦手科目にしない工夫があるのは素敵です。
私自身、社会に出てから本格的に英語を身につけましたが、“使うために学ぶ”ほうが遥かに覚えが早いと痛感しましたからね。ですからプリスクールでも文法を詰め込むのではなく、歌や遊びを通じて“英語が好き”になる環境づくりを大事にしています。
3-2. コンベンション事業:国際会議を丸ごとコーディネート
もう一つの柱である“コンベンション事業”では、具体的にどのような形で国際会議をサポートされているのでしょうか?
国際会議は、単に会場を借りて通訳を配置するだけでは成り立ちません。海外からの要人やスピーカーの招聘(しょうへい)、空港への出迎え、宿泊手配、レセプションの運営など、ありとあらゆる細かい準備が必要です。しかも、バブル期の北九州は『地方都市でも積極的に国際会議を誘致する』という動きが盛んで、“初めて開催する”というケースが多かったんですね。何もない状態からスピーカーの選定や会議の内容作りを行うには、語学力はもちろん、全体のディレクション力や調整力が求められるんです。
それは確かに想像以上に大変そうです。でも、やりがいも相当ありそうですね。
はい、“会議のマネジメント全体を知っている通訳”というのは海外でも高く評価されます。例えばスピーカーを招待するときには、渡航ビザや航空券だけでなく、事前に送付する資料の準備や、会場での注意事項をしっかり伝える必要がある。そうした段取りを一括管理してこそ、スムーズに会議が進行しますし、参加者にとっても『また北九州で会議を開きたい』と思わせる大きなポイントになるんです。
4.海外出張エピソード──「ボス呼んで!」で交渉突破
4-1. リオの地球サミットで表彰があるのに“入れない”!?
木下会長ご自身も世界各地を飛び回ってきたそうですが、特に印象深かった国際会議はどこですか?
何度も海外出張をしましたが、忘れられないのは1992年のリオデジャネイロ地球サミットですね。北九州市が環境対策への取り組みを評価されて、表彰されることが決まっていたのに、現地の会場に入れず大騒動になりました(笑)。会場がとんでもなく広大で、入口の警備も厳しくて、『お前は入れない』と門前払いされてしまったんです。私がいくら英語で説明しても要領を得てもらえず、最終的には『あなたが判断できないなら、ボスを呼んで!!』と頼み込み、1時間ほど粘ってようやく通してもらいました。
本当にドラマのような展開ですね。“ボスを呼べ”が最終手段だったというわけですか。
そうなんです。会場の入り口で警備員と折衝してもラチがあかないことが多々ありますが、“偉い人に直接交渉する”という方法を取るとすんなり通してもらえることがあります。大規模国際会議って想定外のことだらけですけど、それを面白がれるかどうかが大切ですね。私としては“ゲーム感覚”に近い部分もあって、むしろ交渉を楽しんでいました。
4-2. ロサンゼルスやニューヨークでも“想定外”は当たり前
リオだけでなく、ロサンゼルスやニューヨークの日米市長会議など、多方面で活躍されたとお伺いしました。その際もやはりハプニング続きだったのでしょうか?
ロサンゼルスでは、当時の市長が初めて英語のスピーチをする場面があって、ホテルや機内で徹夜の猛特訓をしました。ニューヨークでは、空港の保安検査で爪ヤスリをめぐって没収騒ぎになり、『どうしてもそれは取り上げられたくない』と必死で交渉した結果、封筒に入れて預け荷物に回すことで何とかOKをもらったり(笑)。とにかく国際会議や海外出張では“想定外”が日常茶飯事なんです。
でも、その都度『どうやって切り抜けるか』を考えることで、語学力だけじゃなく交渉力やマネジメント力が鍛えられます。私はそこにやりがいを感じていましたし、いつの間にか『これが自分の得意分野なんだ』と思うようになりましたね。

5.就活生へのメッセージ:「まず動いてみる」人脈が道を開く
5-1. 人を好きで送り出す、会社を好きで辞めてもらう
創業から35年以上経つ企業だからこそ、人材の採用や退職にまつわるエピソードも数多くあったかと思います。経営面で特に大切にされているポリシーがあれば教えていただけますか?
私が大切にしているのは、『辞める社員にも会社を好きなままでいてほしい』という姿勢ですね。人材が辞めること自体は、人生の局面で仕方のないことです。そこで無理に引き止めるよりも、『今までありがとう』と気持ちよく送り出したほうが、お互いにプラスになるはず。特に北九州は人脈のつながりが強い土地柄なので、円満に卒業してくれた人は“出戻り社員”として戻ってくることもあるし、あるいは別の場所からアウルズのファンになってくれる可能性も大いにあります。
意地悪をして去られてしまえば、そこで関係は終わってしまいますよね。でも、お互いをリスペクトしたまま縁が残れば、いつか新しい形で一緒にプロジェクトをやるチャンスが巡ってくるかもしれない。私は“人が好き”ですから、そのつながりを大切にしてきたら、いつの間にか今のネットワークが築かれていたという感じです。
たしかに、“会社を好きなまま辞められる”というのは珍しくもあり、素敵な考え方ですね。
それが結果として、人材流出ではなく新たなビジネスチャンスを生むきっかけになることも珍しくありません。嫌われて去られるより、好かれて去ってもらったほうが、絶対にいいでしょう? だからこそ、私は“人を大切にする”というのを経営の根本に据えています。
5-2. “Sky is the limit!”──限界を自分で作らない
最後に、就活生に向けてアドバイスやメッセージをお願いします。
私が好きな言葉に、“Sky is the limit!”というフレーズがあります。文字どおりだと『空が限界』となりますが、“実質的には限界なんてない”という意味合いでよく使われます。就職活動をしていると、『自分には何も強みがない』『英語が苦手だから海外なんて無理』などと思い込んでしまう人が多いんですよね。でも、実際には“やってみないとわからない”んです。
私自身、市長から『法人化したら?』と背中を押されたときは、まさか国際会議を企画運営する会社にまでなるとは思っていませんでした。けれど、一歩踏み出してみると予想外のご縁が生まれて、気づけば世界中で活動していたりする。大事なのは語学力の完璧さより、“伝えたい想い”と“行動力”です。英語がちょっと下手でも、現地でジェスチャーを交えながら必死に伝えれば通じることも多いですよ。
ですから、“Sky is the limit!”という気持ちを忘れずに、自分の可能性を狭めずにどんどんチャレンジしてほしいですね。人生は何が起こるかわかりませんから、最初から限界を決めてしまうのはもったいない。若い皆さんこそ、その一歩を踏み出せるエネルギーを持っていると思います。
ありがとうございます! 木下会長のお話を伺っていると、“自分で天井を決めない”という大切さがひしひしと伝わってきます。今日は本当に勉強になりました。
こちらこそ、最後まで熱心に聞いてくれてありがとう。アウルズは、これからも北九州から世界へ“言葉”で挑戦を続けます。もし興味があれば、いつでもインターンや見学に来てください。一緒に“限界なんてない”未来を作っていきましょう!
今回の取材を通じて、アウルズが単に“翻訳・通訳を提供する会社”にとどまらず、“言葉を武器に世界を動かす総合コーディネーター”として活躍している姿が浮き彫りになりました。英語教育ではプリスクールやALT派遣を通じて小さな子どもの未来を支え、コンベンション事業では国際会議の企画・運営を全面的にサポート。その根底には、木下会長が語る「まずやってみよう」「人とのつながりを大切にしよう」という精神がしっかりと根付いているのです。“Sky is the limit!”という言葉が示す通り、最初から自分の限界を決めてしまうのは惜しいこと。英語に自信がないと感じている人も、海外との接点が少ないという人も、まずは小さな一歩を踏み出してみる。そこから大きく広がる未来の扉を、アウルズのストーリーが力強く示してくれています。