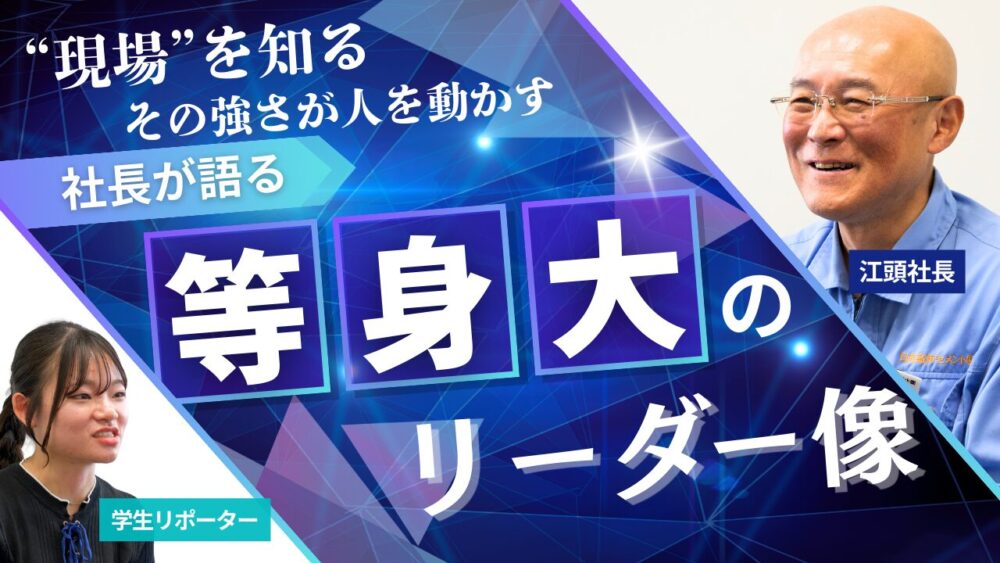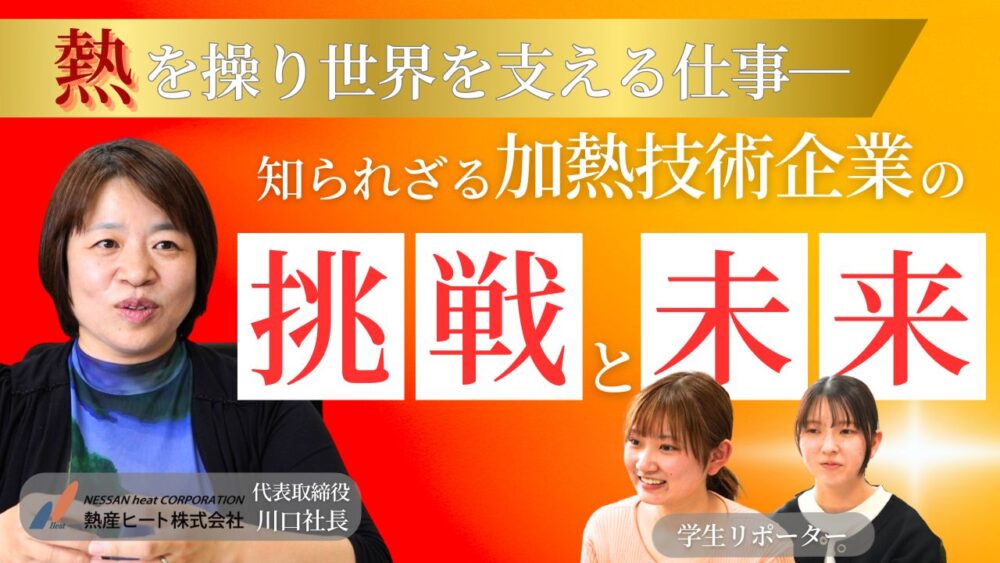「カブトムシ」と聞いてあなたは何を思い浮かべますか? 子供時代の夏休みに山や森で捕まえた記憶、飼育ケースの中で観察日記をつけたこと、あるいは大ヒットしたゲーム『ムシキング』で友達と競った楽しい日々を懐かしく思い出す人もいるかもしれません。しかし、現代社会でカブトムシをビジネスとして活用し、循環型経済の中核を担おうとしている企業があります。それが株式会社TOMUSHIです。
同社は一見遊びの対象にしか思えないカブトムシを使い、「資源循環」という現代的な課題に立ち向かっています。なぜ今、カブトムシなのか? どうしてそのようなユニークな発想に至ったのか?今回は、TOMUSHIの代表取締役・石田社長に、二人の学生が詳しく話を聞きました。
「カブトムシで資源循環」って、一体どういうこと?
本日はよろしくお願いします!早速なんですが、まず「TOMUSHI」という会社が具体的にどんなことをされているのか教えていただけますか?
こちらこそよろしくお願いします。TOMUSHIは一言で言うと、「カブトムシを使った資源循環ビジネス」をやっている会社です。廃棄されるはずだったものを再資源化し、それを別の価値に変える仕組みをつくっています。
たとえば、キノコを栽培した後に残る「廃培地」や、食品工場から出る「野菜くず」「果物の皮」など。これらは多くの企業が廃棄物としてお金を払って処理しています。けれど私たちは、それを“幼虫のエサ”に活用しているんです。
廃棄物がエサになるんですか? カブトムシって、そんなものも食べるんですね。
そうなんです。カブトムシの幼虫は非常に優れた“分解者”で、腐植物や有機残渣を分解する能力があります。特に水分を多く含んだ素材でも問題なく食べてくれるのがポイントで、他の昆虫、たとえばコオロギやミルワームにはできない芸当なんです。
コオロギとかって、今すごく注目されてますけど、逆にできないこともあるんですね。
はい、たとえばコオロギは乾燥させた餌じゃないと育ちにくいんですよ。その分、加工や乾燥の手間、コストがかかる。でもカブトムシの幼虫なら、レトルト工場の出荷前廃棄物や、濡れたキノコの廃培地など、手を加えずそのまま食べてくれる。処理コストがかからないのに、生物の力で分解され、さらに栄養として活用される。これはすごく経済的なんですよ。
しかも、それを食べた幼虫が成長して……また何かに使われるんですよね?
そうです。まず、幼虫が排出する「フラス」——つまり糞ですね。これがすごく栄養価の高い有機肥料になるので、農家さんに提供しています。そして、ある程度育った幼虫や成虫は、粉末化して養殖用の魚や家禽(鶏など)の餌として活用しています。
まさに“無駄がない”仕組みですね。エサにもなって、肥料にもなって……。
はい、だから私たちは「育てる」「食べる」「排出する」「使う」というサイクルを、カブトムシで回しているんです。ゴミだと思われていたものを命に変え、それがまた次の命を育てていく。この循環がうまく回り始めたとき、「これって資源循環の新しい形だな」と実感しましたね。
正直、「カブトムシで起業した」って最初に聞いたときはピンと来なかったんですけど……今のお話で一気に納得しました。
ありがとうございます(笑)。でも実際、こうして説明すると皆さんびっくりされますし、「すごく理にかなっている」と言ってもらえることが多いですね。

意外な創業秘話と壮絶なスタート
ここまでのお話で、カブトムシを使ったビジネスがどれほど可能性に満ちているかは伝わってきました。でも、そもそもなぜ「カブトムシで会社を作ろう」って思ったんですか?
正直、始まりはものすごく個人的で、ふざけたような動機なんですよ(笑)。僕、小さいころ「ムシキング」っていうゲームにドハマりしていて。当時はゲーセンに通って、カードを集めて、友達と真剣勝負してました。双子の兄も同じように熱中してて、その記憶がずっと残っていたんです。
懐かしいです!私も小学生のときにやってました。ムシキングって、男子の間で一大ブームでしたよね。
そうそう。あの頃の“カブトムシ=ヒーロー”という感覚が、今思うと僕の原点かもしれません。大学を辞めたとき、「自分に何ができるか」を真剣に考えたんです。いろんなことをやろうとしたけれど、どれも“やらされてる感”が強かった。でも、「好きなことなら夢中になれる」って思って。
それで、カブトムシを思い出したんですか?
はい。兄と2人で「カブトムシ買ってみる?」って軽いノリで(笑)。そこから、外国産のカブトムシをネットで大量に購入しました。おばあちゃんの家の一部屋を借りて、そこを飼育場にしたんですけど……数百匹単位で虫がいる空間って、なかなか壮絶ですよ(笑)。
うわあ、想像しただけで……おばあちゃん、びっくりしませんでした?
びっくりどころか、本気で怒られました。「虫と一緒に暮らすなんて無理!」って(笑)。でも僕は「これは家族だ!」とか意味不明なことを言って全然引かなくて。
いや、それは強い(笑)。でも、そのまま趣味で終わらず、会社にしたのがすごいですね。
実はそのとき、「ちゃんと会社にするから」とおばあちゃんにお願いして、クレジットカードを借りてカブトムシを買い続けたんです。そしてついに祖父母から500万円を出してもらって、さらに銀行から1500万円を借りて、合計2000万円で事業をスタートさせました。
初期投資、なかなかの額ですね……。
そうなんです。今思えば、あまりにも無謀でした。でも、やってみたかったんです。「誰もやってないことを、本気でやるってどういうことか」知りたかった。最初のビジネスモデルは「珍しいカブトムシを繁殖させて売る」っていう、めちゃくちゃシンプルなものでした。
でも、それってうまくいかなかったんですよね?
全然ダメでした。飼育のノウハウも甘くて、温度管理も設備も不十分だったので、カブトムシがどんどん死んでいく。そのたびに心が削られていきましたね。
資金的にも、厳しかったのでは?
はい。数ヶ月で2000万円がほぼ消えました。気づけば、通帳には30万円しか残っていない。社員も離れていって、自分ひとり取り残されたような感覚になりました。完全に詰んだと思いましたよ、本当に。
……その状態から、よく再起できましたね。
まさに「どん底」でした。でも、そのタイミングで銀行の担当者が「キノコ農家の廃棄する培地を餌に使えないか」って提案してくれたんです。それが、TOMUSHIの再出発のきっかけになりました。
逆境からの劇的な再起
それにしても、社員がいなくなって、資金も底をついて……そこから再起するのは本当にすごいことですよね。何がきっかけになったんですか?
きっかけは、銀行の担当者のひと言でした。「最近、キノコ農家で廃棄されてる培地が大量にあって、処分に困ってるらしいんです。あれって……カブトムシに使えたりしませんかね?」と。正直、最初は「無理だろう」と思いました。でも、もう試すしかなかったんですよ。
本当に背水の陣だったんですね。
はい、もはや“やるか倒れるか”の状況だったので、すぐにキノコ農家に連絡を取り、現場から廃培地をもらってきました。で、それを幼虫に与えてみたんです。そしたら、ものすごい勢いで食べる。しかもちゃんと育つ。これは……とんでもない可能性があるぞって、ゾクッとしましたね。
実験が成功した瞬間って、どんな気持ちでしたか?
正直、“命が繋がった”と思いましたね。たかが餌、されど餌。カブトムシが生き延びてくれるだけで、自分もまた前に進める気がしたんです。
そこからどうやって事業に発展させていったんですか?
まずは廃棄物を安定供給してくれるパートナー企業を探しに回りました。地元のキノコ農家、野菜工場、酒造会社……。最初は「なんでカブトムシ?」と怪訝な顔をされることも多かったけれど、「これ、処分にお金かかってるんですよね? こっちで引き取って有効活用できます」と説明すると、少しずつ協力してもらえるようになりました。
でも、餌が手に入るようになっても、運営ってすごく大変ですよね。
そうですね。次は「小さなプラント」を作る必要がありました。大企業のように大規模な設備投資はできないので、プレハブの倉庫を改装したり、農業用ビニールハウスを利用したりして、とにかく“今あるものでやる”というスタイルを徹底しました。
それって逆に、どこにでも展開できる柔軟なモデルですよね。
まさにその通りです。むしろ、“小さくて、地域密着で、変化に強い”という強みが生まれました。その後は、事業モデルをパッケージ化して他の地域にも導入してもらえるように整備していきました。
そこまで仕組み化するのに、どれくらい時間がかかったんですか?
最初のプラントが安定して回るようになるまでに1年くらいはかかりました。現場で失敗も繰り返しましたし、設備の温度が合わなかったり、想定よりフラスの発酵が進まなかったり……。でもその都度、試行錯誤して「生きたノウハウ」が蓄積されていったんです。
そこまで地道な努力があってこその今なんですね。
ええ。そして今では、全国103ヶ所にまで拠点が増えました。一番嬉しいのは、各地域で「これはうちの誇りだ」と言ってもらえるようになったことですね。廃棄物が資源に変わり、地域の仕事になり、地元の人たちの誇りになっていく——それがTOMUSHIの目指す“循環”なんです。
若手中心のチームの秘密
TOMUSHIのことを調べていて驚いたのが、チームの平均年齢が若いということでした。実際、どのような方たちが集まっているんですか?
そうですね、平均年齢は25歳くらいです。いわゆる“スタートアップらしさ”があって、フラットでエネルギッシュな組織です。もともと僕自身が若いうちに起業したこともあって、「若い人が活躍できる会社にしたい」という思いが強かったんです。
メンバーの経歴もすごく多様なんですよね?
はい、証券会社で働いていた人、九州電力からの出向者、農業の現場にいた人、大学で昆虫の研究をしていた博士号持ちの研究者までいます。本当にバラバラ。でも、共通しているのは「カブトムシが好き」と「社会に何かを残したい」という想いですね。
それだけ多様だと、どうやって採用してるんですか?就活生向けの求人を出してるとか……?
実は、ちゃんとした採用活動ってあまりしてないんです(笑)。自然に縁がつながって、声をかけたりかけられたりして集まってきた感じですね。たとえば、証券会社の営業担当だった人は、うちの財務周りを担当してくれてたんですけど、あまりに「もっとこうした方がいい」と言ってくるので、「じゃあ、うちでやってみたら?」と誘ったら、来てくれました。
えっ、それで来てくれるんですか!?
はい(笑)。逆に言えば、本人も「ここでなら自分のやりたいことができる」と思ってくれたということだと思います。他にも、JAで米作りをしていた人に「稲じゃなくてカブトムシ育てない?」と冗談半分で言ったら、「面白そうですね」と本当に来てくれたり。
なんだか、リクルートというより“仲間集め”に近い感じですね。
まさにそうです。僕たちがやっていることって、前例がないからこそ「やってみたい」と思える人じゃないと続かない。でも、だからこそワクワクしながら挑戦できるし、そういう空気感があるんです。
そういったチームの雰囲気って、どんな感じなんですか?
全体的に、めちゃくちゃフラットです。年齢や立場関係なく、誰でも意見を言えるし、どんどんアイデアを実行していける。たとえば「もっと発信力を強化しよう」という話になったときに、入社1年目の子が「動画撮ってTikTokに載せましょう」と提案して、実際にバズったこともあります。
それはすごい……。若手の声がちゃんと反映されてるんですね。
うちは「上司が言ったから」ではなくて、「やってみたいと思った人が行動する」文化です。もちろん失敗することもあるけど、それすら“ネタになる”というか、共有して笑い合える関係があるんです。だから、怖がらずにどんどんチャレンジできる。
失敗しても責められない環境って、すごく働きやすそうですね。
はい。だからうちでは“仕事が楽しい”って言うメンバーが多いんですよ。やらされてる仕事じゃなくて、自分たちで選んで動けるから。そういう空気に惹かれて、また新しい仲間が自然と集まってくる。今もなお、“虫好き”な人からDMが来たりするんです(笑)。
「虫好きで社会貢献したい」って、ちょっとニッチだけど……めちゃくちゃ熱いですね!
そうなんですよ。普通なら“変わってる”と思われる人が、うちではヒーローになれる。そんな会社を、これからも作っていきたいですね。

カブトムシの可能性とこれからの挑戦
カブトムシを活用したビジネスはすでに成功されていますが、今後さらに取り組みたいことや新しい挑戦について教えてください。
はい、今後さらに大規模な施設を整備し、より効率的に生産を拡大していきたいと考えています。また、カブトムシの幼虫が作り出すタンパク質が、養殖業界などで非常に注目されているんですよ。特に最近では魚の飼料としての需要が増えていますので、魚粉の代替飼料としての普及を目指しています。
養殖業界にまで展開されるとは驚きました。他にはどのような可能性があるのでしょうか?
海外への展開も視野に入れています。特に東南アジア地域は気候的にも適していて、現地の廃棄資源を活用することで環境問題の解決にも貢献できると思っています。将来的には国際的な循環型モデルとして広く認知されることを目指しています。
カブトムシの活用が世界規模で進むのはとても楽しみですね。
はい、まさにカブトムシが環境保護や持続可能な社会づくりの象徴として広がっていくことを願っています。
石田社長の哲学「失敗はネタになる」
石田社長のお話って、すごく前向きで、聞いていて元気が出ます。でも、やっぱり最初の事業がうまくいかなかった話とかを聞くと、「自分だったら立ち直れるのかな……」って正直不安になります。
気持ちはすごく分かりますよ。でもね、僕がずっと思っているのは、「失敗って、人生で一番面白いネタになる」ということなんです。成功って、他人からすれば「すごいですね」で終わっちゃう。でも、失敗はみんなが笑えるし、共感できるし、学びがあるんですよ。
たしかに……飲み会とかで盛り上がるのって、成功談より失敗談だったりしますよね(笑)。
そうそう(笑)。だから僕は、あえて“ネタになる失敗”をしにいってるところもあるんです。「どうせやるなら、盛大に転べるところまで行こう」と。もちろん、借金して会社潰すようなことになれば大変ですけど、それでも命が取られるわけじゃない。
そのくらいのメンタルで動いてるんですね……。でも実際、失敗って怖くないですか?
怖いですよ、当然。でも僕は、怖いときほど「誰かに話す」ようにしています。隠して一人で抱えてしまうと、どんどん自分を責めてしまう。でも、人に話してみると「え、それだけ?」「それ面白いじゃん」って言ってもらえることが多くて。それで気づくんです。「あ、自分が思ってるほど大ごとじゃなかったな」って。
それって、チームの中でも意識されてることなんですか?
めちゃくちゃ意識してます。TOMUSHIでは、失敗を共有する文化を大事にしていて、誰かがやらかしたら隠さずみんなに共有する。それで笑って終わる。そうやって「失敗=悪」じゃなくて「失敗=面白い・学べること」っていう空気を作っていくんです。
それなら、挑戦するのが怖くなくなりますね。
そうなんですよ。むしろ「何かに挑戦して失敗する」って、チームにとってはありがたい経験になる。成功って再現が難しいけど、失敗は「何がダメだったか」が明確だから、再現性のある学びになります。
たしかに、失敗から学んだことって、次の仕事で活かせたりしますもんね。
その通り。そして、若いうちは特に失敗していいと思ってます。年齢を重ねると、責任とか守るものとかが増えて、チャレンジしにくくなる。でも若いときは、多少転んでも人生はやり直せる。むしろ、いっぱい転んだ人ほど“味のある人間”になれると僕は信じてます。
今、まさに就職活動中でいろいろ不安だったけど……なんだか「やってみようかな」って気持ちになってきました。
うれしいですね。僕の考えとしては、「就職=正解」でも「起業=成功」でもなく、「自分が何にワクワクするか」を選ぶことが一番大事だと思ってます。だから、迷ってるなら、やってみる。転んだら笑えばいい。笑えないなら、それを話せば、誰かが笑ってくれる。そうやって次に進めばいいんです。
めちゃくちゃ励まされました……。石田さんのような考え方を持てたら、もっと前向きに挑戦できそうです。
ぜひそうなってください。そして、もし将来失敗して「どうしよう……」って思ったら、そのときは僕にDMしてください(笑)。一緒に笑ってネタにしましょう!
“好き”を仕事にすることは、無謀で現実味のない選択に思えるかもしれません。
けれど石田社長の歩みは、それが社会を変える原動力になり得ることを教えてくれました。
カブトムシから始まった挑戦が、資源循環の新しい形となり、今、多くの人と地域を巻き込んでいます。
迷ったときこそ、自分の“好き”を信じてみる——そんな選択肢も、あなたの未来にはきっとあるはずです。