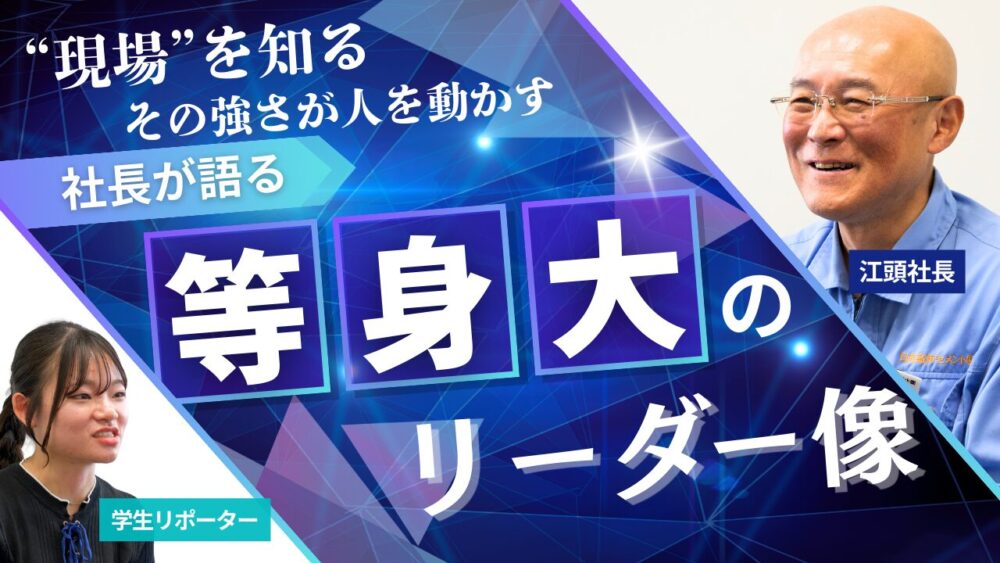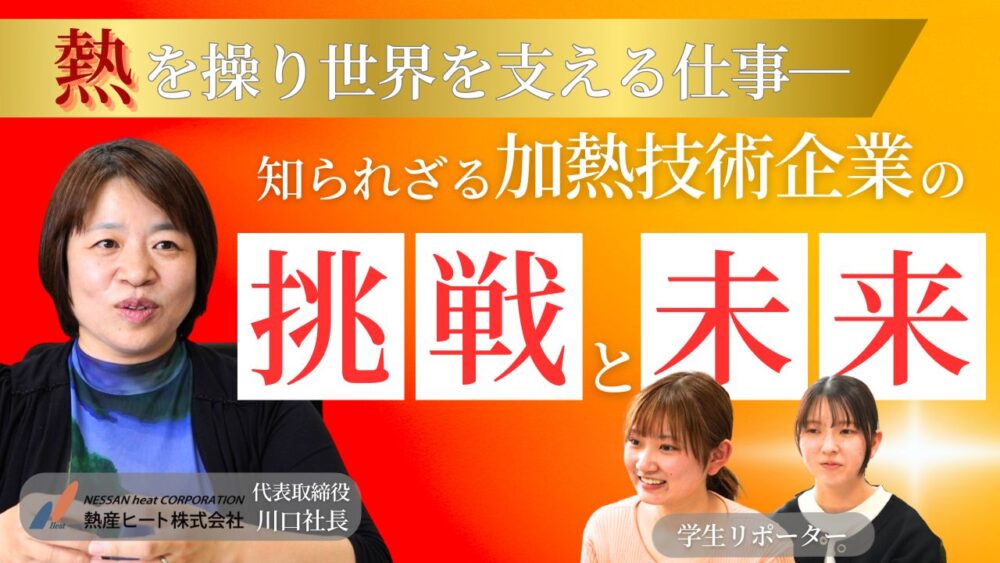「建設業界って、文系でも入れるの?」「ゼネコンって何をする会社?」
そんな疑問を抱える就活生は多いのではないでしょうか。
福岡を拠点に公共工事を中心に手がける松鶴建設は、そんなイメージを良い意味で裏切る存在です。
“最後のゼネコン”とも称されるこの企業には、若手を信じて任せる文化、地方企業としては異例のスケール感ある仕事、そして人に惹かれて入社を決めた社員たちがいます。
今回は、松鶴建設の川田社長と採用担当の久保さんにインタビューを行い、学生リポーターが同社のリアルな魅力に迫ります。

文系でも活躍できる、“人”が動かす建設の仕事
今日はよろしくお願いします。さっそくなんですが、「ゼネコン」って言葉はよく聞くものの、正直どんな会社なのかよくわからなくて…。松鶴建設は、どんなことをしている会社なんでしょうか?
よろしくお願いします。そうですよね、「ゼネコン」って言葉は耳にするけど、意味まで知ってる人って意外と少ないんですよ。
松鶴建設は、その「ゼネコン」、つまりゼネラル・コントラクター(General Contractor)として、公共工事を中心に手がけている建設会社です。
公共工事というと、道路とか橋みたいな…?
その通り。うちが主にやってるのは、道路や橋の整備、下水道の更新、川の護岸工事といった土木インフラの工事です。建物を建てる「建築」じゃなくて、暮らしの土台を整える「土木」が中心ですね。表には出にくいけど、地域の生活を支えるすごく大事な仕事なんですよ。
てっきり建設業って、ビルを建てたりするものだと思ってました。
そう思う人も多いですよね。でも私たちゼネコンの仕事って、実はもっと“街全体”に関わるような内容なんです。ちなみに、「元請け」って言葉を聞いたことありますか?
うーん…なんとなく、工事の一番上にいる会社ですか?
まさにそのイメージでOKです。うちは「元請けゼネコン」として、国や自治体と直接契約を結び、工事全体を管理する立場です。実際の作業は、専門の協力会社さんたちにお願いしながら、全体の指揮や調整をするのが私たちの役割なんですよ。
じゃあ現場での仕事って、力仕事よりも“まとめる”ことが多いんですね。
そうなんです。工事の進行管理や安全管理、品質チェック、予算や書類の調整など、“段取りと判断”が求められる仕事です。いわば現場の司令塔のような存在ですね。
なんだか想像していた建設業と全然違って、頭も使いそうですね…。理系の人が多いんですか?
もちろん理系出身の社員もいますが、文系出身の社員も多いですよ。必要な知識は入社してから覚えれば大丈夫。むしろ現場で大切なのは、人とのコミュニケーション力や調整力、責任感だったりします。
そう聞くと、建設業もすごくチームプレイなんですね。
一人でできる仕事じゃないからこそ、チームでうまく回していく力が大事なんです。だから、ゼネコンの仕事って意外と“人間力”が問われるんですよ。
文系でも活躍できるのは意外でした!ゼネコンって、もっと遠い世界の話だと思ってました。
そう思われがちだけど、実際に入ってみると「自分でもできるかも」って感じるはずです。それに、自分が関わった道や橋が何十年も残る。そんな誇れる仕事って、なかなかないと思いますよ。
倒産2回からの再出発。信頼で築いた30年
創業30年とのことですが、松鶴建設は最初から今のような形だったんですか?
実はそうじゃないんです。うちをつくった創業者は、もともと別の会社を2回立ち上げていて、2回とも倒産を経験しているんですよ。
2回も…。それでまた会社を始めようと思ったのがすごいですね。
本人も相当な覚悟だったと思いますよ。1回目は鉄鋼関係、2回目は建設業。いずれも厳しい経営環境の中でうまくいかず…。ただ、建設の仕事自体には手応えを感じていたので、「もう一度ちゃんとやり直したい」という思いで松鶴建設を立ち上げたんです。
立て直すって、言葉で言うよりずっと大変そうです…。
本当にそうだったと思いますよ。特に当時は、いわゆる“手形払い”が多くて。工事をしても、代金の一部は「3か月後に支払いますよ」という約束の紙で払われることが普通でした。で、その紙を出した会社が潰れたら、ただの紙切れになってしまう。
え、それって…現金が入らないってことですよね?
そうなんです。どれだけ真面目に工事をしても、取引先が倒れたら一緒に巻き込まれる。そういう経験が何度もあって、「これはもう、自分たちで直接仕事を受けて、自分たちで管理していかないと危ない」と痛感したんです。
なるほど…。そこで、公共工事に目を向けるようになったんですか?
そうです。公共工事は行政との直接契約になるので、支払いがきちんとしていて安定しています。もちろん簡単に参入できるわけではないけど、「リスクを減らすならここしかない」と考えました。
でも、そういう工事って、新しい会社がすぐに参加できるものなんですか?
それがなかなか難しいんですよ。当時は“昔ながらの業者さん”が多くて、新しく入ってきた会社には厳しかった。実績がないと声もかからないし、競争の土俵にもなかなか上がれなかったです。
それでもあきらめなかったんですね。
もちろんです。役所に何度も足を運んで、担当の方に顔を覚えてもらって。「小さな仕事でもいいからやらせてください」とお願いして、コツコツ信頼を積み重ねていきました。最初に受けた工事は、500万円くらいの小規模なものでしたけど、そこから少しずつ広がっていきましたね。
地道な積み重ねが、今につながってるんですね。
そうですね。一つひとつ、丁寧に。実績を出して、評価をもらって、少しずつ大きな仕事も任されるようになりました。もちろん最初は、「若い会社だから…」と厳しい目を向けられることもありましたよ。でも、やるべきことをしっかりやれば、ちゃんと見てくれている人はいるんです。
リーマンショックのときも、やっぱり影響があったんですか?
影響は大きかったですね。民間の工事が一気に減って、「この先どうなるんだろう」って。でも、うちはそのときすでに公共工事に力を入れ始めていたので、なんとか踏ん張ることができました。その経験もあって、今は「地に足のついた経営をしよう」と意識しています。
お話を聞いていると、会社の土台が“挑戦”と“信頼の積み重ね”でできている感じがします。
まさにその通りです。うちは特別な武器があったわけじゃありません。ただ、諦めずに動き続けて、誠実にやってきた。それが今の松鶴建設につながっていると思います。

「ルール通りじゃ、進めない。」業界の“見えない壁”と、信頼を築く力
さっき、新しく公共工事に入るのは大変だったとお話がありましたが、建設業界ってそういう“見えないルール”みたいなものが多いんですか?
そうですね。昔に比べたらだいぶ透明になってきたけど、当時はやっぱり「慣習」が根強く残っていましたね。競争入札って建前はあっても、実際には「この地域はこの会社が…」みたいな、暗黙の了解のようなものがあったんです。
それって…入札のときに、あらかじめ“誰が取るか”が決まっていたような感じですか?
そういう空気はたしかにありましたね。新しく参入したいと思っても、「あの会社が取る予定だから今回は入らないでくれ」なんて言われることもありました。
えっ、そんなことが…!正直、驚きです。
私たちが参入しようとした当初も、何度かそういう場面がありましたよ。でも「ルール上問題ないなら入ります」と、自分たちで判断して行動しました。もちろん周りからは反発もありましたけど、それでも堂々とやるべきことをやっていれば、少しずつ認めてもらえるようになっていくんです。
信念を持って動いていたからこそ、ですね。
はい。でも、ただ突っ走るだけじゃダメで。役所の方々ともきちんと信頼関係を築いて、「この会社に任せて大丈夫だ」と思ってもらうことが大切でした。工事って、ただ技術があればいいというより、人とのつながりがものすごく重要なんですよ。
実績がないと話を聞いてもらえないような状況だったんですか?
最初はそうでしたね。だから、どんなに小さな仕事でも「しっかりやる」。それを繰り返すことで「この会社はちゃんとやるぞ」と信頼が少しずつ積み上がっていくんです。特別な何かがあったわけじゃありません。
地道な積み重ねが、結局いちばん強いんですね。
本当にそう思います。たとえば、以前こんなことがあったんですよ。ある現場で、他の会社さんが長期間なかなか進められずにいた工事があって、うちに「引き継いでやってもらえませんか?」と相談が来たんです。
それって、かなりプレッシャーがかかりそうですね…。
ええ、でも「引き受ける以上は、ちゃんとやり切る」と腹をくくって。結果的に、その現場は予定よりも早く終わらせることができました。あとから聞いた話なんですが、「前の会社のときは住民から苦情が絶えなかったのに、松鶴さんが来てから落ち着いた」と言われたそうで。それは本当にうれしかったですね。
現場って、住民の方とも距離が近いんですね。
そうなんです。特に都市部の工事だと、工事車両の音や振動、交通規制など、地域の方への影響が避けられません。だからこそ、丁寧に説明して、できるだけ迷惑をかけないように気を配る。それも、私たちの大切な仕事の一つなんですよ。
なんだか“工事”っていうより、“人と向き合う仕事”という感じがしてきました。
本当にその通りです。技術やスピードも大事だけど、一番大切なのは「誠実であること」。信頼を得るって、そういう積み重ねから生まれるものですからね。

「入社3~5年目でも“現場の責任者=社長”」若手にこそ任せる理由がある。
松鶴建設について調べていると、「若手にもどんどん現場を任せる」という言葉を見かけました。それって本当なんですか?
はい、本当です。うちでは、入社して数年の若手社員にも現場を任せる機会があります。もちろんいきなり一人に全部を背負わせるようなことはしませんが、段階的に裁量を持たせて、責任をもって仕事に取り組んでもらうんです。
そんなに早くから任せてもらえるのって、ちょっと緊張しそうです…。
そうですね。でも逆に言えば、任されるからこそ成長も早いんです。自分が中心になって動くと、考え方も変わってきますし、仕事に対する責任感も自然と育っていきます。うちはそれを「現場の社長」って呼んだりしてるんですよ。
現場の社長…!なんだかすごい響きですね。
現場には所長という立場があるんですが、そこまで任せられるようになると、本当に一つのチームのトップとして働くことになります。もちろん困ったときには先輩や会社がしっかりサポートしますよ。でも、基本は「自分で考えて、自分で動く」。そういう姿勢を大事にしています。
文系出身でも、そういう立場になれるんですか?
もちろんなれますよ。実際に、文系で入社して、今では現場を任されている社員もいます。最初は右も左もわからなかったけど、現場に出て、職人さんや上司に教えてもらいながら、どんどん成長していった。そういう姿を見るのが、私たちにとっても嬉しいんです。
どんどん成長していく姿は確かに嬉しいですね!でもやっぱり、最初から任せるのって不安じゃないですか?
もちろん全く不安がないわけじゃありません。でも、それ以上に「任せることで見えるものがある」と思っているんです。たとえば、先輩について見ているだけでは気づかないことも、実際に自分がやってみると見えてくる。失敗を経験してこそ、次に活かせるものがあるんですよ。
それって、働く側としても信頼されてるって感じられそうですね。
そうだと思います。自分が任された現場が無事に終わったときの達成感って、本当に大きいんです。「自分の判断でやりきった」っていう実感が、自信にもなります。
実際、どれくらいで現場を任されるようになるんですか?
早い人だと、入社して3~5年目くらいで所長を任せることもあります。ただ、それには現場経験や資格が必要で、「1級土木施工管理技士」という国家資格も条件の一つになります。これは実務経験を積んだうえでないと受験できないんですが、社内でサポート体制もしっかり整えていますよ。
現場を動かすと聞くと、すごく大変そうだけど、やりがいは大きそうですね。
ええ、大変さは確かにあります。でも、自分の判断で人を動かし、工程を進めて、無事に終わったときの達成感は格別です。誰かの指示だけで動いていた頃とは、仕事の見え方がまったく変わってくるはずです。
なんだか、“育ててもらう”っていうより、“育っていく”環境なんですね。
いい表現ですね。うちは「自由と覚悟」っていう言葉を大切にしていて、自由にやっていいけど、その分責任も持つ。それが仕事の面白さにもつながっていくと思っています。
「地上に残らない仕事が、まちを守っている。」
これまでのお話から、松鶴建設がいろんな現場を手がけてきたことが伝わってきました。その中で、特に印象に残っているプロジェクトってありますか?
いくつかあるんですが、一つは東京で担当した「鴨場(かもば)」という施設の工事ですね。これは宮内庁の関連施設で、一般的な工事とは少し違う、特殊な現場でした。
宮内庁…!すごいですね。それって、どんな場所なんですか?
鴨場は、外国からの賓客をもてなす場所で、自然に囲まれた静かな敷地の中に建物があって、アヒルや鴨を使った伝統的な接待が行われるんです。私たちは、その中の一部施設の新設工事を担当しました。
なんだか想像がつかない世界です…。大変だったことってありましたか?
そりゃもう、いろんな意味で気を遣いましたよ(笑)。作業音や振動はもちろん、景観や敷地内の自然環境にも細心の注意が必要で。工事の内容自体は特別難しいものではなかったんですが、求められる“空気感”を壊さないことが一番の課題でした。
たしかに、宮内庁の仕事って聞くと、ちょっと緊張しちゃいそうです…。
そうですよね。実際、この工事は受注に至るまでの経緯も印象的でした。当初、なかなか契約が決まらず、20社以上が入札に参加した末、最終的に「松鶴さんにお願いできませんか」と声をかけてもらったんです。
そのときって、やっぱりプレッシャーも大きかったですか?
正直、かなりありました(笑)。採算的には正直厳しい案件でしたが、「この経験は今後の財産になる」と思って、覚悟を決めて引き受けました。結果的に、それが実績として残り、別の仕事にもつながったんです。
どんな仕事も、次につながっていくんですね。
まさにその通りです。あとは福岡でやった「山王公園の地下貯水施設」の工事も、かなり記憶に残っています。これは大雨による浸水被害を防ぐために、地中に巨大な貯水槽をつくる工事でした。
それって、普段私たちが歩いてる地面の下にあるんですか?
そうなんですよ。地上からは見えませんが、地下に大きな空間があって、豪雨のときには一時的に水をためて街が浸水しないようにするんです。完成してしまえば、誰も気づかない場所。でも、まちの安全を守る大事なインフラなんです。
すごい…。まさに“見えないところで支えてる”って感じですね。
そういう仕事こそ、建設の面白さだと思うんです。目に見える派手さはないかもしれないけど、災害を防いだり、暮らしを守ったりする。そういう部分に携われるのが、この仕事の魅力ですね。
たしかに、私たちが普段安心して暮らせているのって、こういう工事があるからなんですね。
工事って、完成したときに「わっ」と注目されることは少ないけど、日常の中でふと気づいたとき、「この道、実は自分たちがつくったんだな」って思える。それだけで十分誇らしいものなんですよ。

「この人と働きたい。」人に惹かれて集まる、あたたかい会社
会社の雰囲気としては、やっぱり“体育会系”な感じなんですか?
それ、たまに言われるんですけど(笑)、うちは意外とそうでもないんです。確かに元気はいいけど、ガツガツした雰囲気ではないですね。どちらかというと、フラットで話しやすい空気のほうが強いかもしれません。
そうなんですね。たとえば、社員同士の距離感ってどうなんですか?
距離は近いと思いますよ。実は年に3回、全社員と面談してるんです。4月・7月・12月って決めていて、そのタイミングで一人ひとりと時間を取って、近況を聞いたり、仕事の悩みを相談されたり。社員の顔をちゃんと見て話す場は、大事にしています。
社長が直接面談されてるんですか?それってなかなか珍しい気がします。
たぶん、あまり聞かないですよね(笑)。でも、人が増えても全員とちゃんと話せる関係でいたいんです。現場で頑張ってる社員たちの声を、社長が直接聞けるって大事なことだと思ってます。
たしかに、それだけで安心できそうです。
あとは…うち、社員旅行も毎年行ってるんですけど、基本的に費用は会社がほぼ負担してるんですよ。
会社が連れて行ってくれるんですか?
そう。頑張った分はちゃんと社員に還元したいし、「みんなでいい思い出をつくろう」っていう気持ちもありますから。過去にはシンガポールやグアムにも行きましたし、今度宮古島にもみんなで行きます。
それはすごい…!めちゃくちゃ楽しそうです。
仕事はもちろん真剣にやりますけど、メリハリをつけるのも大事。日々頑張ってくれているみんなへの感謝の意味も込めて、そういう場をつくるようにしています。
社長と社員の距離が近いからこそ、会社全体もあったかい雰囲気なんですね。
そう感じてもらえると嬉しいですね。私自身、社員のみんなには「仕事だけじゃなく、人生そのものが充実するような会社でありたい」と思っているので。大げさかもしれないけど、それくらいの気持ちで日々向き合っています。
ここまでお話を聞いてきて、会社としての考え方はすごく伝わってきました。もうちょっと社長ご自身のことも聞いてみたいんですが…社長はもともと建設の道を志していたんですか?
いやいや、実は僕自身、まったくそんなつもりはなかったんですよ(笑)。建設に興味があったわけでもなくて、たまたま縁があったというか、ある人との出会いがきっかけでした。
どんな出会いだったんですか?
うちの創業者ですね。とても情熱のある人で、「この人と一緒に働いてみたい」と思わせてくれたんです。正直、仕事の内容よりも「この人についていきたい」っていう気持ちが強かったですね。
人に惹かれて働くって、なんだか素敵ですね。
そうなんですよ。で、実際に一緒に仕事を始めたら、いろんなことを学ばせてもらって。気づけば僕が会社を引き継いで、今はこうして社長をやっているというわけです。
実は僕も惹かれて入社したって言うと社長と同じなんです。前職では旅行代理店に勤めていて、松鶴建設の社員旅行をサポートする立場だったんです。同行して現地での案内などをしていたんですが、びっくりしたのが社員と社長の距離の近さ。宴会で社員の皆さんが「給料上げろ〜!」なんて替え歌にして歌ってて(笑)それを社長が大笑いしながら聞いてるんですよ。「すごい会社だな!」って、強烈な印象を受けました。
そのときから、松鶴建設に惹かれていたんですか?
そうですね。当時から社長がすごく気さくで、僕のことも毎回気にかけて声をかけてくださってて。そんな中、コロナで旅行業界が打撃を受けていた頃に社長から一本の電話をもらったんです。「最近どう?」って。少し弱音を吐いたら、「うちに来てみないか?」って誘ってくださって。迷いもありましたが、社長の人柄と社員の雰囲気の良さはずっと印象に残っていたので、思い切って飛び込みました。あのときのご縁が、まさか自分の働く場所になるなんて、当時は想像もしていませんでしたけどね(笑)。
それだけ社長や社員の皆さんの人柄が印象的だったってことですよね。久保さんの話を聞いて、会社選びって仕事内容だけじゃなくて“人との出会い”も大事ですね。
社長も、創業時の社長に惹かれて松鶴建設に入社されて、 “人が人を惹きつけてつながっていく”ってすごく素敵だなと思いました。
ありがとう。うちはね、“人とのご縁”がすべての原点だと思ってるんです。だからこそ、一緒に働く仲間との関係性や信頼を大事にしたいし、これからも“人を育てる会社”であり続けたいですね。
本日は貴重なお話をありがとうございました!温かい社風や、皆さんのつながりの強さがすごく伝わってきました。
「建設=堅い仕事」というイメージを、松鶴建設はいい意味で裏切ってくれました。
若手に仕事を任せる風土、現場を動かすやりがい、そして人との信頼関係を大切にする文化。
そのすべてが、“人を育てる会社”という言葉を物語っています。
自分にできるか不安。でも、挑戦してみたい。
そんな想いを持つあなたにとって、一歩を踏み出すきっかけとなる場所かもしれません。